- 2025 03/21
- まえがき公開
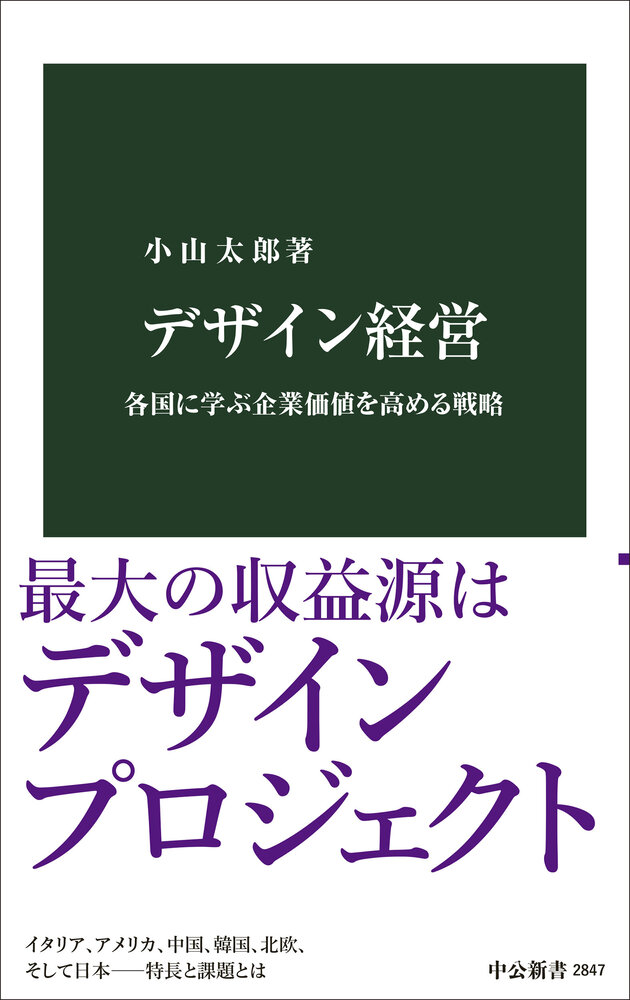
どれほど消費者調査をしても、人々が気付いていない未来のニーズは掘り起こせない。だが、デザインにはそれが可能だ。本書は、「デザイン経営とは何か」を解説し、デザインプロジェクト中心の経営とは何かを描く。イタリア、アメリカ、中国、韓国、北欧、そして日本の先進的な企業を紹介し、アパレル、インテリア、家電、自動車など、多様な事例から、デザイン経営の類型と特長を解説し、日本の進むべき道を提示する。
『デザイン経営 各国に学ぶ企業価値を高める戦略』の「はじめに」を公開します。
□ ■ □ ■ □ ■ □
はじめに
デザインが企業価値を高める
良いデザインとは何だろうか。
その一例として、サムスン電子の薄型パネルテレビを挙げることができる。それは、額縁に入れて飾られた絵画のようにインテリアになじみ、他の家具と比べても遜色ない存在感を放っている。世界市場でのシェアも常にトップである。
日本でも、デザインに注力することで好業績を上げている企業がある。たとえばバルミューダは、自然に吹く風を再現した扇風機や目立たずにインテリアの脇役となるような空気清浄機などをデザインしている(インテリアの主役になるのを目指さないなら目立たないほうがよい)。
こうした企業は、デザインへの投資を行うことで高い競争力を保ち、営業利益や株価の面で高いパフォーマンスを発揮している。イギリスのデザイン評議会の報告によると、1ポンドのデザイン投資は、4ポンドの営業利益増をもたらし、また、デザイン賞を受賞する企業の株価は、市場平均と比べて2倍の成長を達成するということである。さらに、デザインへの投資は、売上高などの財務指標にプラスの影響を与えるのみならず、顧客満足度や購入意向も高めることが、近年続々と発表されている研究から明らかになっている。デザイン経営の推進は、今や世界的なトレンドである。
こうしたデザイン経営を取り巻く状況に鑑み、2018年に発表されたのが、経済産業省・特許庁の「産業競争力とデザインを考える研究会」による「「デザイン経営」宣言」である。
この宣言では、「「デザイン経営」は、ブランドとイノベーションを通じて、企業の産業競争力の向上に寄与する」としたうえで、次のようにいう。
デザインは、企業が大切にしている価値、それを実現しようとする意志を表現する営みである。それは、個々の製品の外見を好感度の高いものにするだけではない。顧客が企業と接点を持つあらゆる体験に、その価値や意志を徹底させ、それが一貫したメッセージとして伝わることで、他の企業では代替できないと顧客が思うブランド価値が生まれる。さらに、デザインは、イノベーションを実現する力になる。なぜか。デザインは、人々が気づかないニーズを掘り起こし、事業にしていく営みでもあるからだ。供給側の思い込みを排除し、対象に影響を与えないように観察する。そうして気づいた潜在的なニーズを、企業の価値と意志に照らし合わせる。誰のために何をしたいのかという原点に立ち返ることで、既存の事業に縛られずに、事業化を構想できる。
このようなデザインを活用した経営手法を「デザイン経営」と呼び、それを推進することが研究会からの提言である。
これは、リターンの大きいデザインへの投資を各企業に勧めると同時に、企業内外のアーティストやデザイナーが、経営の根幹に触れる意思決定に関わるような「デザイン経営」を推奨するものである。
さまざまな「デザイン経営」
それではデザイン経営の推進とは、具体的に何をすればよいのか。
ソフトウェアの開発工程を工夫することをもってデザイン経営に取り組んでいるとする企業もあれば、顧客の体験価値を高めるようなサービスの設計を行うことでデザイン経営に取り組んでいるとする企業、あるいは自社の企業理念やロゴを定めることをもってデザイン経営に取り組んでいるとする企業もあるなど、さまざまな企業があるのが現状である。
このように「デザイン経営」が企業によってバラバラに捉えられ、各社各様の「デザイン経営」があるのは、そもそも「デザイン」の捉え方が千差万別であるからだ。本書の狙いは、こうした百家争鳴ともいえる状況を整理すべく、まずデザインの定義から始めて、デザイン経営の具体像を提示することであり、それと同時に、自社にふさわしいデザインプロジェクトを各社が実践することを射程に含めている。
デザインの3つの意味
一言にデザインといっても、以下の3種類がある。
⒜ビジネス上の問題解決
⒝最終製品の“かたち”の決定
⒞工学的設計
これら3種類が、デザインする製品・サービスの種類や、社会、そして企業の置かれた状況によってさまざまな意味で用いられ、そのためデザイン経営のタイプも3種類に分かれるのである。以下にその例を1つずつ述べよう。
⒜ビジネス上の問題解決としてデザインを捉える。
これは、アメリカのデザインコンサルティング会社であるIDEO(アイディオ)が提唱する「デザイン思考」である。ユーザーへの共感から始まり、問題定義、そしてアイディアの創造とプロトタイプの作成&テストへと進んでいく一連のプロセスを、デザインとして示すものである。事例としては、アップル・コンピュータのマウスのデザインや、使いやすいスマホのユーザーインターフェース(UI)デザインが含まれよう。
⒝最終製品の“かたち”を決定する。
これは、コンセプトに対応した美しいかたちを与え、芸術作品のような工業製品を作るという意味である。いわゆるインダストリアルデザインがこれに当たる。具体的には、美しい流線形を備えたフェラーリのスポーツカーのボディが挙げられよう。この場合、ユーザーに対する市場調査は重視されない。というのも、美的に成熟していない公衆の好みに追随しても、芸術作品のような工業製品は作れないからである。インダストリアルデザインには、「芸術作品のような工業製品を普段から用いる暮らし」を実現するという理想がある。この⒝は、その理念を受け継いでいるのである。
⒞工学的設計としてデザインを捉える。
エンジンの性能設計や建築物の構造計算などがその具体例である。⒝のインダストリアルデザインが、美的観点からそれ以上付け加えたり削除したりすることのできないという意味で「完成した美しいかたち」を備えた製品を実現するのに対し、この工学的設計で念頭に置かれているのは、あらかじめ設計した通りの性能が保証され、計算通りの強度を発揮できるかという点で、⒝とは対照的である。
以上の整理から、デザインプロジェクトの性格は、⒜ビジネス上の問題解決、⒝最終製品の“かたち”の決定、⒞工学的設計、という3つの要素の組み合わせによって示すことができよう。3つの要素すべてをバランスよく備えたプロジェクトもあれば、1つの要素が突出しているプロジェクトもあるだろう。
デザイン経営では、こういったデザインプロジェクトが企業活動の中心となる。ここでは、最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)と最高デザイン責任者(CDO: Chief Design Officer)との頻繁な対話を通じて、同時進行する幾つものデザインプロジェクトが円滑に進むような配慮がなされ、また試作品の出来栄えや、次のプロジェクトのための将来ビジョン等について意見交換が行われる。言ってみるならば、CEOとCDOとの対話で、会社の大きな意思決定が行われる。
本書では、国内外の豊富な事例を通じてさまざまなタイプのデザインプロジェクトを取り上げている。優れたかたちを備えた工業製品が得意なイタリアを扱った第2章では、キッチンのバルクッチーネ、アルマーニ、フェラーリの事例を取り上げ、“デザイン思考”発祥の地であるアメリカについての第3章では、テスラ、IBM、アップルの事例を取り上げた。デザインを工学的設計と同一視する傾向のある中国に関する第4章では、ハイアール、DJI、奇瑞・吉利・長城といった自動車会社を扱い、トップダウンでデザイン経営を導入する韓国を扱う第5章では、サムスン電子、LGエレクロトニクス、現代自動車を取り上げた。そして第6章の日本では、ホンダ、バルミューダ、ファミリアの事例を挙げ、第7章のエコロジーを意識する北欧では、エレクトロラックス、イケア、ボルボを取り上げた。
本書を手に取った方が、「デザイン経営」の具体的なイメージを掴み、日々の活動に活かしていただければ、著者として幸甚である。
(はじめに、著者略歴は『デザイン経営』初版刊行時のものです。本文の一部は書籍掲載のものとは異なります)
