- 2025 02/21
- まえがき公開
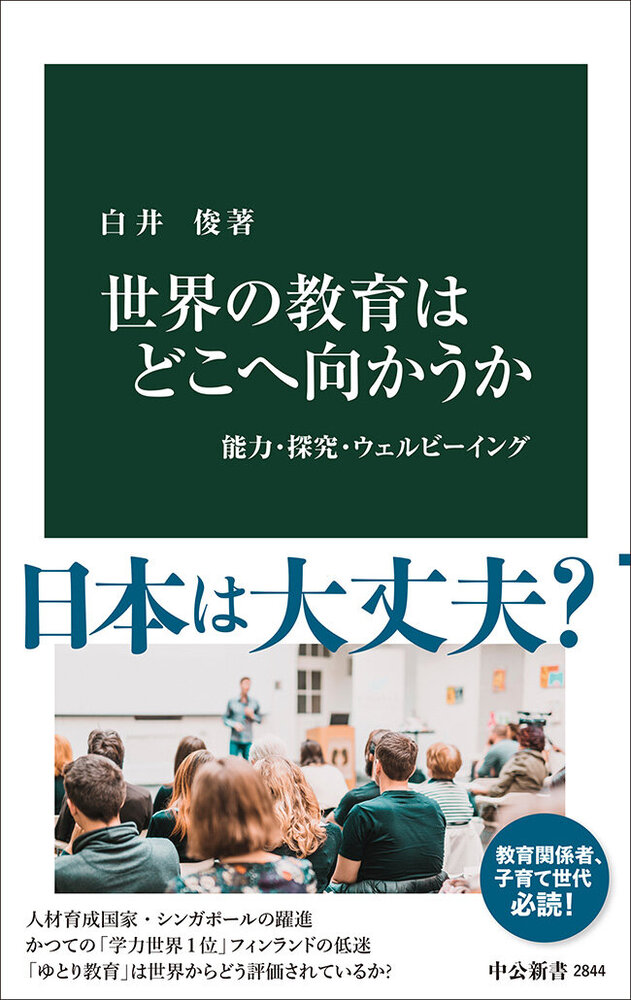
デジタル化やグローバル化などの社会変化を背景に、世界各国が教育改革を加速させている。本書は国連やOECD、ユネスコなどの国際機関、各国での議論を踏まえ、これからの教育を考察する。新たな時代に求められる能力や主体性、ウェルビーイングとは何か。各国が直面する教師不足や過重なカリキュラムへの対応策は。そして、日本に欠けている点とは。一人ひとりの子供が尊重された、あるべき教育、学校の未来を探る。
『世界の教育はどこへ向かうか 能力・探究・ウェルビーイング』の 「はじめに」を公開します。
私たちは、ふだん何気なく「能力」や「探究」、「主体性」といった言葉を使っている。これらはいずれも、日本の教育を考える際に必ずと言ってよいほど登場する言葉だが、実は、多義的で捉え方が難しい。
多義的であるということは、人によって、想定している内容が異なる場合があるということだ。例えば、教師が子供たちの能力や主体性を伸ばすために努力しても、それは社会が期待している能力や主体性とは同じではないかもしれない。あるいは、一生懸命に探究の授業づくりに取り組んでも、それは保護者や子供たちが期待している探究とは異なるものかもしれないのである。
問題は、こうした言葉の解釈だけではない。そもそも、教育が何を目指すべきなのか、学校や教師の役割は何なのだろうか。私たちの多くは、これまでの自分の体験などに基づいて、「大体、こんなものだろう」と考えているかもしれない。しかし、こうした認識もまた、人によって違い得る。
本書では、OECD(経済協力開発機構)やユネスコ(国際連合教育科学文化機関)などの国際機関、シンガポールやフィンランドなどの諸外国における議論や教育事情について随所で触れている。その目的は、世界の教育がどこへ向かっているかを参考にすることで、日本の教育を捉え直すことにある。例えば上述の能力や探究、主体性といった概念はもちろん、教育の目的や、学校や教師が果たすべき役割といったことも含めて、実は教育の根本とも言うべき重要なことがらが、あまり議論されないままに同床異夢となっていることも多い。そこに、諸外国との比較というレンズを入れて考察することで、私たちの認識の違いを浮き彫りにしようとする試みであり、本書を通じて、日本の教育が目指す方向性についての共通理解が進むことになればと考えている。
本書の序章は、教育面で注目を集めるエストニア、フィンランド、シンガポールの事例を参考にしながら、世界の教育改革がどう変わってきたかを概観することから始める。教育におけるデジタル化の意味を構造的に捉え直すとともに、学力で常に注目されるフィンランド、シンガポールの教育事情に迫る。また、教師を取り巻く事情が、国際的に変化していることについても触れる。
第一章から第五章では、教育に関して主要な五つの論点を挙げ、それぞれについて国際的な視点から検討し、日本における教育の方向性を考える。
第一章のテーマは、「教育は何を目指すべきか」である。教育という仕組みも、産業や医療、福祉など大きな社会システムの一部に過ぎない。その意味では、そもそも世界がどのような方向に動いているのか、という視点から教育について俯瞰的に捉えることが重要になる。その際に参考になるのが、いまや普遍的な理念となりつつある、国際連合(国連)が主導するSDGs(持続可能な開発目標)や、OECDによるウェルビーイングといった考え方である。これらに共通するのが、経済成長中心の世界観から人間重視の世界観に転換する過程で登場した概念ということである。今の学校で必要とされているのは、まさに子供たち一人一人に向き合い、「個人の尊厳」を大切にしていくことなのではないだろうか。
第二章のテーマは、「主体性」である。日本の教育では主体性が大事だということが繰り返し唱えられてきた。しかし、各種の国際比較データを見る限り、日本人の主体性は強いとは言えないし、そもそも、主体性とは何かの共通理解が十分ではないように見える。ここでは、主体性の英語訳が何かということを考えながら、特にOECDが提案する「エージェンシー(自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する力)」という概念と比較して考えることで、日本の「主体性」が目指すべき方向性を考える。
第三章では、子供たちに求められる「能力」について考える。伝統的な認知能力に加えて、近年では、リーダーシップや粘り強さ(グリット)などの「非認知能力」が重要だとされている。ただ、こうした能力の発揮においては、場面や文脈が非常に重要になってくる。例えば、リーダーシップは大切だが、他にリーダーがいるのにもかかわらず、それを押しのけてリーダーシップを発揮しようとすることは、むしろ状況を判断する力や他者を尊重する態度の欠如とも言える。「能力」の育成を考える際に、こうした側面は十分に考慮されているのだろうか。これまでの日本の議論に欠けている視点を、「コンピテンシー(能力)」に関する議論を手がかりに考える。
第四章では、「探究」を取り上げる。近年日本では、大学入試で探究型試験が導入されたり、高等学校で探究科が設置されたりするなど、探究が注目されている。しかし、そもそも探究が何かということについて、共通理解はあるのだろうか。実は、国際的な議論では、探究はそれほど注目されている概念とは言えないのだが、なぜ、日本とのギャップが生じているのだろうか。世界に先駆けて導入が決まった「総合的な学習の時間」の歴史を振り返りつつ、諸外国における事例とも比較しながら、本来の探究がどうあるべきかに迫る。
第五章で取り上げる「何をどこまで学ぶべきか」という問題は、探究を進めていくうえでも避けては通れない課題である。現状の学校には、時間的な余裕がない。学校教育には、英語、プログラミング、環境教育、防災教育、金融教育、国際理解教育など、実に多くの要素が求められている。もちろん、どれも大切なことではあるが、授業時間が有限な中で、すべての要素を扱うことはできないし、無理に詰め込んでも意味があるとは限らない。実際、OECDが国際的な学力調査であるPISA(生徒の学習到達度調査)で金融リテラシーを測定したところ、カリキュラム上で金融教育を扱っていることとスコアの間に相関関係は見られず、むしろ、数学をしっかり理解している方が好スコアにつながっていると指摘されている。ここから示唆されるのは、様々な知識を表面的に身につけることよりも、本質的な思考力を磨くことの方が重要であるということだ。各国が直面するカリキュラム・オーバーロード(教育課程の過積載)に陥らないためにどうすべきか、この問題への対応について検討する。
終章では、以上の議論を踏まえつつ、「ニュー・ノーマル」の教育像が示す今後の方向性に触れるとともに、未来の学校がどのような形になっていくか、OECDやユネスコが示しているレポートを踏まえながら考察する。
日本も含めて、どの国の教育にも優れた部分もあれば、課題もある。重要なことは、客観的な事実やデータに基づいてそれぞれの教育を捉え直し、その強みは生かしつつ、課題があれば修正していくという作業を、丁寧に続けていくことだろう。
本書が、現場で奮闘されている教職員、生徒、保護者や地域の方々をはじめとして、教育に携わる多くの方々の後押しとなり、一人でも多くの子供たちが「充実した学校生活だった」「この学校に行ってよかった」「この先生に出会えてよかった」などと学校生活を振り返ることができるようになれば、これに勝る喜びはない。
*本書は、筆者が所属する組織の見解を示すものではありません。
(まえがき、著者略歴は『世界の教育はどこへ向かうか』初版刊行時のものです)
