- 2025 02/21
- まえがき公開
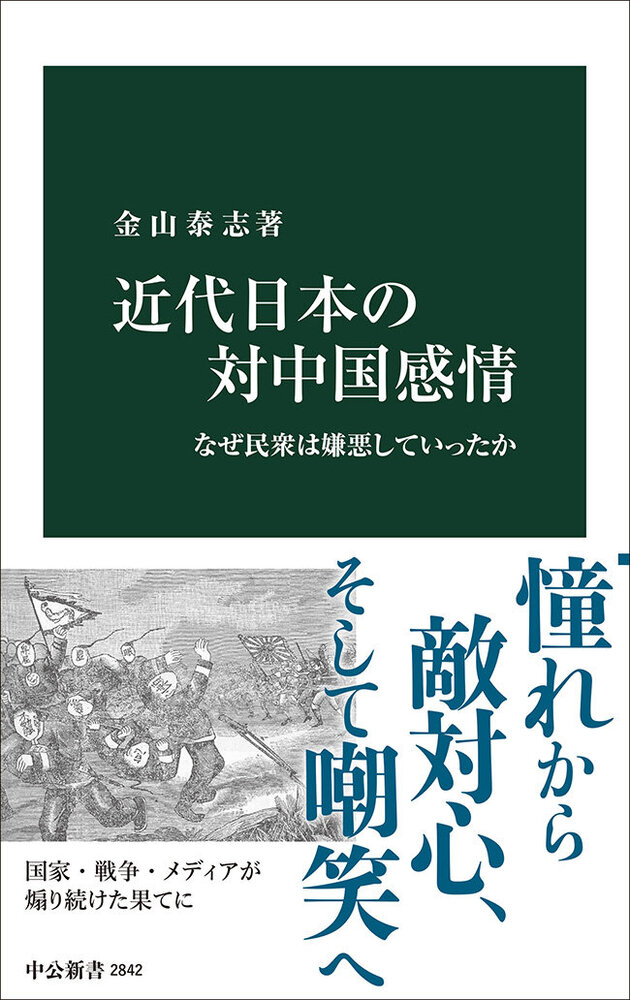
明治維新後、欧米をモデルに近代化した日本。他方で中国はその停滞から一転し蔑視の対象となった。日清・日露戦争、満洲事変、日中戦争と経るなか、それは敵愾心から侮蔑、嘲笑へと変わっていく。本書は、明治から昭和戦前まで民衆の対中感情を追う。世論調査がない時代、民衆が愛読した少年雑誌に着目。赤裸々な図版から、古代中国への変わらぬ思慕とは対照的に、同時代中国への露骨な差別意識、感情を描く。図版百点収載。 『近代日本の対中国感情 なぜ民衆は嫌悪していったか』の 「はじめに」を公開します。
日本近現代史研究の核心
「あの悲惨な戦争を二度と繰り返してはならない」。アジア・太平洋戦争の日本にとっての終戦月である8月、そのような趣旨のテレビ番組が連日放送される。戦争の記憶の継承は大事である。同時に、どうしてあのような戦争の惨禍が起こったのか、その要因を問い直し続けることが必要であり、それは日本近現代史研究が担う大きな役割でもある。
近代日本でなぜ戦争が起こったのか。その要因は多岐にわたるが、一つに戦前の日本社会で共有されていた支配的な民衆感情の存在があげられる。当時、日本の戦争は、多くの日本人が賛同していたものであり、その認識を支えていたのが、日本社会で漠然と共有されていた民衆の対外感情だった。 たとえば、1937(昭和12)年7月に始まる日中戦争であれば、日本民衆の中国へのネガティブな感情が、41年12月に始まったアジア・太平洋戦争であれば、日本民衆のアメリカへのネガティブな感情が、日本の戦争への歩みを支持していたといえる。戦前日本の対外感情を問い直すことは、戦後80年を迎えようとする今日、将来の対外関係を考えるためにも重要な課題となる。
なぜ中国か
日本の対外感情といった場合、眼差しの対象として、アメリカ、イギリス、朝鮮、インドなど、さまざまに考えられるが、本書は「中国」に着目する。
周知の通り、近代日本の軌跡は、日清戦争・北清事変・対華二十一ヵ条の要求・満洲事変・日中戦争などに象徴されるように、中国との対立の歴史でもあった。日本の近現代を通して、中国は「大いなる他者」「忘れ得ぬ他者」であり、中国の存在を抜きにして、日本の過去も将来も語ることができない。
日中関係史を紐解こうとする場合、焦点となるのが日本人の中国観だ。日本人が中国・中国人のことをどのように見ていたのか。「中国観」「中国認識」「中国像」などとさまざまな用語で表現される中国に対する日本人の眼差しは、日本の対中政策及び対中行動を考えるうえで重要な要因となる。これまで多くの日本人及び中国人研究者が、「日本の中国観研究」を行ってきた。ただし、その蓄積の多くは知識人たちの言説分析であり、一般民衆の対中国感情(以下、対中感情と略す)に着目した研究は行われてこなかった。
本書では、この中国に対する日本人の一般民衆の眼差しを、「好き・嫌い」「良い・悪い」といった感情レベルで見ていきたい。
感情への着目、「少年雑誌」という史料
近年、注目される感情心理学は、人間のあらゆる認識や行動には感情が伴っていると指摘する。いま、手許にあるスマホで「中国」と検索すれば、中国に対する「低劣」と言わざるを得ない過激な言説(特にSNS)がいくらでも目に飛び込んで来る。ただ、これを「低劣」だとあっさり切り捨ててしまってよいのだろうか。近代日本の戦争に至る足跡を考えてみても、感情剥き出しの表現が社会に蔓延し時代を動かしていた。本書を通読することでその様相を追体験できるようにしていきたい。
さらに、現在の中国観を歴史的に相対化する意味でも、近代(戦前)日本の中国観は感情レベルに着目する必要がある。ちなみに、2023年の日中共同世論調査では、中国に対して「良くない」印象を抱いている日本人の割合は「92.2%」にものぼる。SNSなどのインターネットメディアでの感情的な言説も含めれば、現在の中国観の多くが感情レベルで語られている状況にある。
感情レベルの中国観を明らかにするうえで、本書では近代日本で刊行された少年雑誌のビジュアル表現(挿絵・漫画・写真)に注目する。少年雑誌は、歴史学の領域であまり注目されてこなかった史料であり、民衆感情を捉えるうえで有用な史料であることはあまり知られていない。子ども向けの娯楽メディアである少年雑誌には、わかりやすい善悪二元論でエンターテイメント化されたものが溢れかえっている。特に中国との敵対時には、きわめて先鋭的な形で敵愾心や蔑視感情が誌面に表出し、中国・中国人に対する感情的な表現を読み取ることができる。
一方、戦前の少年雑誌は、小説や漫画などの娯楽的要素だけでなく教育的要素も併せ持ち、学校教育の補助的役割も果たす修養書としての側面も担っていた。当時の子どもたちにとって中国は遠い世界であり、教科書などを通じてしか知らない世界だった。編者・記者である大人たちは、少年雑誌を準教科書的に使って、子どもたちに中国・中国人とはどのような国であり人柄なのかを教えようとしたわけだが、その際、ビジュアル表現が添えられた娯楽的な読物(物語)や漫画、写真などを通じて、感情的かつ印象的に中国・中国人を紹介することになる。
また、少年雑誌の挿絵・写真の多くは、誌面の文章記事に添えられ、漫画には台詞である文章が付されている。少年雑誌を史料とすることで、中国・中国人がどのように表現されているのかを、ビジュアル史料と文字史料から複合的に見ていくことができる。
本書では、明治・大正・昭和戦前期に最も有力だった少年雑誌を時代に合わせて選定する。21世紀現在、最も発行部数の多い少年雑誌は『週刊少年ジャンプ』だが、それぞれの時代に現在の『少年ジャンプ』のような有力雑誌が存在していた。その詳細は各章で紹介する。
本書の特徴
以上のように、本書は次の3点を特徴とする。
①従来の中国観研究が対象にしてきた知識人層ではなく民衆の対中感情に着目する。
②知識人層が執筆した記事や書物といった文字史料ではなく、少年雑誌の挿絵や漫画、写真といった非文字史料=ビジュアル表現に着目する。
③明治・大正・昭和戦前期という長期間(19世紀後半~20世紀前半)にわたる一般民衆の対中感情の包括的把握を行う。
先述したように、日本の中国観研究の蓄積は膨大である。歴史学に限らずさまざまな領野から研究が行われているが、その多くは知識人を対象としたものである。また、「日清戦争期」「日中戦争期」といったように時代が限定され、近代日本を見通した包括的な研究は少ない。論文ではなく、本という形で中国観をまとめるのであれば、この点は是非とも押さえておきたい点である。もちろん、少年雑誌だけで一般民衆の感情をすべて捉えることはできない。ただ世論調査がないこの時代、民衆感情を捉えるうえで、その大きな一助になると考える。
一方、本書で取り上げるビジュアル史料は、現代では中国人への差別や偏見に満ちたものが多い。近代日本では、こうした差別と偏見に満ちた表現がメディアに溢れ、学齢期の少年向きの雑誌にさえ掲載されてきた。本書は、これらを歴史史料として提示し、多くの民衆がこれらを目にし、強く影響を受けたことを伝えたいのだが、読まれ方や史料の切り取られ方によっては、差別や偏見が助長される危険性をはらむセンシティブな内容を多分に含んでいる。
そのようなリスクを踏まえたうえで、本書が専門書ではなく、より多くの人が手に取る新書という形で出版されることに何よりの価値があると考えている。たとえば、昨今のネットの言論空間(特にSNSなど)を見ていると、「日本には差別なんてなかった」といった記述を目にすることがある。そういった歪んだ歴史認識の反証として、実証的かつ近代日本を包括的に見通したものが、新書という形でコンパクトにまとまっていることの意義は大きいはずだ。また、ネットメディアによって感情が煽動される現代日本では、たとえばヘイトスピーチの問題などを考える際、過去のメディア(少年雑誌)が侮蔑感情を煽っていた様相を見ていくことで、物事を相対的に捉える視点を養うことにもなるだろう。
差別や偏見といった排他的な感情は、国や社会が危機に直面した際や、将来への不安が増幅した状況で顕著に表れる。そのような危機的状況に陥ってしまう前に、過去の排他的な感情をいま、見つめ直しておく必要があるのではないだろうか。
以下、本書では少年雑誌のビジュアル史料を中心に扱っていくが、歴史学では「史料と史料の突き合わせ」も大事である。他メディアのビジュアル史料も比較参考として適宜紹介したい。少年雑誌のみを史料として扱うと、「それは少年雑誌に限った話ではないか」との批判を免れ得ないためである。では、多くのビジュアル史料とともに、近代日本の対中感情の様相を見ていこう。
(まえがき、著者略歴は『近代日本の対中国感情』初版刊行時のものです)
