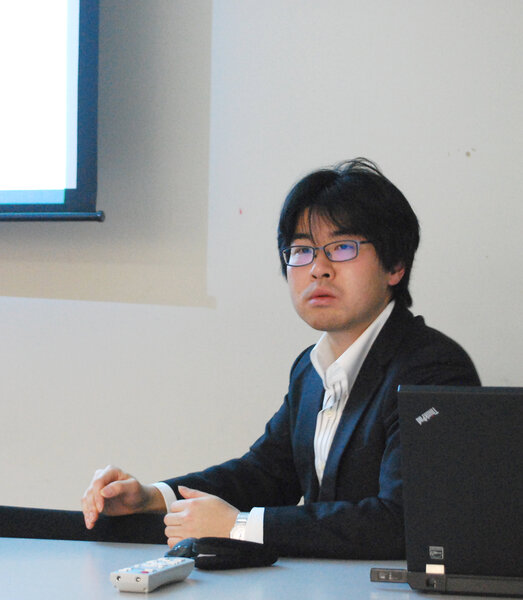- 2025 01/07
- 著者に聞く

高校世界史で習う「レコンキスタ」。言葉はなんとなく覚えているけれども、その中身はあやふや……。そんなレコンキスタに正面切って取り組んだ新書が『レコンキスタ―「スペイン」を生んだ中世800年の戦争と平和』です。著者の黒田祐我さんにお話をお聞きしました。
――最初にお尋ねしますが、「レコンキスタ」とはどういうものですか。手元の古い『世界史用語集』(山川出版社、1985)には「国土回復運動」として
「キリスト教徒によるイベリア半島からのイスラム勢力駆逐運動」
「キリスト教徒によるイベリア半島からのイスラム勢力の駆逐運動。はじめは北部山岳地帯を拠点とし、10世紀頃から各地にキリスト教の小王国・公国が自立し、対イスラム戦を通じて、次第に統合の方向をたどる。軍事的性格と、ローマ=カトリックとの結合が特色。」
とあります。これは現在の捉え方はだいぶ違うように思うのですが……。
黒田:「レコンキスタとは何か?」……これを一言で説明できるのであれば、誰も苦労しません(笑)。本書を読んでいただく必要もなくなってしまいます(笑)。
本書のタイトルでは、800年間の長きにわたる中世の歴史を「レコンキスタ」という一言で表現しているわけですが、実際は、各地域と時代に生きた人々(為政者から一般庶民まで)それぞれの「レコンキスタ」(理念を作る、略奪に出かける、戦う、辺境に入植するなどなど)があって、その総体、とでも言えばいいでしょうか。
とりあえず言えるのは、建前として、あるいは長期的な視野で振り返れば、おっしゃる用語集の説明にはなるのでしょうが、実際には、はるかに複雑なプロセスを経ています。
そのプロセスの複雑さ自体を、可能な限り丹念に伝えようと心掛けました。
その用語集の説明でも、あるいはこれは「レコンキスタ」に限ったことではないと思いますが、世界地図などでおなじみのように、ある政治単位はひとつの色で、別の政治単位は別の色で、それぞれ混じりあうことがない状態で描かれています。「キリスト教徒」の勢力が一方にあって、他方で「イスラム勢力」がそれと対峙して、前者の色一色に染めあげられていくプロセスだとイメージされているわけです。
でも実際には、そうではありえませんでした。
「キリスト教の小王国・公国」は一致団結せずに仲違いばかり繰り返し、また領域拡大の過程で、ムスリム臣民も多数抱えるようになりました。
「イスラム勢力」は、そもそも圧倒的多数がキリスト教徒の臣民である社会から、数百年かけてムスリムが多数派になる社会を作っていったにすぎないのです。
そもそも「イスラム勢力」とか「イスラム戦」という表現の仕方自体が問題だと思います。「イスラム」は宗教であり社会全体を指すと無批判に受け入れてしまっています。それに代わる用語がまだ定着してないのが問題ではありますけど。ただの愚痴です。
――本書を読んで、一筋縄ではいかないレコンキスタのリアルに触れることができました。なぜこんなに時間がかかったのかなど、これまで疑問に思っていたことに触れられていたことも興味深かったのですが、ナスル朝が真綿で首を絞められるように逼塞していくさまとか、肉屋をめぐるトラブルのような、ムスリムとキリスト教徒とユダヤ教徒の共存といがみ合いとか、大砲出現前の攻城戦とか、さまざまな未知のことが巨細にわたって描かれ、当時の実情を知ることができました。
これらの研究にあたってのご苦労、あるいは本書執筆にあたってのご苦労や工夫がありましたらお教えください。
黒田:本書で取り扱った時代(=中世)には、そもそも「スペイン」という単一の政治単位がまだ存在していません。ですから本当は「スペイン史」というくくりにしてはいけないのです(笑)。
研究者は一人ですべてを研究し尽くせるわけでもなく、それぞれの専門の地域と時代を持っています。中世の「スペイン史」の場合、大体次のように細分化された専門領域になります。
時代では、8世紀から10世紀の専門、11世紀から13世紀の専門、14世紀から15世紀の専門。
地域では、カスティーリャ王国やアラゴン連合王国といった政治単位、そしてそれぞれの王国内の地域で、さらに細分化されています。アンダルス史はアンダルス史で、やはり時代に分かれて研究がなされています。
さらに中世文学や中世考古学、はたまた古銭学の知見も今は非常に重要になってきています。
……つまりは、さまざまな分野の歴史研究で培われた成果の全体を掴んで、自分なりにそれらを咀嚼して消化した後、あらためて自分で全体を再構築する必要がありました。
私は本来、11世紀から15世紀の中世カスティーリャ史(特に南部アンダルシーア地方)が専門なのですが、地中海史や、アンダルスやイスラーム世界との関係史にも非常に関心をもっていたので、いろいろな地域と時代を若いころから「つまみ食い」してきた経験がうまくいかせたと思っています。
*アンダルス:イベリア半島でのイスラーム世界領域を指す。
――なぜスペイン史、特にほとんど日本では研究者のいないレコンキスタを研究しようと思ったのですか。
黒田: これも話し出すと長くなります(笑)。
とりあえず時系列で簡単にお話しします。もともと古代ローマ史を専攻しようと思いながら大学に入学しましたが、学部生時代にアミン・マアルーフ著『アラブが見た十字軍』を読んで逆の視点からの十字軍の歴史の面白さに心打たれ、中世ヨーロッパとイスラーム世界との交流の歴史を専門にしようと心に決めました。
大学院に入って、さあ研究テーマを絞ろうと考えたとき、聖地十字軍国家あるいは中世シチリア島をフィールドにするか? あるいは「十二世紀ルネサンス」などを扱う科学史にするか? で悩みました。でもどちらの分野も、勉強不足もあって、どうにも取り組んでみたい具体的な研究テーマが見つかりませんでした。
当時の指導教授に相談したら、あっさりと「じゃあスペイン史やれば? キリスト教徒とムスリムが一番長く共存した場所だし。史料もあるだろうし。そして日本では研究者もいないし。すぐ第一人者になれるよ」と言われて、一念発起しました。そういう不純な動機です(笑)。
スペイン語自体を習っていなかったのに、よくいきなり飛び込んだものだと、当時の若い自分をほめてあげたいです。スペイン語をとりあえず自学自習して、辞書を引きながら概説書を読んでみると、興味深いテーマが複数見つかりました。なお、実際には日本では専門家の層も厚くなり始めていたので、そんな第一人者には簡単になれるものではないことがすぐわかりました。
――今後、なにを研究、あるいは執筆しようとお考えですか。
黒田:個人研究としては、これまで研究に携わってきたスペイン南部アンダルシーアで、中世のナスル朝と鬩ぎあったカスティーリャ王国の最前線地帯の人々の生き様をもっと調べたいと思っています。
ただ、あまり専門的な話をしても日本では誰も聞いてくれませんし、需要もない(笑)。その成果は専門論文として出すとして、じゃあ、その成果を含めて、どう社会に還元したらよいか? とりあえず二方向で考えています。
ひとつは、カスティーリャ王国やアラゴン連合王国が活動域とした「西地中海」という舞台の歴史を全体として提示してみたいと思っています。時計回りに、イベリア半島から南フランス、イタリア半島からマグリブ(北アフリカ)。西地中海に浮かぶ島々。十字軍の舞台となり、中東と連結している「東地中海」に比べると、西のそれはあまり注目されてきませんでした。しかしイメージされてきた以上に、西もヒトの交流が盛んであったのです。
もうひとつは、歴史認識の問題を扱ってみたいと思っています。これは専門としている中世そのものの分析ではありません。本書で扱ったようなレコンキスタの時代が、後代にどのようにイメージされ、教えられ、そして語られていくのか? を提示してみたいのです。
本書でも触れましたが、国政でも一定の影響力を持つようになっているスペインの極右政党VOXは、中世レコンキスタを模範として、ムスリム移民排斥を訴えます。移民排斥という主張の是非はさておき、中世の歴史を安易なかたちで政治利用することは、近代以降、実は右も左も繰り返し行ってきたことです。
――本書に関連して、スペインに行ったら訪れるべきお薦めの場所あるいは体験すべきイベントなどがあったらお教えください。本書にはコルドバのメスキータとか、廃墟になった王宮とかは詳しく出て来ますが、アルハンブラ宮殿は最初に出てくるだけです。著者としてはあまりアルハンブラ宮殿はお薦めではないのでしょうか?
黒田:アルハンブラ宮殿が嫌いなわけではないです(笑)。初めて行ったときは心の底から感動しました。ただ、私が取りあげなくても世界的に既に有名です(現在はオーバーツーリズム気味です)し、当時のアンダルスやキリスト教諸国を示す遺構はそれだけではない、という意見を込めて、敢えて(涙を呑んで)取りあげなかっただけです。
ヨーロッパの他の場所とは違った建築文化という点に限定するならば、アンダルス社会が根付いた場所(本書でも出てくる地図をご参照ください)には、さまざまなかたちで当時の遺構が多く残されています。
中世のはじめ、現在のスペインの首都マドリードはただの砦でしたが、王宮とアルムデナ大聖堂のすぐ南には、後ウマイヤ朝時代の城壁が残っています。南に行けば行くほど当時の遺構は増えていきますが、本書が対象としている時代の建築そのものがそのままで残っていることはほぼありません。修繕・修復・改築が繰り返されています。でも、時代を経た「リフォーム」自体の意味も考えながら、中世の名残を見つけ出していただければと思います。
アンダルス社会が直接根を張らなかった北部であっても、「ムデハル建築」と呼ばれる建築をいろいろなところで見ることができます。ムデハルとはキリスト教諸国内に残留したムスリムを指します。このムデハル職工たちがもともと会得していたとされる技法や意匠を導入して建てられた教会が各地で見られます。
ちょっと質問の主旨からはずれるかもしれないのですが、本書で扱った中世では、古代ローマ時代の石材(石柱や城壁、はたまた墓石まで)がいろいろなところに再利用されています。地域と時代を超えて、いたるところで古代や中世の影響が垣間見えるということを、発見・確認しながら旅をしていただけると、前近代の歴史家のひとりとして嬉しいです。スペイン名物のパエリアやフラメンコは、長い歴史の結果であって、原因ではありません。
――最後に読者、特に若い人たちに、これだけは言っておきたいということがありましたら、なんでもお教えください。
黒田:書きあげてみた後になって私も気づいたのですが、本書は「割り切れなさ」がキーワードのひとつとなっています。いつの世も人は、「わかりやすさ」をせっかちに求めます。「どちらが善で、どちらが悪なのか?」「どの宗教が正しいのか?」「自国の境界はどこなのか?」などなど。でも世の中そんなに白黒つけられないし、簡単に割り切れません。それを無理に割り切ろうとするところに、大きな悲劇が生じるのです。民族であれ国家であれ宗教であれ、政治思想であれ、近現代の歴史は「割り切った」結果の悲劇で満ち溢れています。ではどうすればいいのか? 私はもっと「割り切らなかった」前近代の歴史に耳を傾けてみたほうがよいと思っています。
それと関連するかもしれませんが、そして今に始まったことではありませんが、もっと歴史に関心を持ってほしいと思います。学校で習う世界史や日本史は、どうしても事項の羅列になってしまい、暗記科目気味にならざるを得ないので、嫌いだ・興味が持てないという意見をよく聞きます。
でも、ちょっと考えてみてください。その歴史の事項の積み重ねのなかで、我々を取り巻く言葉も、概念も、食べ物も、衣服やファッションも、ありとあらゆるものが形作られてきたのです。そして我々もそのうち歴史の一部になります。こう思えば、少しは歴史が身近なものに感じられるのではないでしょうか。