- 2024 10/23
- まえがき公開
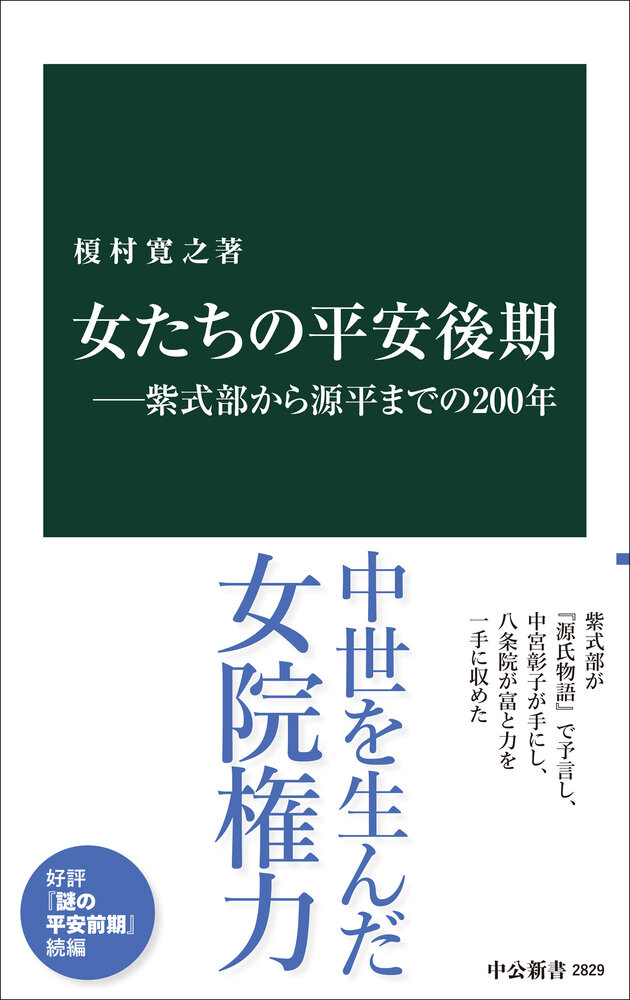
平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院政をしき、それを支える中級貴族や源氏・平家などの軍事貴族、乳母が権力を持つようになる。そのなかで巨大な権力を得た女院たちが登場、莫大な財産は源平合戦のきっかけを作り、武士の世へと移って行く。紫式部が『源氏物語』で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言われた平安後期の実像がいま明かされる。 □ ■ □ ■ □ ■ □ はじめに
『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(榎村寛之著)の「はじめに」を公開します。
日本史といえば、武士政権が初めてできた源平合戦から鎌倉時代のはじまりの時期と、群雄割拠する戦国時代、幕末を中心とした江戸時代などの人気が高い一方で、たとえば本書で取り上げる平安時代は、人気のあるなし以前に400年も続いたことさえ知る人は少ないでしょう。
これからご紹介する平安時代後期は『源氏物語』の書かれた時代以降から源平合戦までの約200年のことです。
中世の始まりと武士の時代のさきがけというイメージで、鎌倉時代前史と理解されることが多い時代ですが、じつは武士も貴族も民衆も入り混じって、それぞれに歴史がありじつに面白いことを知っていただきたいのです。
藤原道長が活躍した平安時代中期は、支配層が「オール藤原」といえる摂関政治の全盛期でした。これが、平安時代後半になると、藤原氏だけでなく、源氏・平氏、そして皇族などいろいろな人たちが出てきます。というより、平安前期や紫式部の時代には忘れられていた傍流の藤原氏や、貴族にとどまれず武士になってしまった源氏・平氏がリベンジをかけてきます。そして彼らを引き上げたのが、「院」(上皇)と呼ばれる皇族ですが、この存在がまたわかりにくく、しかも面白いのです。古代国家のトップだった天皇を卒業した彼らは、有能で個性豊かな人々を、生まれ育ちさえ超えて近臣に引き上げました。なかでも「治天の君」と呼ばれた上皇たちは古代国家を潰しにかかるように暴れまくるのです。
そうした古代から中世へと激しく動く時代の中で、女性たちはどのように生きていたのでしょうか。平安中期の女性は、すでに本名が公文書や日記にさえあがることの少ない、地味な存在になっていましたが、その一方で新たな形や場所で大きな役割を果たしていました。
紫式部や清少納言の後継者にあたる、サロンに仕える貴族女性たち、またそのサロンの主人の、定子皇后や彰子中宮の後継者にあたる妃たち、そして斎王のような皇族女性たちのことは、これまで歴史的にはほとんど取り上げられることはありませんでした。なかでも「女院」つまり女性の上皇と呼ばれた人たちは、院とともにこの時代の重要なワイルドカード(トランプで、いろいろなカードの代行ができる特殊な切り札)になっていましたが、その実態はほとんど明らかになっていないのです。
あまり知られていないこの時代の女性たちの足跡から、平安時代後期や社会を考え、戦国時代や幕末のように議論や話題にしていただけたらと楽しみにしております。本当に面白いですから。
(まえがき、著者略歴は『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』初版刊行時のものです)
