- 2024 10/01
- まえがき公開
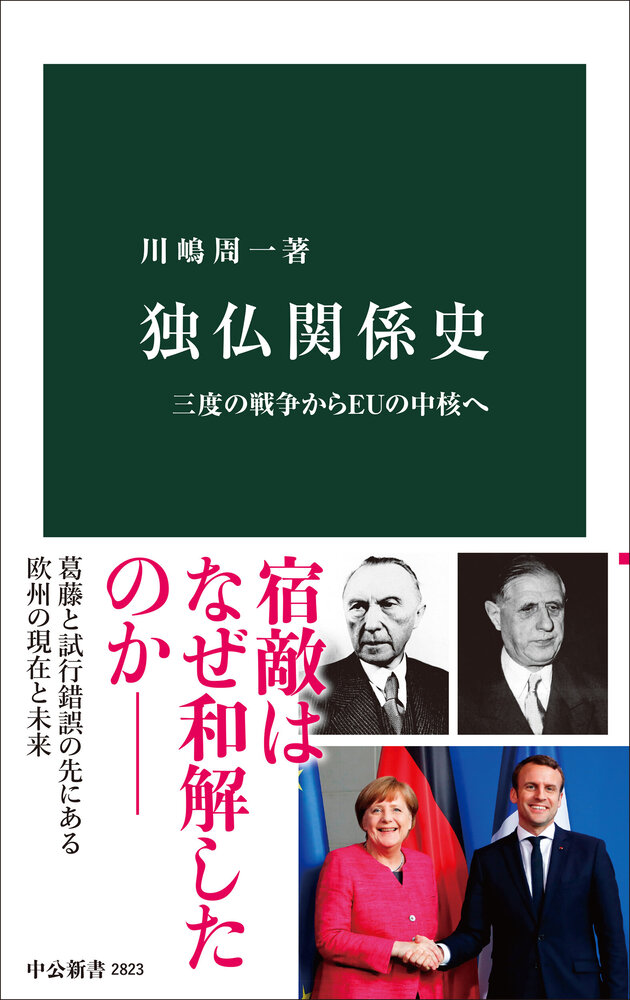
ドイツとフランスは、19世紀から20世紀にかけての70年間に3度も戦争を繰り広げ、不信と憎悪を募らせた。しかし、その後の両国は徐々に和解への道を歩み始め、EUの基盤を築いていく。なぜ、協調は可能だったのか? 本書は、ド・ゴール、アデナウアー、ミッテラン、コール、メルケル、マクロンなどの政治指導者の政策、民間外交の動きなどを一望。因縁深い両国の関係を通し、欧州の歴史をたどり、展望を示す。 『独仏関係史 三度の戦争からEUの中核へ』(川嶋周一著)の「まえがき」を公開します。
まえがき――独仏関係という視角
33%。
この数字は、1914年に勃発した第1次世界大戦で、その年に20歳を迎えたフランス人男性が、大戦中に命を落とした割合である(Héran 2014)。1894年に生まれたフランス人男性のおよそ3人に1人は、戦争に行った後戻って来られなかった。戦争が続いた4年間にドイツとフランスの死傷者の総数は、どちらも500万人をはるかに超す。
しかも、この数字には広い意味での戦争被害者、たとえば家や財産を失った人や強姦された女性、栄養失調で命を落とした嬰児などといった人たちの数は含まれない。それらを含めれば気の遠くなるような人的被害を両国は被った。これほどまでの犠牲を出しながら、ドイツとフランスは第1次世界大戦で全面的に戦った。
その第1次世界大戦勃発から90年余りが経とうとしていた2003年1月22日、ドイツのゲアハルト・シュレーダー首相とフランスのジャック・シラク大統領は、パリでの首脳会談後、独仏共同閣議(独仏閣僚理事会)を開催した。パリ近郊のヴェルサイユでは、独仏両下院議員が出席する合同議会まで開かれた。この2003年は、1963年に締結された独仏協力条約(通称エリゼ条約)の締結40周年記念に当たる年だった。エリゼ条約締結以降、両国は外交で密接に連携し合いながらヨーロッパ統合を促進するばかりでなく、2国間の行政的文化教育的な提携もきわめて深いレベルで実施している。
振り返れば独仏両国は、19世紀後半から20世紀の中盤にかけて、普仏(独仏)戦争、第1次世界大戦、第2次世界大戦と、3度も全面的に戦い血を流し合った。しかし第2次世界大戦後は、この敵対的な関係性を劇的に改善することに成功した。19世紀から20世紀中盤にかけて世界を揺るがす戦争はヨーロッパから生まれていたが、第2次世界大戦後に独仏間の友好関係が確立すると、ヨーロッパから戦争は退場したかに見えた。
だが、2022年にウクライナ戦争が勃発し、二つの世界大戦を生んだヨーロッパの国際政治に再び戦争の影が差すようになった。このヨーロッパ国際政治を理解するには、イギリス、フランス、ドイツといったヨーロッパの鍵を握る国家のみならず、中小国が果たす役割や、ヨーロッパ連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)などの地域的枠組みとの関係といった、当地で行われる外交(ヨーロッパ外交)の在り方や、歴史的に形成された構造や力学を考慮に入れる必要がある。その中で、ドイツとフランスとの関係は、他の2国間関係と比べ独特の存在感を発揮している。なぜなら、敵対から協調へと転じる過程で、独仏関係にも独自の力学や構造が生成され、良くも悪くも、ヨーロッパ国際関係の中の一つの不可欠な構成要素となっているからである。では、独仏はどのように関係を発展させ、現在のヨーロッパの国際関係の中で、いかなる役割を果たしているのだろうか。
本書は、19世紀からウクライナ戦争が勃発した2020年代初頭までの、フランスとドイツ(1949年から90年までは西ドイツ)間の関係を、歴史的に概観するものである。
独仏関係の通史を描く本書には、二つの狙いがある。一つは、ヨーロッパの国際関係の歴史に一つの見取り図を示すことである。独仏関係の歴史はヨーロッパ国際政治の歴史の中に埋め込まれており、この二つを切り離しては理解できない。その逆もまた真なりである。
独仏関係が敵対から協調へ向かう筋道を理解するためには、ヨーロッパ全体への視野が必要になるし、ヨーロッパ国際関係全体を視野に収めようとするとき、独仏関係という視角は明瞭なレンズを我々に提供する。そのレンズが大国主義的なものであることは重々承知しているが、敢えて独仏関係からヨーロッパ国際政治を見ることで、ヨーロッパ国際関係の勘所のようなものを摑むきっかけになるのではないだろうか。
第2の狙いは、独仏関係が持つ複雑な力学を理解することである。確かに独仏両国は、世界でもまれな協調関係を作り上げたが、しかしその内側には抜き差しならない緊張が存在し、提携関係の構築には一筋縄ではいかなかった複雑な経緯がある。独仏関係は理想形ではなく、歴史的に形成されたある一つの型に過ぎない。独仏関係の現実と理念の両方を冷静に観察できた時、国際関係とその歴史を見る目は、より奥行きをもって眺められるようになるだろう。
したがって、本書が扱う独仏関係はまず政治外交的な次元を扱う。ただし、政治外交的な関係が、その次元の論理だけで完結しなくなるのが20世紀の特徴でもある。この次元に加え、独仏両国を取り巻く国際環境(ヨーロッパ統合や冷戦)の次元や両国の人的交流もまた重要なトピックである。政治外交(外交政策や大統領、首相などの政治的リーダーの次元)、ヨーロッパ統合や冷戦(独仏関係を基礎づける国際環境の次元)、トランスナショナル(2国間関係に内実を与えるヒトとヒトとの関わりの次元)という三つの次元は、独仏関係を理解する際に不可欠な視点となる。
なお、日本語で独仏関係を扱った書籍や論文の数は多くないが、反面、フランスやドイツには当然多数ある。ではそういった書籍を翻訳すれば事足りるかと言えば、そうはいかない。明らかに前提となる知識も関心も目的も違うからだ。そもそもフランス人にとっての仏独関係と、ドイツ人にとっての独仏関係の重みも、また異なる。
独仏関係という大国の振る舞いを、周りの小国が冷ややかに、時に苦々しく眺める様子も、当事国の視点からは抜け落ちがちである。本書は可能な限りバランスをとって、日本人が独仏関係史を理解することの意味に向き合って執筆したつもりである。あらかじめ断っておくと、独仏両国を等しく扱ってはおらず、ややフランス側から見た記述が多い。詳しくは本論を読んでもらえればと思うが、独仏関係をより必要としているのはフランスで、ドイツにとってフランスとの関係は、ヨーロッパを重ね合わせることで重要となるからである。
不幸にして現在の国際政治には動乱や戦争の暗雲が広がっているようだ。しかしだからこそ、過去に何度も戦争を重ねたドイツとフランスが、どうやってその関係を改善したのか、と同時にその関係性を理想化せずにいかに冷静に認識するかを、いまほど求められている時代はなかろう。歴史を学ぶことは、未来を創る土台となるべきものである。
本書の構成は以下の通りである。序章から第1章までは、ドイツとフランスが国家としての関係を築いた19世紀から、3度の戦争を重ねて憎悪を募らせた時代を扱う。第2章から第5章までは、第2次世界大戦が終結してからベルリンの壁崩壊前夜までの、ドイツが東西に分断され、世界も冷戦に覆われていた時代を論じる。なおこの時代に関しては、本書は専ら西ドイツ(以下、西独)を扱う、これは、フランスにとって戦前のドイツを引き継ぎ、パートナーシップを築いたのは西独だからである。もちろんフランスと東ドイツ間にも多くの語るべきことがあるが、論旨から外れるため記述していない。そして第6章から第7章では、冷戦終焉後、ドイツが再統一してから現在までの独仏関係を描く。終章では、両国のこれまでの関係を振り返りつつ、2022年に勃発したウクライナ戦争がもたらす影響と今後の姿について考察を行う。
本書の用語法にも簡単に触れておきたい。
「ヨーロッパ」と「欧州」の使い分けについては、基本的に「ヨーロッパ」を用い、「欧州」は固有名詞(欧州通貨単位など)で用いる。序章で用いられる「ヨーロッパ世界」とは、前近代のギリシャ・ローマ世界の遺産を引き継ぎながら中世以降に成立するキリスト教の西ヨーロッパ世界を指す。それゆえ、近代以降の記述では単に「ヨーロッパ」を用いる。
「国際政治」と「国際関係」という言葉は、一般的には国際政治が政治外交や安全保障に関する狭義の国家間政治を意味し、国際関係はそれに留まらない経済・文化などを含む、より広義の国家間関係を指す。厳密に区分するのは難しいが、一応の使い分けを試みている。
ヨーロッパ国際政治/ヨーロッパ国際関係は、ヨーロッパという地域内の国際政治/国際関係を指す。本書で用いる「ヨーロッパ」は正確には「西ヨーロッパ」であることが大半だが、冷戦期に東西ヨーロッパが分断されている文脈以外では、厳密に使い分けてはいない。「国際秩序」とは、主として国家によって成り立つ国際関係の秩序の在り方を指す用語である。国際秩序はグローバルなものとして成り立つ一方で、地域的に固有の国際秩序が成立する場合も多い。ヨーロッパ国際秩序とは、そのようなヨーロッパという地域で成り立っている国際秩序を指す。
本書では、ヨーロッパ国際秩序を構成するのは国家だけでなく、ヨーロッパ統合などの地域的枠組みやNATOなどの安全保障機構を含み、特に安全保障上の秩序を指す場合はヨーロッパ安全保障秩序というように限定する場合もある。ヨーロッパ安全保障秩序は、ヨーロッパ国際秩序を構成する基幹的な要素というのが本書の前提としてある。
(まえがき、著者略歴は『独仏関係史』初版刊行時のものです)
