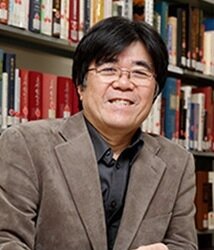- 2023 07/20
- 著者に聞く

男性が親や妻の介護をするのも当たり前の時代となった。それ自体は良いことだろうが、介護心中や虐待といった事件は増加する傾向にあり、加害者の多くは介護する夫や息子たちである。過重負担に耐えかねて介護離職する人も少なくない。「これまでの女性と同じように」介護することでは、問題は解決しない。個人はどう介護に向き合うべきか。また、介護者支援はどうあるべきか。『男が介護する 家族のケアの実態と支援の取り組み』を著した津止正敏さんに話を聞いた。
――今回、執筆依頼を受けてどう感じましたか。
津止:もう5年ほど前になりましたが、2016年10月に早稲田大学が主宰した教職員向けの講座「仕事と介護の両立」の終了後に名刺交換した方が中公新書編集部の並木さん。執筆のご依頼でした。「男性介護者」というニッチな分野が大勢の読者獲得を想定する「新書」に応え得るものかどうか、少し戸惑いながらお話に耳を傾けていました。専門書を別にすれば一般向け介護分野のほとんどがノウハウもの、という思い込みも私にはありました。それでも、私が事務局長を務める「男性介護者と支援者の全国ネットワーク(男性介護ネット)」の10周年が話題になっていたこともあって、ちょうどいい記念の上梓になるのではとの思いもありました。この10年余りの「男性介護ネット」の“いま”を起点に“これまで”を振り返りながら“これから”を少し展望してみようという、私の思いが伝わるものとなったのかどうか、読者のみなさんに聞いてみたいと思います。
――執筆で苦心された点は?
津止:専門書と違って、分かる人に分かってもらうだけではない、多くの人の目に留まり手に届けるための執筆作法にまずは戸惑いました。一文は短く、段落を区切って、見出し・小見出しは単調にならずに、と並木さんの叱咤激励を受けながらの作業でした。また内容的には、良くも悪くも、私がこの10年余りのネットワークの活動で出会った男性介護者とのエピソードが素材となりました。本書で登場頂いた介護者のみなさんには、そのエピソードに可能な限り氏名・年齢・居住地を添えるようにしました。読者のみなさんに介護のある暮らしのリアルが少しでも感じ取られたとすれば、すべてこのエピソードの持つ臨場感によるものだと思います。これらの豊富な具体を通して、介護の課題やこの社会の本質に迫るという、いわば私なりの臨床場面を記録したともいえます。
――それにしても、主たる介護者の3分の1が男性とは驚きました。
津止:みなさん、そうです。そして「そういえば、私の近所にも、知り合いも、会社の同僚も、家族にも」と思い当たる方々の顔が浮かんできて、すぐに納得するように思います。「2019年国民生活基礎調査」(厚労省)によると、同居の主たる介護者のうち、男性は3人に1人を占め、実数ではもう100万人をゆうに超えています。直近の「2017年就業構造基本調査」「2016年社会生活基本調査」(いずれも総務省)では、男性介護者の比率はさらに高まりそれぞれ37.0%、39.7%という実態も明らかになっています。これらの政府調査はその目的や規模、手法の違いもあって単純に比較できるようなものではないが、いずれにしても家族介護者のなかでは、男性はもう例外的で稀有な存在ではなくなっているのです。
――ところで「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」とは?
 ケアメンサミットでの基調講演
ケアメンサミットでの基調講演津止:「介護する側もされる側も、家族介護者の男性も女性も、誰もが安心して暮らせる社会」(結成宣言)ことを目指して、「男性介護者と支援者の全国ネットワーク(男性介護ネット)」が発足したのは2009年3月8日。国際女性デーの日でした。以来、私はネットワークの事務局長を務めるようになりましたが、女性の日に男性介護ネットの発足という奇遇な組み合わせもあって、それまで縁が薄かったジェンダー問題にも関心を寄せるようにもなりました。この日を契機に、介護する夫や息子などを総称して「男性介護者」という言葉が世に広がり、「ケアメン」という造語も私たちの中では普通に使われるようになりました。発足当初は、ほんの数か所を知るだけだった男性介護者の会や集いも、私たちが把握しているだけでももう150か所を超えるまでになりました。会員数は700人弱と小さな会ですが、全国47都道府県のすべてに会員がいます。その意味では、小さいけれど少し大きなネットワークともいえます。
――さまざまなエピソードが紹介されていますが、とりわけ印象深いものがあれば教えていただけますか。
津止:なによりネットワークの発足集会です。そのインパクトは今も忘れられません。遠くは九州や北海道から160人の介護者が集まりました。会場となった私の本務校である立命館大学末川会館のホールは、そのほとんどが白髪交じりの中高年の男性たちで埋まりました。所用の途中でこのイベントに立ち寄ったという人。この集会に参加すれば自分と同じ立場で介護する人と出会えるのではないか、とその参加の動機を語った下の世話も大変だが妻の体調の状態を知るには一番だ、と介護の意味を語る人。かつての企業戦士もいれば、労働運動の闘士も。スピーチが途切れることはありませんでした。「男性諸兄、介護の世界にようこそ!」との樋口恵子さんのメッセージにも胸が熱くなりました。何かこの国の介護の世界が一変するのではないかと思うほどの高揚感に包まれた日でした。
――男性介護者が集い、支え合う「コミュニティ」とはどういったものでしょうか。
津止:「ひとりじゃない! 生きる勇気が湧いてきた」――男性介護ネットの広報リーフレットの表紙を飾るコピーですが、会員から頂いたお便りに記されていたフレーズでもあります。同じ立場で介護する人の話を聞き、いろんな介護の様子を目の当たりにして、「ひとりじゃない!」と叫びたくなったのでしょう。「男のプライド」「介護かくあるべし」という規範から少し解放されて一息つける場となっているのでしょう。手探りの介護生活の中でようやく出会ったコミュニティの効用です。介護する男性という一点でつながる当事者同士の交流で自生するお互い横に並ぶような関係は、指揮命令系統に束ねられたヒエラルキーの職場や、支援する人される人が対面で向きあう相談室とは全く対照的な関係といえましょう。介護が肯定されリスペクトされる貴重な場こそが「コミュニティ」です。各地に広がってほしいと思います。
――出版後の反響はいかがですか。
津止:『男が介護する』の出版を機に、思わぬお便りがあって驚きました。高校の恩師から届いた近況です。たぶんに拙著の帯コピー「100万人へのエール」から取ったものでしょうが、“私も100万人のひとりかな”とありました。“妻は今デイサービスに週3回通っている。本人はもともと行っていたコーラスの集いにいっている、と思っているみたい。でも私が助かっているというのが本音かな”。意外でした。数年前に自宅に伺った時には、むしろ恩師の方が心配だった。会話が弾まなくなった恩師のそばで、「聞こえが悪いの。会話も難しいので大きな声で話してね」と私にこっそり諭してくれていた奥様でした。いま、その奥様がデイサービスに通い、気遣われていた恩師が介護者となって二人の暮らしを支えています。「男性介護」と「老老介護」、“帰省の際は、ぜひ我が家でフィールドワークを”との言葉も添えられてありました。
江戸時代の武士の介護を「第2章 江戸の親孝行から『恍惚の人』まで」で取り上げました。近世女性史の研究者・柳谷慶子さんの研究に依拠した分析だったのですが、小説や映画の「たそがれ清兵衛」がずいぶんと違う印象となった、という感想を言う方もいました。現代の介護にまとわりつく「Shit Job(割に合わない仕事)」というイメージとは全く様相を異にする、「尊い介護」を担う男性たちの実態に、これからの希望も見えます。
――では最後に、今後の取り組みの予定をお聞かせください。
津止:男性介護者の会や集いの取材を続けていこうと思います。こうしたコミュニティは、私が知るだけでも、全国に150か所以上を数えています。本格的なリサーチをすればさらに多くの活動や魅力ある方々に出会えるはずです。主宰者・団体のプロフィール、取り組み内容、開催頻度、参加者の状況、プログラム、運営上の課題等々お聞きしたいことは山ほどあります。コロナ過でのフィールドワークの難しさはありますが、オンラインなどIT技術も活用しながらお話に耳を傾けていこうと思います。こうした取材をもとにいつかまたみなさんにお届けすることが出来れば嬉しいです。
――ありがとうございました。