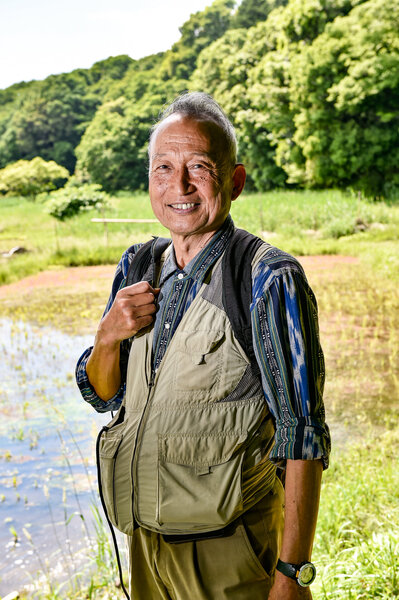- 2022 07/11
- 著者に聞く

(その2)から続く
 アズチグモに捕らえられたヒメウラナミジャノメ
アズチグモに捕らえられたヒメウラナミジャノメヒメウラナミジャノメがヒメジョオンに止まっていると思って、よく見たら、アズチグモの囚われの身でした。
徘徊性といっても、アリグモのように動き回るのではなく、花の上や葉先にじっと第1・2脚を広げて獲物を待っているのが、ハナグモやアズチグモなどカニグモの仲間です。このような大物を仕留めるのだから、毒は強そうです。でもこの毒は、人間には害がありませんから、わたしたちは自然のドラマをじっくり観察できます。
 テンション高いカタハリウズグモの網
テンション高いカタハリウズグモの網足元近くに面白い水平円網がありました。
カタハリウズグモです。渦巻き状の隠れ帯を作っていますので、腹ペコのクモだと分かります。
このクモは満腹のときには直線状の隠れ帯を張ります。渦巻き状の隠れ帯は糸の緊張が増して、小さな獲物でも振動がクモにつたわるのです。このクモは隠れ帯の形でクモの空腹度が分かるのです。
 アシナガグモ
アシナガグモ水辺には大きな水平円網を張るアシナガグモやヤサガタアシグモがいます。
我々が近づいたので、警戒してアシナガグモが網からヨシの葉の上に移動しました。これらのクモは水生昆虫が狙いです。
このように、いろいろな環境があってこそ、いろいろなクモがいます。クモだけでなくいろいろな生物がいることが大事なのです。

クモには網を張るクモ、徘徊性のクモのほかに、地中に暮らすクモもいます。地中に暮らすクモはほんとうに見つけづらいです。秋になって冬虫夏草というキノコ(クモタケ)が生えてきてはじめて、ここに地中性のキシノウエトタテグモがいたのかと分かるくらいです。攪乱されていない場所で見られます。草が生えていると分かりにくいです。
 カントウタンポポの花
カントウタンポポの花この谷津では、ぶらぶら歩いていても30種くらいのクモはすぐに見つけることができます。丁寧に探せば60種くらいはいくでしょうね。
こうやって、クモを探しながら歩いていると、50メートル進むのに30分掛かったりします。ふだんぼうっと歩いていると分かりませんが、草の陰、湿地など、さまざまな環境にあわせて、実にいろいろな種類のクモが生きているのです。
クモ以外にもカントウタンポポ、シュレーゲルアオガエル、タヌキやノウサギなど、この谷津ミュージアムでは、さまざまな生き物を見ることができます。このあたりでは、谷津の豊かな自然が残っているのはもうここだけでしょうね。
しかし、ここの環境が安泰というわけではありません。5年ほど前から、西日本に棲息するヌマガエルが入り込み、ニホンアカガエルやトウキョウダルマガエルが減少しないか心配しています。いろいろな外来植物も入り込み、取り除くようにしています。
人と自然が生み出したこの谷津の自然環境をなんとか、みんなで維持していきたいと思っています。