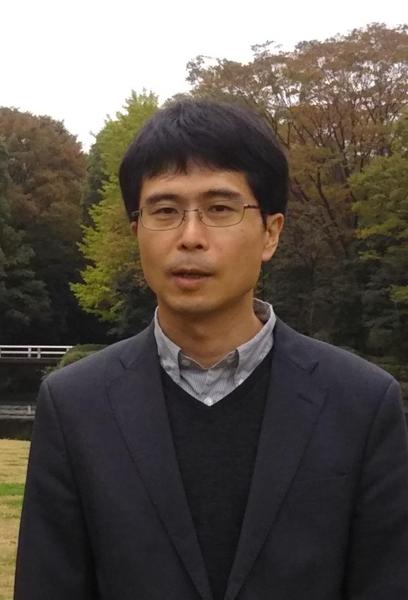- 2019 12/03
- 著者に聞く

かつては、人間の夢や希望を叶えるものとされた科学技術。近年では、AI、バイオテクノロジーなど、人間の生き方・あり方までも変えようとする技術が台頭しています。『科学技術の現代史』は、アメリカを中心に第2次世界大戦以降から現在までの歴史を描いています。技術的進展から、経済的効率性の重視、そして中国の台頭、民間企業の隆盛といった統制・制御が難しい時代へ――。200ページ強で、文系にはとっつきにくいこの歴史を、具体的な技術を取り上げながら、わかりやすく記して下さった佐藤さんに話を聞きました。
――ご本の反響はいかがでしょうか。
佐藤:第2次世界大戦後の75年間にわたる科学技術史を一冊の本にまとめるのはなかなか複雑な作業でしたが、ありがたいことに多くの方から肯定的な評価を頂くことができました。意外な方面から講演依頼なども頂き、現代科学技術の方向性に幅広い方々が関心をもっておられることを感じました。
――佐藤さんが特に読んで欲しかった所、伝えたかったこととは?
佐藤:この本で目指したのは、科学技術の歴史上の出来事を逐一紹介することではありません。科学技術全体の構造変化を描くことが目標でした。もちろん、そのためには個別の事項も重要です。原子力、宇宙開発、コンピュータ、バイオテクノロジー、インターネット、AIなどが登場します。知的財産権、リスク評価、大学の変容、デュアルユース(軍民両用)などの横断的なテーマもとりあげました。これらの個別の分野やテーマについて、簡潔でバランスのよい記述を目指しました。
最大の主張は、「システム」「リスク」「イノベーション」という3つの軸を据えると現代科学技術の構造変化を複眼的に、しかも比較的容易に捉えることができるということです。個別の歴史も重要ですが、それを統合したときに何が見えてくるかを重視しました。
――執筆での苦労、気をつけた点があれば教えて下さい。
佐藤:執筆にとりかかった時点で、ある程度構想は固めていましたが、書き進めていくと絶え間なく大小の修正を加えていかざるを得ませんでした。歴史の論文や研究書を書くときには基本的には時系列で叙述していけばいいのですが、本書はテーマごとに章立てをしたので、各章の整合性をとりつつ順序立てて記述していくのにかなり苦労しました。しかし、苦労した分だけ、最後にはわかりやすい記述になったと思っています。
――「学生に向けた科学技術のベーシックな本を」との話が、企画段階からありました。ネットが身近になり、いつでも情報を得られるようになった最近の学生と、それ以前の学生とでどういった違いがありますか。
佐藤:現在、インターネットであらゆる情報が得られるようになりました。しかし、何かについて体系的に学ぼうとするとき、たいていは本を手に取るほうが実は効率的です。大学の学部生でも、そのことに気づいている学生もいます。
今回の本は現代科学技術の歴史について、インターネットよりもはるかに体系的で確実な情報源となっていると思います。加えて、その歴史全体の構造をとらえる視座を提案しました。
――佐藤さんは、文系と理系の融合点とも言える科学技術の歴史に、そもそもなぜ関心を持ったのですか。
佐藤:大学卒業まではほぼ理系、それも数学・物理系にしか関心がありませんでした。しかし、社会に出ようとするときに、理系の人間が社会で与えられる役割には限界があるように感じました。そこで公務員になって科学技術庁(現文部科学省)に入り、その後さらに米国の大学院で科学技術の歴史を学びました。
私は科学技術あるいは科学者・技術者の社会における位置の現状に対して、根本的な問題意識をもっていたのです。いまでも、あえていえば「正しさの追求」と「強さの追求」はこの世界でどのような関係であるべきかを考えることがあります。
――かつて人類の未来に貢献するとバラ色に輝いていた科学技術が、一歩間違えば人類を滅ぼしかねない時代となりました。これについてはどう思われますか。
佐藤:1960年代中頃までは原子力や宇宙開発といった分野の科学技術が人類の未来を切り拓いていくイメージがありました。ところが1960年代末以降、環境運動や反戦運動が高まり、冷戦の緊張緩和(デタント)が進むなかで、科学技術がもつリスクが顕在化し、その権威と信頼性も揺らいで、科学技術への国家予算の投入が停滞します。
ただ、1960年代以前の科学技術も、もちろんリスクを伴っていました。原子爆弾・水素爆弾、大陸間弾道ミサイルなどが人類全体を脅かし、環境面・安全面などでもさまざまなリスクがありました。ところが、人々はそれを科学技術の負の面とは認識していませんでした。当時は世界が軍事重視・経済拡大の時代であり、科学技術自体に伴うリスクに目が向いていなかったのです。その後時代を追って科学技術のパワーとリスクが増大・複雑化してきましたが、同時に人々の科学技術に対する主観的な視角も変わってきました。
――これからの科学技術の中で、最も関心を持っているものは何ですか?
佐藤:世界を今後最も大きく変えていくという意味でAIです。膨大なデータからパターンを見出し、判断をしたり予測をしたりすることに長けているAIは、人間の知的能力の多くの部分をしばしば人間より優れたレベルで代替できます。しかもそれをリアルタイムで細かくできる。例えば自動運転車や電力の需給調整などに応用できます。今後我々の社会はあらゆる面で最適化された、無駄のない社会になっていくと想像できるでしょう。
AIは、第2次世界大戦以降、これまでの情報通信技術の歴史の延長線上にあるものです。驚くべきことは、原子力や宇宙開発やバイオテクノロジーなどと違って情報通信技術だけは75年もの間、圧倒的なペースを維持して進化し続けてきました。今後、この勢いが変わることを予想することは難しいように思います。
――シンギュラリティについては、どのような意見を持っていますか。AIは人類を超えるでしょうか。
佐藤:今後、AIが人間を凌ぐパフォーマンスを示すタスク領域が拡大し続けていくことは確実でしょう。一方で、人間のもつすべての能力をAIが超える事態や、AIが人間の意思を離れて自律的に進化し人間を服従させるような状況になることは、少なくとも想像可能な未来には起きないだろうというのが、現時点での主流の意見です。
しかし未来予想は、その通り実現しなくても、少し違う形で実現することもある。例えば、近年中国を中心に、AIがはじき出した個人個人の「信用度スコア」が普及し始めています。また、日本を含め各国の企業で採用や人事にAIが用いられるようになってきています。人類がいつの間にか、AIの支配を部分的に受け入れていくような時代になる可能性は十分にあるのではないでしょうか。
――これからの研究について、また次回作についてお聞かせ下さい。
佐藤:これまで、科学技術史、科学技術政策史、大学の変容と研究資金、政策形成と科学との関係などについて研究してきました。かなり多様ですが、すべて科学技術の社会での位置というテーマに関わっています。
最近では、あらゆる社会経済領域でデータ分析の威力が増していることが気になっています。データ分析の統計的・定量的アプローチは科学技術全体の性格も、科学技術と社会との関係も変えていくでしょう。次回作の予定はまだありませんが、今後はデータ重視の時代における科学技術と社会の変化について研究を進めていきたいと考えています。