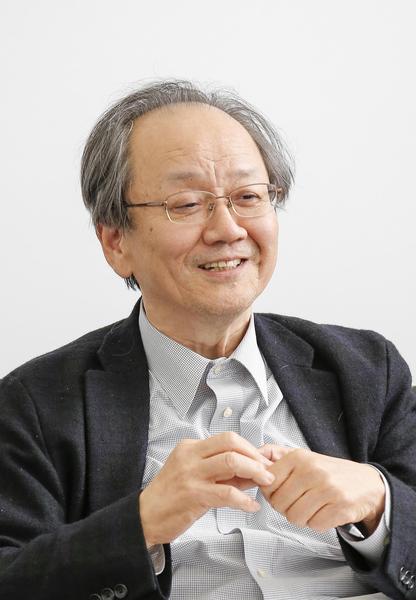- 2019 09/25
- 経済社会の学び方

本連載は加筆・修正の上、中公新書『経済社会の学び方 健全な懐疑の目を養う』として2021年9月に刊行されました。現在、好評発売中です。連載第4回以降の記事は書籍でお楽しみください。
■社会研究と自然科学の違いとは
自然科学と社会研究の間には違いがいくつか存在する。もちろん、これら二つの分野の間に明確な境界線が引かれるわけではない。たとえば霊長類の研究(primatology)などは、猿やゴリラ、チンパンジーの心理や行動、あるいはその集団の支配や秩序の構造と機能のしかたなどを研究する場合、用いられる概念や理論は、社会研究と似てくるであろう。しかしおおまかに両分野の研究対象、問題の立て方、接近方法などを比べれば、一般に、自然科学と社会研究に違いが存在することは確かだ。その違いと共通点についていくつか確認しておこう。
■個別の経験がすぐに学問にはならない
物理学や化学の分野の専門家たちの論争や研究テーマについて、一般の人々が意味のある発言をするということはまず無理だろう。それほどに玄人と素人、あるいは専門家と非専門家の間の知識や理解の溝は大きい。それに対して、政治や社会の問題に対しては、誰しも自分の生活から得た個別的な知識や経験に基づいた意見を持っている。そうした知識や経験は貴重ではあるが、どれほど一般化できるのかは疑わしい。
社会研究には非日常性(危機など)を研究する分野もあるが、多くは、原則として人々の日常生活(ordinary life)の基本構造をその論究の対象としている。人々は社会問題の性格を「個人的には」実感しているものの、その実感がそのまま経済学や政治学の知見となるわけではない。経済学の主眼は、あくまである意図なり変化が、「全体として」どのような帰結を生み出すのかという点を分析するところにある。したがって個人の経験と関心そのものがそのまま学問となるわけではない。
しかしインフレや失業のような誰もが経験する身近な問題では、その分析のための訓練を全く受けていない者の発言が声高になることがある。こういう現象は、自然科学の分野では起こりえない。つまり、物理学や医学・生物学で何かを論じることは、長い間積み上げてきた基礎的訓練があってはじめて可能になるからだ。社会研究においても、こうした事情はほとんど変わりがないのだが、問題自体の「身近さ」ゆえに、その学問が持つ体系を全く考慮しない意見や主張を述べることができる。
社会研究にも「積み上げ型」の基礎的なトレーニングが必要だということは意外に理解されない。統計の見方、文書資料の読み方、聴き取り調査の進め方などは、すべて時間のかかる訓練を必要とする。人間の「こころ」を研究する心理学なども、すぐに人の心が分かるようになるというわけではない。分析の仕方を、訓練によって学び取らねばならないのだ。高校時代の友人が、上智大学におられた臨床心理学者の故霜山徳爾先生の著作に感銘して、人間学的な心理分析の勉強をしたいと強く思い、霜山先生に直接うかがってアドバイスを求め、「何をまず読んだらよいでしょうか」と尋ねたところ、「まず、ドイツ語を勉強しなさい」と言われたと筆者に話してくれたことがあった。これこそ、「魚を素手でつかみ取ることなど無理だ。まず網を作るか、釣り道具を手に入れなさい」という迂回生産の原理の重要性を指摘したアドバイスであったと思う。回り道をし、「積み上げて」いかないと、何も手にすることはできないという点で、あらゆる学問の根本は同じなのだ。
■定義の不確かさ
すでに述べた点であるが、自然科学には概念そのものに、量的に測定可能なものが含まれているものが多い。自然科学では(筆者の自然科学の知識は、大学受験と大学教養部時代に学んだ物理学と化学以上のものではないので、やや粗い見方かも知れないが)、概念と用語には「一意性」が認められ、測定可能なものが中心をなしている。したがってその根本概念には曖昧さがない。しかし人間や社会の研究においては、その中核的な概念がかなりの幅を有している場合が多い。測定できたとしても、定義がいくつかあり、したがってその結果は一つではない。先に述べたように、「豊かさ」を測定するのにも、指標はGDPだけではないのだ。
経済学で中核的な位置を占める「資本」という概念も、一意的にその意味が確定できず、測定の段階になると、その困難はさらに高まる。たとえば、数年前に大変な評判を生んだフランスの経済学者トマ・ピケティの大著『21世紀の資本』(山形・守岡・森本訳、みすず書房)で用いられた資本概念は、マルクスの資本概念とも、現代経済学の主流とも異なっている。ピケティが定義する「資本」概念には、機械などの物的資本だけでなく、住宅(これをピケティは重視)、土地、金融資産(現金、債券、株など)、知的財産権、奴隷の価値なども含まれており、「富」の概念に近い。実際、ピケティは資本、富、資産をほとんど同義に用いている。
もちろん、明確に定義され、測定されているわけであるから、それ自体に問題があるわけではない。しかし「資本」という概念と用語の用い方が、研究者によって異なるという点は注意を要する。経済学におけるもっとも基礎的な概念ひとつをとっても、定義が確定していないのだ。こうした問題は概念の一意性という厳密さを重んじる自然科学では、あまり見られないのではなかろうか。
■大根を「正宗」で切らない
自然科学と社会研究の間には、このような相違があるものの、それぞれ独自の研究対象と方法があることに注意すべきだ。自然科学の厳密さそのものを尊重するあまり、問題も対象も異なる問いに対して、自然科学の研究メソッドをそのまま社会研究に用いることが、学問的な進歩だと思い込んでしまうことは避けねばならない。この点についても、アリストテレスの言葉は傾聴に値する。
「われわれの対象の素材に相応した程度の明確な論述がなされるならば、それをもって充分としなければならないであろう。(中略)だいたい荒削りに真を示すことができるならば、つまり、おおよそのことがらを、おおよその出発点から論じて、同じくおおよその帰結に到達しうるならば、それをもって満足しなければならないであろう。(中略)その場かぎりの仕方でかたることを数学者にゆるすことが不可ならば、弁論家に厳密な「論証」を要求するのも明らかに同じようにあやまっているのである」(『ニコマコス倫理学』第1巻第3章)
要するに、大根を名刀「正宗」で切ることはないということなのであろう。
■なぜフィールド・リサーチは避けられるのか
「方法論」の最後として、近年あまり論じられることのない、「聴き取り調査(フィールド・リサーチ)」について簡単に触れておこう。労働研究の分野でもフィ-ルド・リサーチを行う若い研究者が減ってきたことが同業者の間で話題になることがある。何故、フィールド・リサーチは避けられがちになったのだろうか。その理由をまず考えてみたい。
近年の「社会科学」の実証研究は膨大な量の数量データを用いて、変数間の数量的関係(多くの場合相関関係)を調べるために回帰分析等の統計的推定作業を行ない、仮説をテストするという計量的手法を用いるものが圧倒的に多い。こうした統計処理が中心のエコノメトリック・メソッド(計量経済学的方法)を用いた論文には、自然科学分野の論文と似た定型的な形式がある。まず問題を提示し、これまでの先行研究の問題点や限界を論じ、いかなるデータを用いて、変数間のどのような仮説を新たにテストするのか、その結果として新たに何が分かり、何が未解決なのかという構成になっている。
しかし社会研究の論文の場合、このような構造をそのままとることが困難なケースがある。そもそも既存の概念や理論モデルを前提としないような問題の研究は、数量的な分析にすぐさま入ることは難しい。特に「事実」の発見を中心としたフィールド・リサーチの場合、直ちに統計的な処理を適用できるような条件やデータが整っているわけではない。
定まったスタイルがないならば、研究論文としてまとめる際、プレゼンテーションに困難が伴うことは避けられない。フィールド・リサーチには、設定された問い自体に数量化を拒むような性質のものが多い。探求したい問いを、仮説として命題の形に定式化(formulate)することに高いハードルがある。さらに、仮に問いが出来上がっても、概念を変数に置き換えるに際して、適切な指標の選択に時間がかかる。必要な概念化(conceptualization)が難しいだけでなく、先に「技能」の問題を例として説明したように、仮説を立てテストできるようにするための「指標」を開発することが容易ではない。要するに、フィールド・リサーチには「形」が作りにくく、論文としてまとめあげるまでには、相当の時間がかかるのだ。研究に時間がかかれば、論文の形でそれが同分野の研究者達から認められるのにも時間がかかる。優秀さを早く認められたい者は、よい結果が早く論文の形でまとめられる形式のアプローチをとるであろう。
■試行錯誤の可能性
しかし、社会研究の対象となる諸々の問題は、エコノメトリック・メソッドだけで答えが得られるものばかりではない。現実には、統計が使えない、あるいは量化できないタイプの実証的問題があまた存在する。また、数量的なデータや文献資料が存在し、利用できても、現実の慣行と資料が異なると推測されるようなケースも存在する。
研究者は、関心を持つ問題の全貌を初めから知悉しているわけはない。現実の(経済)活動を観察し、聴き取りをさせてもらい、時として現場に参与させてもらいながら、生きたままの活動に接することによって初めて感知される問題も多い。したがって、新しい問題の理解や解決方法を見つけようとする場合、フィールドで発見的に(heuristic)に調べるという方法が不可欠になる。
これはいわゆる「アンケート調査」と呼ばれるものと対極をなす。アンケート調査は、研究者が設定した問いに答えてもらい、その回答結果を解析する。問題はすでに「問い」の形で、研究者の知識と問題意識の範囲内に限定されてしまっている。したがって、「やはりそうだった」、「予想通りだった」という理解に終わる場合が多い。予想と異なっていたからといって、さらに新しい問いや情報が入ってくるということはない。つまり、研究者の認識と理解に新たな発見はなく、確認するという作業に留まりかねない。その意味では、研究としては、アンケートを実施した段階で終結していると言える。
フィールド・リサーチには、試行錯誤の可能性が織り込まれており、聴き取りを続ける過程で発見された事実で、新たに修正された仮説をさらにテストすることが可能になる。もちろん、フィールド・リサーチと一口に言っても、その目的と密度によって様々なタイプに分かれる。一応大きく三つに分けると次のようになろう。
1)国際比較のための大規模な聴き取りを軸にした共同研究。いくつかの「論文」と「本」にまとめあげることを目的とするもの。
2)(数量的分析のための)部分的仮説をテストするため、小規模な聴き取りを事前に行うもの。問題意識が現実的な妥当性を持っているかを調べるための聞き取り調査である。
3)計量研究・理論研究の準備段階として、予備的に行うもの。米国の理論経済学の創発的な研究にはこれを含むものが多い。
具体的なフィールド・リサーチの進め方についての古典的な著作では、ウェッブ夫妻、マックス・ウェーバーなどの調査論が存在する。近年の労働研究や社会学の分野では小池和男、佐藤郁哉などによっていくつかの優れた「指南書」が書かれている。ここではフィールド・リサーチを行うにあたって、道に迷わないために1点指摘するだけにとどめたい。
■研究計画書のすゝめ
そもそも自分が何を知ろうとしていたのかを書きとどめておく事は重要だ。そのためにまず研究計画書を作成しなければならない。とにかく書いてみるということは、いかなる場合でも、自分の「考えの浅さ」を知るために必要だ。また、一度聴き取りをはじめると、面白くなりどんどん本来の目標と別方向に好奇心が働き始め、自分が何を知ろうとしていたのか見失ってしまうことがある。そうした混乱を避けるためにも、研究計画書は不可欠だ。研究費の申請のためにも、聴き取りに応じてくれる人に研究の趣旨・目的を理解してもらうためにも研究計画書は不可欠だ。テーマ・問題意識(何故この問題を取上げるか)から始まり、何を、何で説明しようとしているのかを事前に検討(共同研究の場合は、メンバーの間で共有)しておかなければならない。
■文献サーベイの重要性
最後に、従来の研究をおさえるための文献のサーベイ(調査)の重要性について指摘しておく。これまで何が、どこまで研究されてきたのかを調べることは不可欠だ。先行研究を知ることは、思考の節約のためにも、先達の研究へ敬意(クレディットの形で)を示すためにも欠かせない。そして、先行研究のどこが問題か(不十分か)、自分の研究が新しく何をつけ加えられるとすれば、どの点においてなのかを示さなければならない。先人の仕事と関係なく、研究者が一人で、全くの白紙から何かを新しく生み出すという例は現代においてはほとんどない。すべては積み重ねなのだ。
この点について、山中伸弥教授が、ノーベル賞を受賞した時の会見で、同時に受賞したジョン・ガードン英ケンブリッジ大名誉教授の仕事に言及しながら、概ね次のように述べていたことが印象に残る。
科学的な真理は、何枚ものヴェールにおおわれている。科学研究はそのヴェールを、いわば一枚一枚はがしていくようなものだ。ガードン博士は厚いヴェールを取り除いて、見通しをよくした。自分もその流れの中で、たまたま運よくかなり重要な一枚をはがす幸運な研究者となった。
学問と研究は「運、鈍、根」と言われることがあるが、彼はその事実を冷静に観察して謙虚に語っていると感じた。
(以下、次回。参考文献は、新書刊行時にまとめて表示いたします)