- 2017 11/22
- 著者に聞く
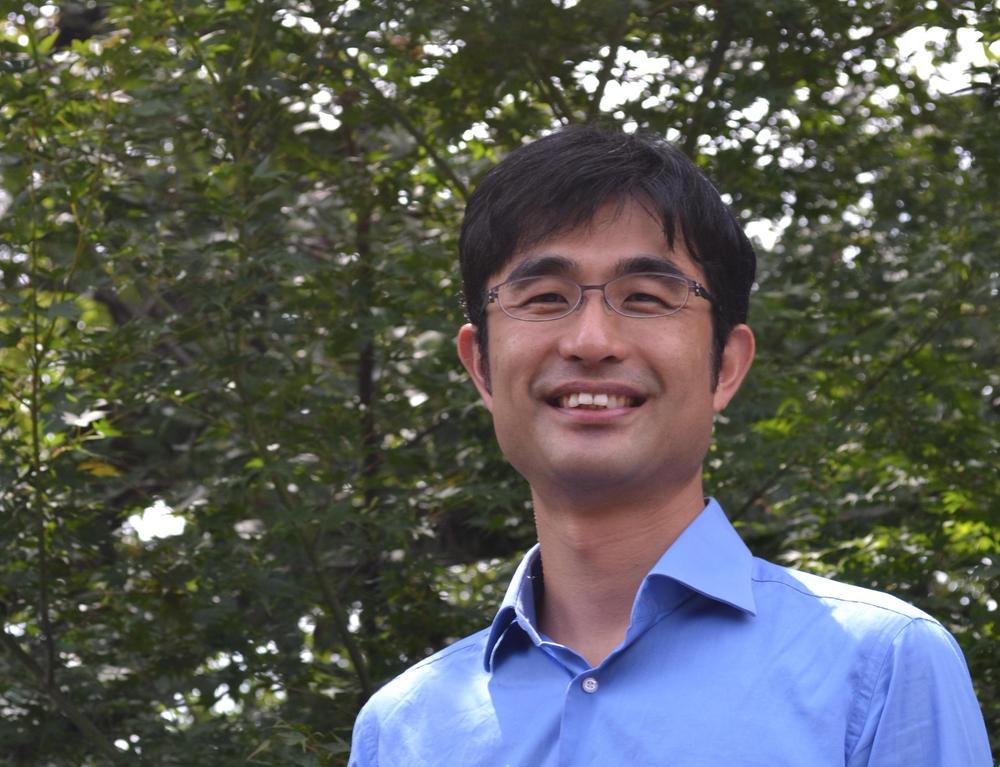
『トラクターの世界史』を上梓した藤原辰史さん。19世紀末にアメリカで発明されたトラクターが、人類の歴史をどのように変えたのか描いた意欲作です。トラクターという着眼点や執筆時の苦労などをうかがいました。
――トラクターへの関心はいつ頃からですか。なぜ、『トラクターの世界史』を描いてみたいとおもったのですか。
藤原:小学生の頃、山に囲まれた田舎の春のよく晴れた日でした。祖父が田んぼで運転しているトラクターがとても格好よくて近くで見てみたいとおもいました。近寄ろうとすると、「危ない! 近寄るな!」と祖父が怒鳴りました。彼の怒鳴り声が、わたしにとってのトラクターの原体験です。
普段は無口な祖父でしたが、騒音と振動が激しいトラクターがどれだけ危険な乗り物であるのか、孫を事故に巻き込んだ事例があとをたちませんでしたから、伝えたかったのでしょう。そういえば、機械を扱うときは、いつも怒鳴っていました。
研究テーマとしてトラクターに関心を抱いたのは大学院生の修士課程の頃です。ナチス時代の農民の暮らしが知りたくていろいろ資料を探していたのですが、行き詰ってしまいました。あるとき、パラパラめくっていた新聞に可愛い「ブルマー」という名前の小型トラクターの広告(わたしをトラクターの道に誘ってくれた感謝を込めて、ブルマーの写真を本書で掲載しました)が載っていて、これも農民の暮らしの一部だと知ってから、真っ暗なトンネルにかすかな光が見えた気がしました。
 ブルマーの広告。出典:Deutsche Landwirtschaftliche Presse, 25. 9. 1937.,
ブルマーの広告。出典:Deutsche Landwirtschaftliche Presse, 25. 9. 1937.,ゼミも変わっていて、先生も学生たちも、こんな変なテーマを選んだことを非難するどころか、面白がってくれたことにも勇気付けられました。ただ、修士論文はドイツのことだけだったので、本場のアメリカや歩行型トラクターの歴史が長い日本も含めて、トラクターの世界史を描いてみたいという思いはずっとありました。
――執筆にあたって最も苦労した所はどこですか。
藤原:一つは「世界史」と名乗ってしまった以上、文字通り「世界史」を書かなければならなかったことです。
国民史の限界が指摘されて久しいのですが、わたしもその限界のなかで悩んでいて、ふがいない自分を鍛えるためにも、あえて「現代史概説」という講義を京都大学の全学共通科目で開講したくらいです。それでも、20世紀の歴史はドイツ中心で学んできていて、あまりにも世界の「現代史」を知らないことを思い知らされ、途中で後悔しました。
集まる資料がアメリカと西欧中心になるので、思い切って、ガーナ、東ドイツ、ポーランド、チェコ、中国などの歴史を研究する友人や同僚に問い合わせて、いろいろ聞いたり、教科書を読んだりして、学生に戻った気分で世界史を学びました。スポーツでいえば、体がなまっているのに、走り込みで基礎体力をつけるとことから始めたのが、とても苦しかったです。でも、この本ほど、同僚や友人たちのありがたさを感じた本はありませんでした。
二つ目は、トラクターの構造についてです。工学的な知識も、トラクターの扱い方の映像や画像、農業機械の専門書だけでなく、実際に運転してみたり、触ってみたり、ヤンマー農機の工場見学をしたりして、勉強しました。これも頭で理解するまでかなり時間がかかりました。
――特に注目して読んでもらいたい所はどこでしょうか。
藤原:一つ目は、世界史であるとともに地域史でもあること。岡山の歩行型トラクターの開発がなければ、「トラクターの世界史」は成り立ちません。島根のその開発も、GHQとの関係が重要です。また、どちらも伝統的な製鉄方法である「たたら」とからんでいることも今回の大きな発見でした。
二つ目は、「トラクターの文学史」にもなっていることです。大学院のとき、文学史を専門とする指導教員からたくさんの面白い小説を紹介してもらい、むさぼるように読みました。そのため、ほかの歴史研究者よりも文学を用いる頻度が高いのですが、この『トラクターの世界史』はこれまででも最も文学を用いたい欲望を解放したものになっています。
文学は、歴史を知るうえでも、書くうえでも、たいへん有意義です。とりわけ、スタインベックの『怒りのぶどう』の強烈なトラクター描写は修士論文のときに出会ったので、思い入れが深い箇所です。
――『トラクターの世界史』を通して伝えたかったことは何ですか。
藤原:なによりも、トラクターという機械の魅力です。
家畜からトラクターになるときの農民の反応についてもかなり言及しました。若者は恋するように魅せられていました。また、こんなパワーがあるのにゆっくり動く。それは自然と闘っていることの証拠だと思います。さらに、同じ内燃機関でも、自動車以上に世界各地でデザインが異なります。世界にはトラクターファンがたくさんいますが、それはトラクターのデザインが多様だからです。
なぜ、こんなに大事な機械が見過ごされてきたのか、わたしはいまだに不思議なのですが、おそらく、農業全般に関心がなくなっているからだと思います。でも、トラクターがなければ、第一次世界大戦も、世界恐慌も、ダストボウルも、スターリニズムも、日本の戦後も、違った様相になっていたことでしょう。
それとともに、この機械の魔力です。
事故の多さと健康への影響についてもページを割きましたし、戦車ファンの業界では常識すぎてだれも話題にしない戦車への転用も、あらためて向き合いました。
以上の問題は、トラクターだけの問題ではありません。自動車や携帯電話、身の回りのあらゆる機械に共通するものであり、この本を通じて、ぜひ、まわりの機械との付き合い方を考えるきっかけになってくれればと願っています。化学肥料と農薬のデュアルユースについては、十月に上梓した『戦争と農業』(集英社インターナショナル)で詳しく触れましたので、あわせて読んでいただければ、ありがたいです。
――ご専門は農業史ですが、なぜこの分野に関心を持ったのですか。
藤原:減反や食料自給率の低下のニュースを聞いて、なぜ、日本の農業はこんなに軽視されているのだろうと疑問に思ったことがきっかけです。
そういう思いから、大学の国際関係論のゼミで、一度、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)とコメ自由化の発表をしたことがありましたが、そのとき、いつも鋭い発言をして、仰ぎ見ていた院生から「なんでそんな古い、終わったテーマをやるんだ」と言われたのがショックでした。京都大学の院生が食料問題の構造にほとんど関心がないことに驚いたわけです。
ところが、大学三年生のときに、ナチスの概説書を読んでいたら、ナチスが自給自足を目指していたことを知って、そのことを家族に伝えたら「食料自給自足と公約に掲げたら、ナチスに投票する」と言ってまた別の意味で驚きました。
このことを指導教員に伝えたら、研究テーマとして面白いじゃないか、と言ってくれた。こんなテーマでも大学で研究できるんだ、と勇気づけられました。ここから、この研究をしようと思いました。
――今までの著作『ナチス・ドイツの有機農業』や『ナチスのキッチン』、また今回のご本でもナチス・ドイツにおけるトラクターの受容についても大きくページを割いています。ナチス・ドイツへの関心は、どういったことからでしょうか。
藤原:戦争はなぜ起こるのか、戦争はなぜ終わらないのか、という疑問を小学校の頃から抱いていました。家族の旅行で広島の平和資料館に訪れたときに見たあの人形や、ケロイドの写真を見たときのショックが、いまなお続いています。大学の講義でナチスのことを学んだのもそういう問題意識からでした。
大学で学んでみると、ナチスが試みた政策は、一方で、弱者を「生きるに値しない生命」として殺したり、ユダヤ人やシンティ・ロマたちを大量に殺したり、他方で、食料自給自足政策や貧困対策などいまの日本に必要なものがあり、いったいナチスとはなんだったのか、考え込んでしまいました。この地点から、ナチス・ドイツへの関心は現在まで続いています。
――今後の関心やテーマについてお聞かせ下さい。
藤原:今後も、食と農の歴史および思想研究を、大学の枠にとどまらず、芸術家、農家、陶芸家、運動家、詩人、図書館の司書、専業または兼業主婦、不登校児のための場所作りをしている人々、子どものための美術学校をしている方々、戦争について考える集会を開いている住職、映像作家、写真家、保育園や中高の先生たち、独立系の編集者たち、味わいある本屋さんなど(すべて具体的なお名前が上がるかたばかりです)、これまでお世話になってきた方々とともに続けていきたいと思っています。
プロジェクトは二つに分かれています。一つ目は、食と農を根拠とした思想、「分解」というキーワードを軸に据えた思想を生活者や表現者と一緒に構築するために、食と農を根拠にしようとした過去の学問や思想を検討し、批判することです。たとえば、それは農本主義であったり、農学の哲学であったり、健康食の運動であったり、戦争中に活況を呈したものであることがポイントです。
二つ目は、ともに食べる場所の研究です。「縁食」という言葉をキーワードに、家族の外での食の形態、たとえば、給食や食堂の歴史について調べています。孤食と共食のあいだに存在する食のかたち。これを歴史的に検討するとともに、具体的に探っていくことを目標に据えています。
――読者にメッセージがあれば是非に!
藤原:農業技術がどのようなものであるかをぜひ詳しく知ってください。読者のみなさんの生命活動と密接に関係しています。もっといえば、みなさんの生命を左右するものです。にもかかわらず、これまであまりにも無視されてきました。本書がひとつのきっかけとなって、食と農の新しい技術のかたちが議論されていくことを心から祈っています。

