- 2025 07/24
- まえがき公開
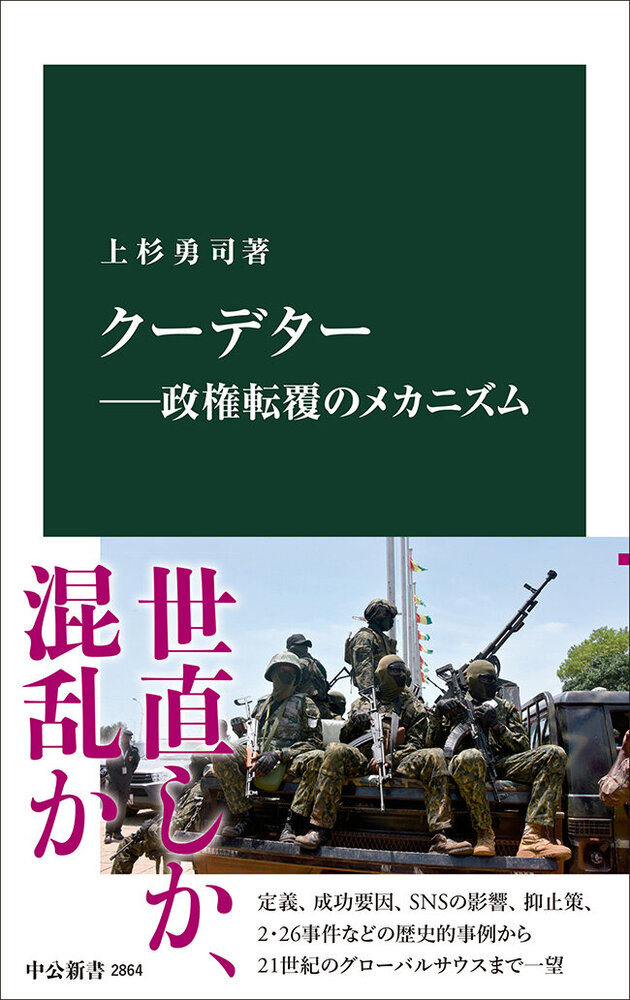
クーデターとは非合法的な政権奪取である。国際秩序の変動期に「避けられない悪」として頻発するが、昨今またその兆候が著しい。本書は昭和の動乱期から21世紀のグローバルサウスまで、未遂や失敗例も含め幅広く検証。行動原理や成功要因を解明し、民主主義vs.権威主義vs.イスラム主義、SNSの影響、資源争奪、ワグネルの暗躍など現代の特徴に切り込む。当事国の民政移管や治安部門改革への支援など、日本の役割も問う。 『クーデター―政権転覆のメカニズム』の 「はじめに」を公開します。
クーデター(coup d’État)とは、フランス語で「国家に対する一撃」という意味をもつ、非合法的に政権を奪う行為だ。居合の抜き打ちのように、一瞬のうちに政権の息の根を止める。
日本史上最も有名な例は、本能寺の変であろう。この謀反は、家臣の明智光秀が密かに計画したものであり、織田信長の天下が一夜にして奪われた点で、クーデターと呼ぶにふさわしい。支配階層に属する一派が、政権の実力者を一撃で引き摺り下ろす。これがクーデターの特徴だからだ。
政権奪取の手段として、軍が使われた場合、それを軍事クーデターと呼ぶ。権威主義体制を研究するジョン・チンらによれば、第2次世界大戦後に発生したクーデター(未遂を含む)の96.6%に軍が関与している。ただし、軍が動員されたとしても、ほとんど交戦することなく政権奪取ができる場合もある。これを無血クーデターという。
クーデターの歴史は古い。『クーデター』を著した尾鍋輝彦は、ナポレオン・ボナパルトによる1799年のブリュメール(霧月)18日から論を起こす。とはいえ、クーデターが頻発したのは、第2次世界大戦後に多くの植民地が独立してからだ。
イリノイ大学『クーデター・データベース』によると、1945年から2024年までに1094件のクーデター(未遂含む)が世界各地で発生し、その半数近くの458件が成功している。
発生数がピークを迎えたのは、1975年のこと。それから減少傾向となり、ソビエト連邦(ソ連)崩壊直後に一度は増えたものの、再び下降して2018年には1件にまで減った。ところが、翌19年以降、アフリカでは、スーダン、マリ、ブルキナファソ、ギニア、ニジェール、ガボンなど計9件が相次ぐ。アジアも無縁ではない。21年のミャンマーやアフガニスタン、22年にはカザフスタン、パキスタン、スリランカで発生した。
近年のクーデターでは、従来のものとは異なる性質が目撃されている。独裁者に対する国民の不満と民主化への衝動がソーシャル・メディア(SNS)と結びつき、新たな政権奪取への原動力を与えた。民主主義と権威主義の対立やイスラム主義の台頭など、新たなイデオロギー対立の影響も見逃せない。レアメタル(希少金属)などの資源争奪戦やロシアの「ワグネル」など民間軍事会社の影響があるとされる。
クーデターは遠い国の話だと思っている人が多いだろう。しかし、対岸の火事だと思って看過してはいけない。なぜならば、日本の国益に大きな影響を及ぼすからだ。
2021年にミャンマーで発生したクーデターは、日本にとっても衝撃だった。同国の民主化や開発のために注ぎ込まれた日本の支援が、一夜にして水泡に帰したのだ。日本企業や在留邦人の安全や利益も危うくなった。さらに、ミャンマーの混乱は、中国や東南アジア諸国連合(ASEAN)など周辺国との関係にも影を落とす。
現在、クーデターが頻発しているアフリカも、日本にとって無縁な存在ではない。国連が2024年に発表した統計によると、アフリカ54ヵ国の総人口は約15億人を超え、2050年には24億人を超えると見込まれている。資源の供給地としてだけでなく、成長市場としても魅力的なアフリカが安定するか否かは、日本の繁栄と深く結びつく。クーデターという現象を理解することは、現代に生きる私たちに欠かせない教養となるだろう。
19世紀に入り、近代から現代へと国際秩序が移行した時期には、欧州の大国においてクーデターが発生した。そして、20世紀になって新秩序が形成される変動期には、日本、ドイツ、イタリアといった新興国で決起が続き、軍国化が進み、民主化が後退した。国際社会の変動期や国家の成長期には、クーデターが権力闘争を象徴する一つの政治現象として見られた。
イデオロギー対立は東西冷戦中からあった。冷戦期は、米国のCIAやソ連のKGBが暗躍していた。民主化が重視されていたわけではないため、決起側は親米か親ソを選べば、政権奪取後に援助を受けられる当てがあった。
ところが、冷戦後の世界では、勝者として米国が民主主義を広めていく。この国際秩序のもとでは、政権奪取が成功しても、その後の政権の正統性を欧米諸国から認められる見込みが薄く、国際援助を得られる可能性もない。現状に不満があったとしても、欧米諸国からの援助の分け前を期待している支配階層にとって、決起は得策ではない。よって、この時期はクーデターの動機づけが弱まっていたといえよう。実際に冷戦後の決起数は、全世界的に減少傾向にあった。
だが、米国主導の国際秩序に陰りが見え始めると、権威主義体制への傾斜やイスラム主義の復古が顕著になっていく。民主的な国家が政変によって軍事政権や権威主義体制へと変更される現実が生まれた。
このような国際秩序の変動期の兆候は、現代にも顕れつつある。だから、クーデターについて学ぶことは、今後の世界が、どのような道を歩むのかを読み解くヒントを与えてくれるだろう。
本書では、第1章で具体的な事例を参照しながら、クーデターを定義づける。近代から現代までに、どこで、どのような政権奪取が試みられてきたのかを概観する。
第2章では、その原因と成功条件を明らかにしていく。決起側の視点から、動機を考え、過去の事例から、成功条件を導き出す。その観点から、ロシア、北朝鮮、中国といった権威主義体制の国家でクーデターが発生する可能性も検討する。
第3章では、21世紀の傾向として、民衆の役割の増大と軍による権力の横取り、携帯電話やSNSの効用、民主主義vs.権威主義やイスラム主義といった思想対立、資源争奪戦の影響、民間軍事会社の暗躍の5点に絞って分析する。
第4章では、政権側の視点から、クーデターを防ぐ方法を探る。韓国やタイなど課題を抱える国を分析する。イラン、イラク、シリア、レバノン、マリなどの事例を考察し、効果的な抑止策を導き出す。
第5章では、再び決起側の視点に立ち、政権奪取後の民政移管の課題を示す。
第6章では、先行研究にはなかった治安部門改革という平和構築の観点から、クーデターが起こらない社会を作るための処方箋を示す。
第7章では、日本の読者に馴染みがある2・26事件を取り上げ、その歴史的教訓から21 世紀型クーデターの理解を促す。
第8章では、日本外交として、世界で多発するクーデターに、いかに対応すべきかを論じていく。
終章では、平和を促す手段としてのクーデターの可能性と限界を議論する。過去には独裁者を倒し、民主化をめざすクーデターがあった。ダルマ落としのように、独裁者や腐敗した権力者をスパッと排除できれば、民主化や世直しにつながる可能性はある。しかし、突き落とした後のダルマがぐらつくように、社会が揺れ、政情が乱れれば、第2、第3のクーデターや内戦を呼び込みかねない。理想をいえば、クーデターを用いることなく、政権交代ができることが望ましい。しかし、それが叶わない社会に残された最後の手段として、民衆と軍が連携する「世直しクーデター」は認められるのか。21世紀のクーデター像に迫る。
(まえがき、著者略歴は『クーデター―政権転覆のメカニズム』初版刊行時のものです)
