- 2025 02/07
- まえがき公開
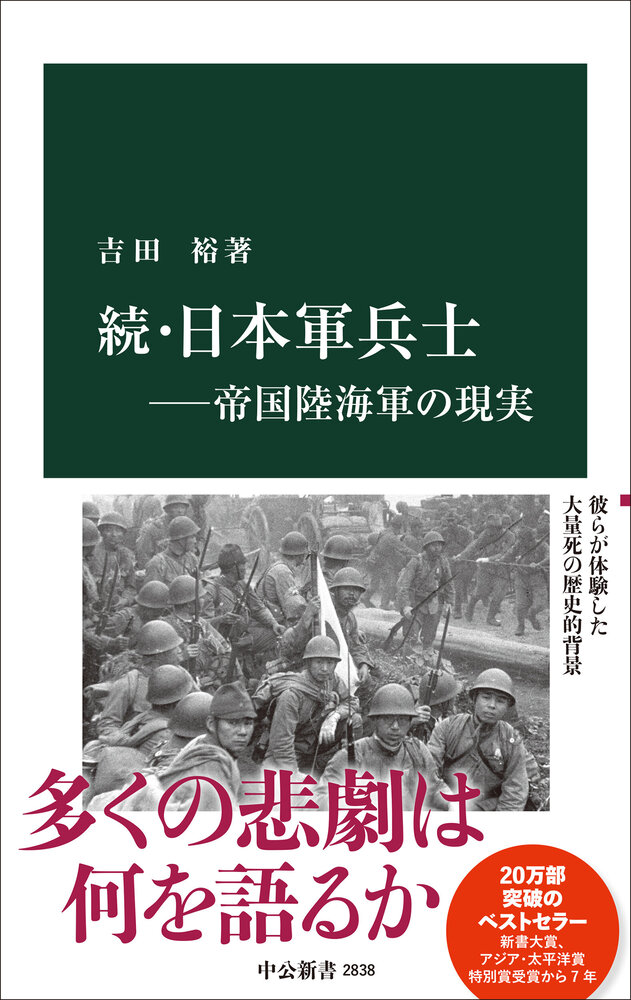
先の大戦で230万人の軍人・軍属を喪った日本。死者の6割は戦闘ではなく戦病死による。この大量死の背景には、無理ある軍拡、「正面装備」以外の軽視、下位兵士に犠牲を強いる構造、兵士の生活・衣食住の無視があった。進まない機械化、パン食をめぐる精神論、先進的と言われた海軍の住環境無視……日中戦争の拡大とともに限界が露呈していく。本書は帝国陸海軍の歴史を追い、兵士たちの体験を通し日本軍の本質を描く。 『続・日本軍兵士―帝国陸海軍の現実』の 「はじめに」を公開します。
1937(昭和12)年7月の日中戦争の勃発から、アジア・太平洋戦争の敗戦までに、約230万人の日本軍兵士が戦争で死んだ。その多くは戦闘による死ではなく、病気による死(戦病死)だった。これまでの戦争ではみられなかった大量の海没死(船舶の沈没による死)や、特攻死(特攻攻撃による死)などの異形の死も、この時期、特にアジア・太平洋戦争期の特徴だった。退却や玉砕(全滅)の際に、捕虜になるのを恐れて友軍によって殺害される傷病兵も少なくなかった。
2017年に刊行した『日本軍兵士――アジア・太平洋戦争の現実』では、さまざまな史料に基づいて、そうした無残な大量死の実態を明らかにした。しかし、大量死の歴史的背景、なぜ大量死が引き起こされたのか、という問題については、陸海軍の軍事思想の特質、統帥権の独立、日本資本主義の後進性などについて、ごく簡単に言及するにとどまった。
そこで本書では、無残な大量死が発生した歴史的背景について、明治以降の帝国陸海軍の歴史に即しながら、できる限り具体的に明らかにしたいと思う。その際、次の3つの視角を重視したい。
第1は、いまふうに言えば、「正面装備」(直接戦闘に使用される兵器や装備)の整備・充実を最優先にしたため、兵站(人員や軍需品の輸送・補給)、情報、衛生・医療、給養(兵員への食糧や被服などの供与)などが著しく軽視されたことである。
それはまた、軍隊だけでなく大日本帝国そのものの持つ危うさでもあった。夏目漱石はその作品のなかで、主人公に次のように語らせている。
日本は西洋から借金でもしなければ、とうてい立ち行かない国だ。それでいて、一等国をもって任じている。そうして、むりにも一等国の仲間入りをしようとする。だから、あらゆる方面に向かって、奥行きをけずって、一等国だけの間口を張っちまった。〔中略〕牛と競争をする蛙と同じことで、もう君、腹が裂けるよ。(『それから』)
「間口」の状況を少し具体的に見てみよう。
1941(昭和16)年、アジア・太平洋戦争開戦時の日本の国民総生産(GNP)は449億円、アメリカの国民総生産は円に換算して5312億円、アメリカの国民総生産は日本の11.83倍である。
ところが、軍事予算は、日本が125億円、アメリカが266億8000万円である。アメリカの軍事予算は日本の2.13倍にとどまり、日米の差が大きく縮小しているのがわかる。これは、日本がアメリカ以上に軍事予算を増大させてきたからである。国家予算に占める軍事予算の割合は、日本が75.57%、アメリカが47.18%だった(『軍備拡張の近代史』)。
さらに、日本がアメリカに先んじて軍備の拡張に力を注いできたことにも、注意を払う必要がある。日中戦争の開戦以降、日本は軍事予算を大幅に増額し軍備の増強に努めてきたのに対し、アメリカの軍事予算が大きく増えるのは、この1941年度予算からだった。この長期にわたる軍拡の結果、日本は、開戦時にはアメリカに匹敵する軍事力を保有していた。 開戦時における日本海軍の戦力は、戦艦・空母・巡洋艦・駆逐艦・潜水艦の合計で、233隻・97万6000トン、アメリカ海軍の戦力は同じく389隻・142万6000トンである。アメリカは太平洋と大西洋の両洋に艦隊を配備しなければならなかったから、太平洋方面では日本海軍がかなり優位となる。
陸軍の兵力では、日本が212万名(航空部隊の兵力を除く)・航空機148個中隊、アメリカが160万名(同右)・航空機200個中隊である。陸上兵力では日本の優位が目立つ(「大東亜戦争の計数的分析」)。
国力が約12倍の国に対して、「腹が裂ける」ほどに軍事力を拡大していることがわかるだろう。そうした無理のある軍拡の結果、漱石の言い方を借りるならば、帝国陸海軍自体も、間口ばかりが立派で、奥行きのない軍隊となった。そのことが兵士にとって、何を意味したのか、という問題を本書では具体的に考えてみたい。
第2には、帝国陸海軍は、将校が温存・優遇される半面で、下士官、そして誰よりも兵士に過重な負担を強いる特質を持っていたのではないか、という問題である。
アジア・太平洋戦争当時、日本の委任統治領だったパラオ諸島のパラオ本島には多数の日本軍が駐屯していた。しかし、アメリカ軍によって制空・制海権を奪われ補給が完全に断たれたため、この島では敗戦までに多数の戦病死者(餓死者)を出すことになる。パラオ本島での戦病死者について分析した作家の澤地久枝は、「兵の死の異様な多さ」に注目し、「日本の軍隊には時代と状況を越え、下士官兵に負荷の重い特性があったのではないかと想像される」と書いている(『ベラウの生と死』)。
ここで軍隊の階級的・権力的秩序について簡単に説明しておきたい。
軍隊というピラミッド型組織の最頂点にいるのが、指揮・命令系統の中核をなす将校である。軍隊全体のいわば管理職と言っていい。中間にあるのが、戦場や兵営で兵士を直接に掌握し、軍隊内秩序に服従させ、戦わせる下士官である。軍隊の言わば中間管理職である。そしてピラミッドの底辺に命令に従うだけの最大多数の兵士がいる。
なお、澤地が「下士官兵」と書いているように、兵士の当時の呼称は、「兵」である。しかし、「兵」、あるいは「下士官兵」という言い方には、将校の側からみた侮蔑的ニュアンスが込められている。そのため、本書では、「兵」を「兵士」と表記することにしたい。
軍隊における将校・下士官・兵士の構成比についても見ておきたい。
敗戦時の陸軍では、全兵員の2.4%が将校、9.2%が准士官・下士官、88.4%が兵士である(『昭和国勢総覧(下)』)。海軍の場合、1943年時点で、全兵員の5.8%が将校、27.9%が准士官・下士官、66.3%が兵士である(『完結 昭和国勢総覧』第3巻)。海軍は陸軍に比べて志願兵が多いため、兵士から進級を重ねた下士官の割合が大きくなる。このピラミッドの頂点から底辺に移動するにつれて、澤地が言うように、負荷がより大きくなるのかどうかを検討してみたい。
この問題は、少し角度を変えて考えれば、「犠牲の不平等」は存在するのか、ということでもある。つまり、軍隊を構成するすべてのメンバーが、おしなべて同じだけの犠牲を引き受けているのか、それとも特定のグループが過重な犠牲を引き受けているのか、という問題である。そのことは、一般の国民が軍隊に編入される時点でも問われなければならない。徴兵制は「国民皆兵」の理念を掲げていたが、兵役の負担ははたして平等だったのだろうか。
戦前の日本社会は極端な学歴社会だった。1935(昭和10)年の時点で見てみると、大学などの高等教育機関に在学している学生が当該年齢人口中に占める割合は、わずか3.0%に過ぎない(『日本の成長と教育』)。同世代の若者のなかの3.0%の若者だけが高等教育機関に進学したのである。大学進学率が50%を超える現代とは異なり、戦前の大学生は、ごく少数のエリートだった。経済的にも恵まれた家庭に育ったこの若者たちも、兵役を平等に担ったのだろうか。そうした問題も検討してみたい。
第3には、兵士の「生活」や「衣食住」を重視するという視点である。軍事ジャーナリストの石渡幸二は、「軍艦の優劣を論ずる場合、必ず引合いに出されるのが攻撃力、防御力、機動力の三要素である」としたうえで、次のように指摘している。
しかし、もう一つ軍艦という兵器体系の持つ大きな特色として忘れてならないのは、それが同時に多数の人間の住家だという点である。何百人という人間が、そこで寝起きし、飯を食べている。いってみれば、軍艦は兵器であると同時に、多数の独身者を収容している一大アパートなのである。〔中略〕したがって、軍艦の設計において、乗員の艦内生活をどうまかなうか、どのような居住施設を設けたらよいかは、非常に大きな課題である。(『艦船夜話』)
つまり、たとえ戦闘本位の軍艦の場合であっても、快適で健康的な一定程度の「生活」や「衣食住」を確保する必要があるという考え方である。そこには、居住性を重視することが、乗員の戦闘意欲をたかめ、その軍艦の戦闘力を全体として強化することにつながるという発想がある。しかし、本書で詳しく分析するように、戦闘第一主義の日本海軍には、「生活」や「衣食住」への配慮はきわめて乏しかった。
同時に、最低限の「生活」や「衣食住」を維持し確保することは、軍隊の正統性の問題にも深くかかわってくる。1944年4月に召集され、高知県で本土決戦のための陣地構築に従事していた真鍋元之は、次のように指摘している。
日本の軍隊は、食費、被服費、住宅費のすべてを、軍側で負担し、兵士からはビタ一文も徴集しない。それのみか、官給以外の物品は《私物》と称し、所持を厳禁している。兵士の生活につき、徹底的に全面保証を与えるのが、日本の軍隊の伝統的な性格であり、この故にこそ軍は、全面的な絶対服従を、兵に要求することが、できているのであった。(『ある日、赤紙が来て』)
ところが、食糧不足に悩まされる兵士の多くが、飢えに駆られて住民から「闇米」を買うようになった。真鍋は、「闇米」の持つ深刻な意味について、「自己の資金で購入した米は、「私物」の食糧である。兵士が私物の食糧で、日常の生活を支えるとき、軍の伝統は、崩壊せざるをえないであろう。なぜなら、私物の食糧は、私物の精神を生み、日本軍のもっとも誇りとする、兵士の絶対服従にヒビが生じるからである」と書いている。「生活」の危機は、まさに軍隊の正統性の危機を意味した。
また、この問題に関しては、作家、深緑野分の発言が重要である。第2次世界大戦で米軍の炊事を担当した特技兵を描いた小説、『戦場のコックたち』を書いた深緑は、「戦争を調べていくと、結局、兵士や市民の生活を保てない国が最終的に負けるとわかってきました。戦争を語るとき、戦闘のことが中心で、生活という視点が抜けがちです」と語っている(『朝日新聞』2023年8月16日付)。
これまでの戦争の語りのなかでは、「生活という視点が抜けがち」だという深緑の指摘は示唆的である。本書では、深緑の指摘も踏まえて、兵士の「生活」や「衣食住」に焦点を合わせて、帝国陸海軍の生態を分析してみたい。
なお、本書では、行論の都合上、『日本軍兵士』で取り上げた若干の論点を再論している場合がある。その場合でも、いくつかの例外をのぞき、『日本軍兵士』刊行後に収集した新たな史料に基づき、叙述するようにした。
(まえがき、著者略歴は『続・日本軍兵士―帝国陸海軍の現実』初版刊行時のものです)
