- 2025 02/05
- まえがき公開
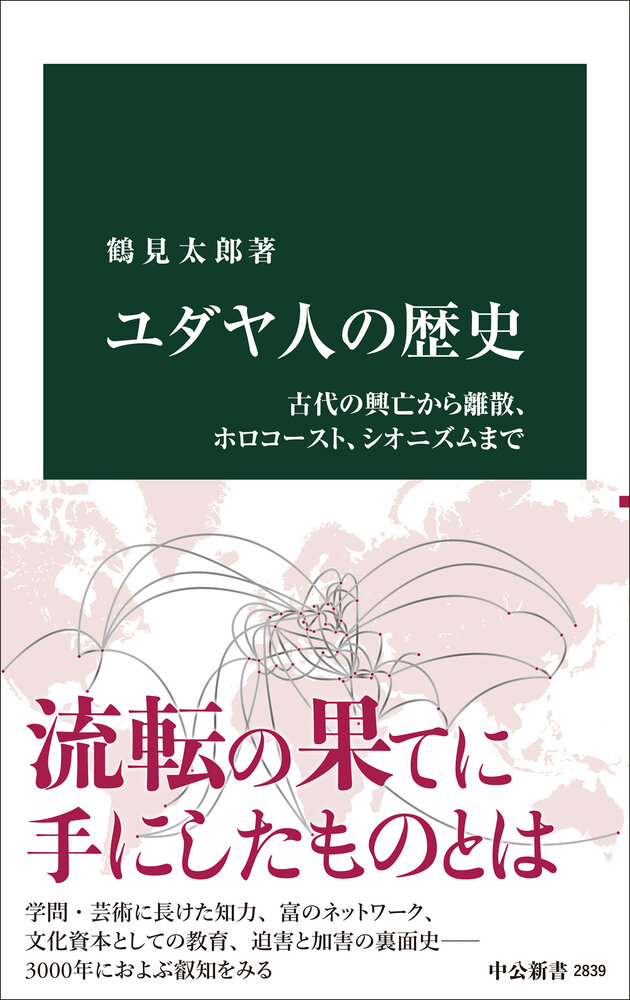
ユダヤ教を信仰する民族・ユダヤ人。学問・芸術に長けた知力、富のネットワーク、ホロコーストに至る迫害、アラブ人への弾圧――。五大陸を流浪した集団は、なぜ世界に影響を与え続けているのか。古代王国建設から民族離散、ペルシア・ローマ・スペイン・オスマン帝国下の繁栄、東欧での迫害、ナチによる絶滅計画、ソ連・アメリカへの適応、イスラエル建国、中東戦争まで。三〇〇〇年のユダヤ史を雄大なスケールで描く。 『ユダヤ人の歴史 古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで』の 「まえがき」を公開します。
まえがき――ある巡り合わせ
ある金曜日の深夜。ニューヨークはブルックリンのボローパーク地区を自転車で移動していると、黒服に黒帽子を身に着けた少年に呼び止められた。家の電灯が云々といっている。今一つ要領を得なかったが、ユダヤ教の規定ゆえに困っているのだろうと思った。
筆者は2012年から14年にかけてニューヨーク大学に研究滞在した際に、ボローパークの南端にあるアパートに住まいを構えていた。その地区のおもな住人は、黒服のユダヤ人、すなわち、伝統的なユダヤ教の戒律を厳格に守る正統派ユダヤ人だ。
ユダヤ教では、金曜日の日没から土曜の日没までが安息日(シャバット)にあたる。安息日とは、「休んでもよい日」ではなく、「休まなくてはならない日」、つまり労働が禁止された日である。しかも、労働と解釈される範囲は思いのほか広い。例えば、火をおこすこと全般が労働と見なされ、意図せずとも結果として火花が散るようなこともしてはならない。そのため、安息日は電気のスイッチを操作することは禁止される。
通りを少しだけ入ったところにある、こぎれいに整頓された家のなかに案内されると、家長と思しき人が迎えてくれた。煌々と明かりが灯ったままの2階の寝室の電灯を消してほしいとのことだった。安息日に入る前に消しておくのを忘れ、このままでは安息日にもかかわらず熟睡できないということなのだろう。
その部屋の電気を消すと、「ありがとう」と任務が完了したことを告げられた。このような任務を行う者は「シャバット・ゴイ」(安息日の異教徒)と呼ばれる。もっとも、安息日に異教徒を労働させることも許されていない。だから、電気を消すのは筆者が気を利かせた形でなければならない。少年の言が要領を得なかったのはそのためだ。
大都市のなかに街区を形成し、独自の伝統規則に沿って暮らしている彼ら正統派ユダヤ人は、21世紀のアメリカ、しかも世界の流行の最先端を行くニューヨークにあって、決して珍しい存在ではない。ブルックリンを中心に、黒服のユダヤ人街は複数存在し、出生率の高さもあり、規模が衰えることはない。英語が支配的ではあるものの、彼らの先祖である東欧ユダヤ人が話していたイディッシュ語はいまも使われる。
現代社会の最先端を横目に淡々と伝統を墨守するこのギャップにこそ、ユダヤ人の生き方の真骨頂がある。居住国と折り合いをつけながら、自らの原則は貫く。そのことが仲間内の信頼につながり、ネットワークが維持されていく。重要なのは、状況に自分を合わせるということでは必ずしもないことだ。むしろ自らの特性とうまく組み合わさるところに入っていき、多少は周囲との関係で自らを「カスタマイズ」しつつも、自らの特性を維持することが周りのメリットにもなり、そのことで自らの居場所がさらに安定化するという好循環を目指すのだ。金融業で成功し、富豪として西洋社会に存在感を持つユダヤ人の存在も、こうした視点から読み解くことができる。
むろんこうした戦略がつねに成功するわけではない。例えば、悪い巡り合わせが重なった先にホロコーストがあったのも事実だ。さらにその先に「ユダヤ人国家」として建国されたイスラエルは、組み合わせなどお構いなしに武力行使を重ね、孤立を深めているように見える。
ただ、それもまた、さまざまな条件が歴史のなかで組み合わさった結果であることが本書から明らかになるだろう。何と組み合わさり、ユダヤ人自身も「カスタマイズ」していくのか。そこに注目して読み進めてほしい。
本書は、世界史やユダヤ教に関する予備知識なしでも通読できるように書かれている。また、世界史を今まさに学んでいる高校生や世界史を復習したい読者にもなじみやすいように、高等学校の世界史探究(旧「世界史B」におおむね相当)の教科書にできるだけ準拠した。ユダヤ人が教科書にほとんど登場しない中世から近代までの時期にも、世界史の何と組み合わさりながらユダヤ人の歴史が展開していったのかが読み取れるようになっている。
(まえがき、著者略歴は『ユダヤ人の歴史』初版刊行時のものです)
