- 2024 12/24
- まえがき公開
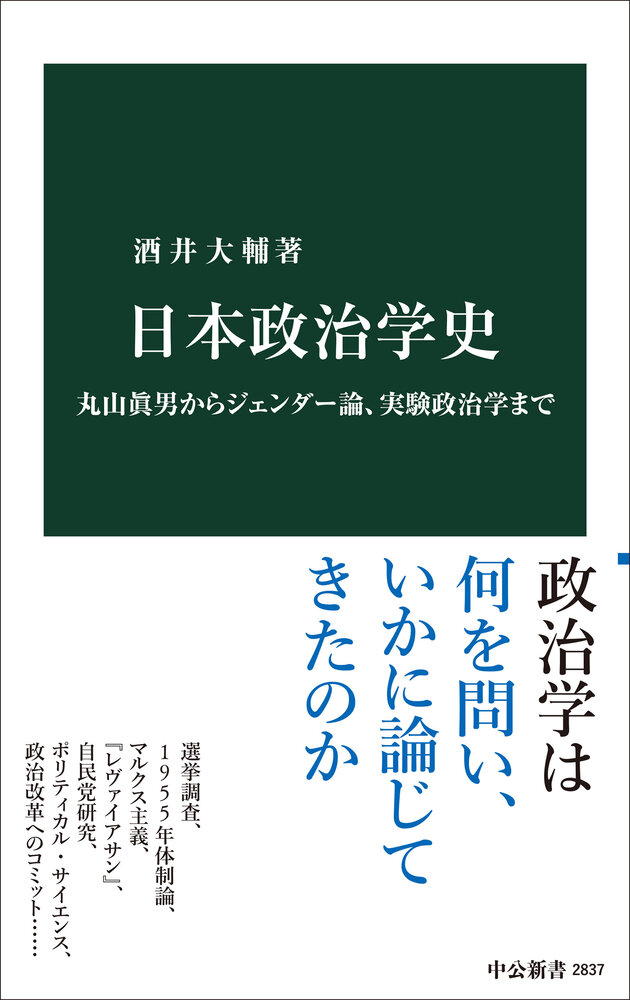
「科学としての政治学」は、どのような道み程をたどったのか――。本書は、戦後に学会を創り、行動論やマルクス主義の成果を摂取した政治学が、先進国化する日本でいかに変貌してきたのかを描く。丸山眞男、升味準之輔、京極純一、レヴァイアサン・グループ、佐藤誠三郎、佐々木毅などの業績に光を当て、さらにジェンダー研究、実験政治学といった新たに生まれた潮流も追う。欧米とは異なる軌跡を照らし、その見取り図を示す。 『日本政治学史 丸山眞男からジェンダー論、実験政治学まで』の 「まえがき」を公開します。
まえがき――科学としての政治学の百年
ひと頃まで、日本の政治学の歴史は、その語られなさが嘆かれてきた。日本で最も引用された政治学者の丸山眞男(1914~96)は、1980年秋の晴れた日、1400人の聴衆で満員となった早稲田大学大隈講堂で登壇し、こう発言している。
私の感想としては、近代日本について広い意味の思想史というものについては非常に多くの研究がなされ、また、優れた研究もございますけれど、近代日本の学問の歴史ということについて、特に社会科学については著しく未開拓ではないか、という感じが強いのであります。(略)今日の政治学の、あるいは今後の政治学の発展にしましても、およそ学問というものは、過去の蓄積の積み重ねの上になされるという本来の性質を持っておりますのに、学問史――近代日本の社会科学の歴史というもの――の研究が本当になされていないことは、大変遺憾なことではないか。(丸山二〇〇八)
この日の講演会は、大正期に活躍した政治学者・大山郁夫(1880~1955)の生誕百年記念会だった。丸山は、大山の業績が「あまりに注目されなさすぎる」現状に触れ、経済学を除く日本の学問史、とりわけ政治学史の研究の不振を訴えたのである。当時、日本の政治学史といえば、蠟山政道(1895~1980)の1949年の著書『日本における近代政治学の発達』があるのみだった。
なぜ日本の政治学史の語りは低調なのか。丸山は言う。「これにはいろいろな理由があると思います。非常に通俗的に申せば、私共の風土に非常に根強い最新流行主義――いつも最新の流行のモードを追っかけている、外国に新しい学説が出るとパッとそれを紹介する」。「過去の蓄積の上に新しいものを創造していく」姿勢が乏しく、そのことが、「日本の、狭く言えば学問、広く言えば文化の底の浅さをなしている」という。輸入学問批判に通じる議論といえよう。これ自体が、政治学史の構造について一つの理解を示している。
丸山はかねて同様の主張を表明してきた。早くも47年の論考「科学としての政治学」では、「ヨーロッパの学界でのときどきの主題や方法を絶えず追いかけているのが、わが学界一般の通有する傾向」と述べた。61年の『日本の思想』では、さらに「思想が対決と蓄積の上に歴史的に構造化されない」ことが日本の伝統とされ、その一端を担うのが「輸入取次業」にいそしむ日本の学界とされた。
だとすれば問題の根は深い。学問でさえ、思想や議論が蓄積されない日本文化のパターンの例外でないというのだ。研究業績が次の探究の踏み台となり、次々と知見が積み重なることが学問の本質だとすれば、日本の政治学はその逸脱として理解され、真の発達はないことになる。自国の学問の発展史に強い関心が生まれるはずがない。
しかし、本当にそうだろうか。冒頭の丸山の発言から40年以上が経過し、その間、日本の政治学史を主題とする著作も書かれるようになった。今では、過去の政治学者たちが単なる「輸入取次業」だったとは考えられていない。海外の動向や日本の現実を前にして、政治学者たちがどのような知的営為を展開したのか、個別に検討する段階に入っている。本書は、個々の政治学者にスポットをあて、日本の「科学としての政治学」がどのような軌跡を経て現在に至ったのか、その歴史を辿るものである。
本書はおよそ10年ごとに叙述を進める。序章では学史方法論を述べ、戦後政治学のアウトラインを押さえた上で、政治学者の指針となった丸山眞男の論考を学史的に読んでみたい。
第1章は、戦後から1954年頃まで、民主主義と再建と逆コースの危機の中、科学を追い求めた研究者たちを扱う。人びとの政治意識を調査した蠟山政道、日本政治学会の創設とともに共同研究を行った岡義武のグループの軌跡を追う。
第2章では、55年頃から米国の行動科学にインパクトを受けて日本政治研究に着手した代表的学者として、石田雄、升味準之輔、京極純一の業績を取り上げる。
第3章は、60年代後半から始まる停滞期の中、従来とは異質な潮流を主題とする。焦点があたるのは田口富久治のマルクス主義と三宅一郎の投票行動研究である。
第4章では、80年代に台頭した政治学の「新しい流れ」を中心に、従来の政治学との対立と連続の様相を見たい。雑誌『レヴァイアサン』に集った大嶽秀夫、村松岐夫、猪口孝や、自民党の助言者として行動した佐藤誠三郎がその中心になる。
第5章では、80年代後半から90年代の政治改革の気運の中、政治改革推進協議会(いわゆる民間政治臨調)など選挙制度改革に取り組んだ人々、そして科学の方法を刷新した新制度論の登場した意味を考える。
第6章は、2000年代から現在であり、政治学の発展と再構成の試みとして、ジェンダー研究と実験政治学を紹介したい。
終章は政治学者を対象とした二つの調査を取り上げ、政治学の目的などに関する考え方の変化を確認した上で、本書の議論をまとめる。
学史はたんなる回顧ではない。政治学が「社会の自己反省装置」(宇野二〇一一)であるとすれば、その歴史は、私たちの社会が適切な反省の手がかりを手にしてきたかの検討素材となる。戦後政治学の読み直しはその豊かな可能性を提供するはずだ。
(はじめに、著者略歴は『日本政治学史』初版刊行時のものです)
