- 2020 11/13
- 著者に聞く
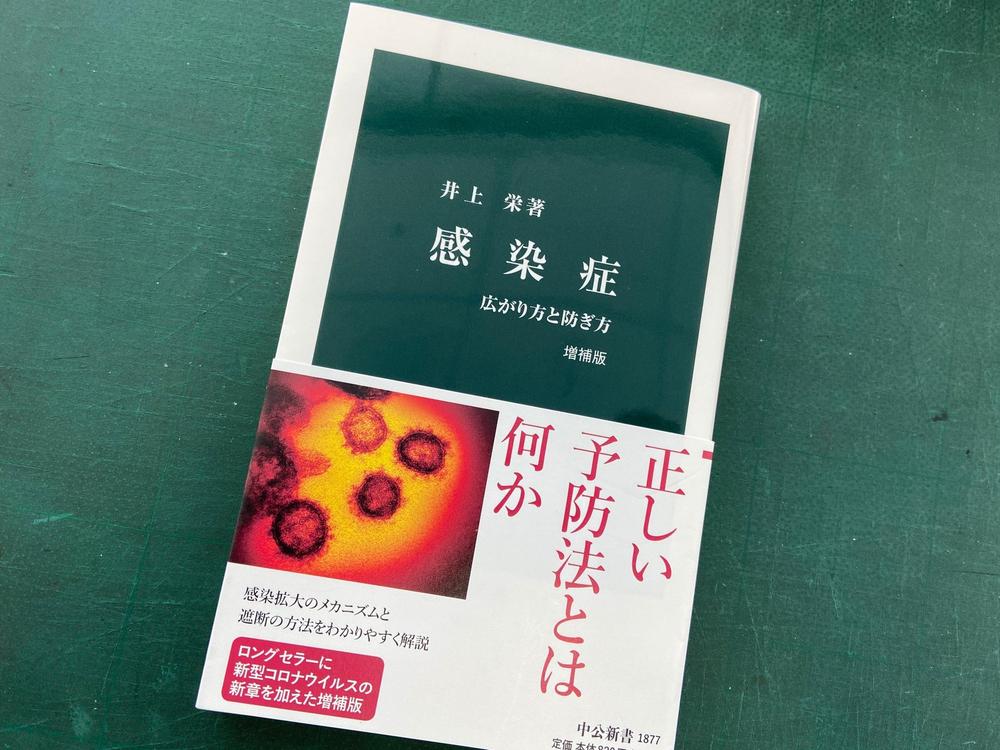
WHOが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを宣言したのが2020年3月11日。そして安倍晋三前首相が緊急事態宣言を発出したのが4月7日のことである。『感染症 増補版』は、その約二週間後に刊行された。コレラから新型インフルエンザまで、感染症の基礎をわかりやすく解説した底本に、COVID-19の特徴や予防法の考察をいち早く加えた本書は話題を呼び、6万部を超えるベストセラーとなった。刊行から半年、その後のCOVID-19をめぐる日本や世界の状況を、著者の井上栄さんはどう見ていたのか。編集部でお話をうかがった。
――『感染症』の初版が2006年12月刊行、その増補版の刊行が2020年4月です。まずは初版の執筆経緯からお聞かせいただけますか。
井上: 2003年、SARS(重症急性呼吸器症候群)が世界に広がったとき、日本人の患者はゼロでした。当時、それは「偶然の幸運」とする意見ばかりでしたが、「偶然」と言ったのではそこで思考停止です。証明できなくても徹底的に「日本人患者ゼロ」の理由を考えておくことが必要と考えました。
2003年にオックスフォード大学出版局から出た、十九世紀の英国人医師ジョン・スノウの評伝を読んで、彼の業績の真の意義を知ったこともあります。彼は細菌学誕生前の時代の人ですが、論理的にコレラ病原体の存在を仮定し、その伝播経路を疫学的に証明し、コレラ対策に貢献したのです。余談ですが、その本を2019年に翻訳出版しました(著者略歴欄参照)。
初版では、各感染症の伝播経路を論理的に考えて、日本人の日常生活のなかに無意識的に病原体伝播を抑える文化が組み込まれていることを強調しました。議論を呼んだ「日本語が飛沫を飛ばしにくい発音である」という仮説は、横浜国立大学の矢吹晋教授との会話の中で出てきた説です。のちに発話での瞬間風圧を測定し、日本語で英語・中国語より低いことを確かめ2015年に論文発表しました。
――この本を書くまでの井上先生のご研究、お仕事についてもお聞かせください。
井上: 私が医学生だった時代には、カリキュラムにウイルス病についての講義が入っていませんでした。これはおかしいと思い、国立予防衛生研究所(予研、現・感染研)の大谷明先生のところへ行って、ウイルスを扱わせてもらいました。大学院修了後に予研ウイルス中央検査部に就職して、ウイルス病の診断技術の開発などに関わったのち、1980年代半ばに国立公衆衛生院に移りました。
当時、慢性肝炎やエイズを除く急性感染のウイルス病の患者は、ワクチンの普及でどんどん減っていました。それに反比例するような形で、スギ花粉症患者が急増していたことに興味を持ち、多数の血清検体中のスギ特異的IgE抗体を測定する方法を確立して、地域別・年齢別の花粉症発生状況を抗体保有から明らかにしました(花粉症の血清疫学調査)。
1996年、堺市でO157大腸菌による大規模集団発生があって、感染症突発事態に対処するための体制が日本に無いことが明白になりました。1992年に予研に戻っていた私は、米国CDC(疾病対策センター)にあるEIS(疫病調査部)のような部署、すなわち現地で迅速な疫学調査を行うプロを養成するための研修コースを創設すべきと考え、外国人専門家の招聘費用と研修員の給与のための予算を要求しました。研修期間は2年間で、2年生が1年生を指導して調査を行う、つまり仕事の中で研修 (on-the-job training) を行うのです。そのような研修員に国が給与を出すのが世界の標準です。
私が定年退職となる前年の1999年に、「実地疫学専門家養成コース(Japan Field Epidemiology Training Program)」が開始されました。はじめは研修員への給与が認められなかったのですが、やっと2017年になって認められるようになります。メディアではあまり報道されませんでしたが、上記コースの研修生および卒業生は2020年に「クラスター対策班」として活躍しました。
――増補版はCOVID-19の広がりを受けて、急遽制作されたものです。初版と増補版で反響に違いはありましたか。
井上: 2009年には新型インフルエンザの世界的流行がありましたが、日本では治療薬タミフルを病初期から使ったこともあり、死者数も少なくて収束しました。それに比べて、新型コロナはまったく違います。治療薬・予防ワクチンもなく、インフルエンザよりも重症傾向で、世界中を震撼させ、国民の生活を揺るがせています。増補版刊行の反響も大きく、いくつかの新聞社などからインタビューを受けました。
――コロナ禍で叫ばれたマスクの着用や手洗いといった基本的対策の重要性は、本書の初版ですでに力説されていましたね。“増補版へのあとがき”では、希望を込めて、「新型コロナウイルスが世界中に広がるなかで、日本人はコロナ危機をうまく乗り切るのではないだろうか」とも書かれています。その後の半年間、日本の状況をどのように見ていましたか。
井上:人口当たりのコロナ死者数が欧米の数十分の一という少なさは驚くべきことです。その理由としてさまざまな仮説がありますが、私は日本人特有の行動様式が大きく関係していると考えています。「同調圧力」ともいわれますが、国民はマスクを一斉に着用し、強制力無しで行動を自粛しました。
――刊行後に明らかになったCOVID-19の研究結果で、印象的なものがあれば教えてください。
井上:無症状の感染者が喋ることで出るエアロゾルが感染を広げることが分かってきました。感染者も周りの人も感染に気付かないで感染が広がるわけで、たいへん厄介なことです。感染者が多くなれば、感染者の一部を占める重症者の数も増えることになります。
エアロゾルは飛沫より小さい粒子で、空中ですぐに乾燥して浮遊するもので、主として声帯の振動で母音を発音するときに発生し、大声を出すほど発生量も多い。今までエアロゾルで広がる感染症はほとんど知られていませんでした。エアロゾル中のウイルスは、声帯より下の下気道や肺の細胞で殖えたものです(鼻風邪ウイルスでは、上気道だけで増殖するのでウイルスはエアロゾルに入りません)。
しかしマスクは、吹き出るエアロゾル量、ウイルス量を減らします(末尾の文献1、2を参照)。空気を吸い込むときは微小なエアロゾルはマスクを通過するのですが、マスクで吸入風速は低下するので、下気道から肺へ入るエアロゾル量も減ると考えられます。今、マスク着用習慣が無かった欧米でも、日本などを見倣ってマスクが広がりつつあります。
――2020年10月末現在、第二波に苦しめられるヨーロッパ、200日連続新規感染者なしの台湾、ウィズコロナの経済活動が推進される日本など、世界各地で状況は様々です。来たる2021年、私たちはCOVID-19とどう向き合っていくべきでしょうか。
井上: 国民全員がウイルスを広げないように行動をすることです。伝播経路を知って論理的に意識して行動する。そうすればウイルスが弱毒化する可能性があります。すなわち、対人距離をとり、マスクをして、密閉・密集の空間で大声を出す機会を避けることです。ちなみに日本語は(音節が母音で終わる)開口音節語なので、大声で歌う場合には、英語(閉口音節語)の歌よりエアロゾル発生量は多いと考えられます。
一般的に呼吸器に感染するウイルスは冬季に広がるのですが、その理由として、次の三点が挙げられます。
① 低温・低湿の環境中でウイルス構造が安定化する
② 冬季には人々は換気が悪い屋内にとどまるのでウイルス伝播も起こりやすくなる
③ 人体の気道内も乾燥し温度が低下するので、気道上皮細胞の繊毛の動き(吸気に含まれるゴミの排除)が悪くなる
コロナウイルスは①に該当します。マスクは③を改善するように働きます。
ウイルス感染後の免疫応答(液性免疫〔血中抗体〕と細胞性免疫〔リンパ球〕)も少しずつ分かってきましたが、まだ不明な点が多いです。人によってはウイルスが免疫抑制を起こすようで、免疫の持続が短くて再感染が起こった例も報告されています。新型コロナは急性の全身性ウイルス感染症で、このような感染症に対してはワクチンがきわめて有効です。生きたウイルスが免疫抑制を起こしても、不活化ワクチンならば免疫を付けると考えられます。ワクチンが出来るまでは、とくに今冬季はじっと我慢ですね。
国は、国民の免疫状況の変化を調べるためにIgG抗体測定の血清疫学調査を半年ごとに行うようです。また、ウイルス遺伝子に変異(核酸塩基の変化)が起こったかどうかをモニターしています。長期的には、実地疫学専門家養成コースの研修生を増やし、その卒業生が国・都道府県の感染症対策部署に就職して活動するようにしてもらいたいです。
――コロナ禍で、感染症研究が注目される機会が増えました。最後に、これから研究の道を志す若い読者にメッセージがあればお願いします。
井上:感染症対策には、広い分野での研究結果を総合して判断することが必要です。新興の感染症を引き起こす病原体は、野生動物が持つウイルスが遺伝子変異を起こしてヒトで増殖するようになったものが多いです。病原体そのものや宿主の免疫についての実験室での基礎研究、屋外環境中での病原体の生態学、社会の中での疫学などが必須です。若い人はまず実験室でウイルス学、細菌学、免疫学などの基礎技術を学んだうえで、実験室での研究を続ける人と、実験室を出て臨床医学、生態学、疫学・公衆衛生などの分野へ行く人に分かれるのがいいでしょう。
――ありがとうございました。
《参考文献》
文献1 Asadi S et al: https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7
文献2 Ueki H et al: https://msphere.asm.org/content/5/5/e00637-20.full
