- 2018 01/17
- 編集部だより
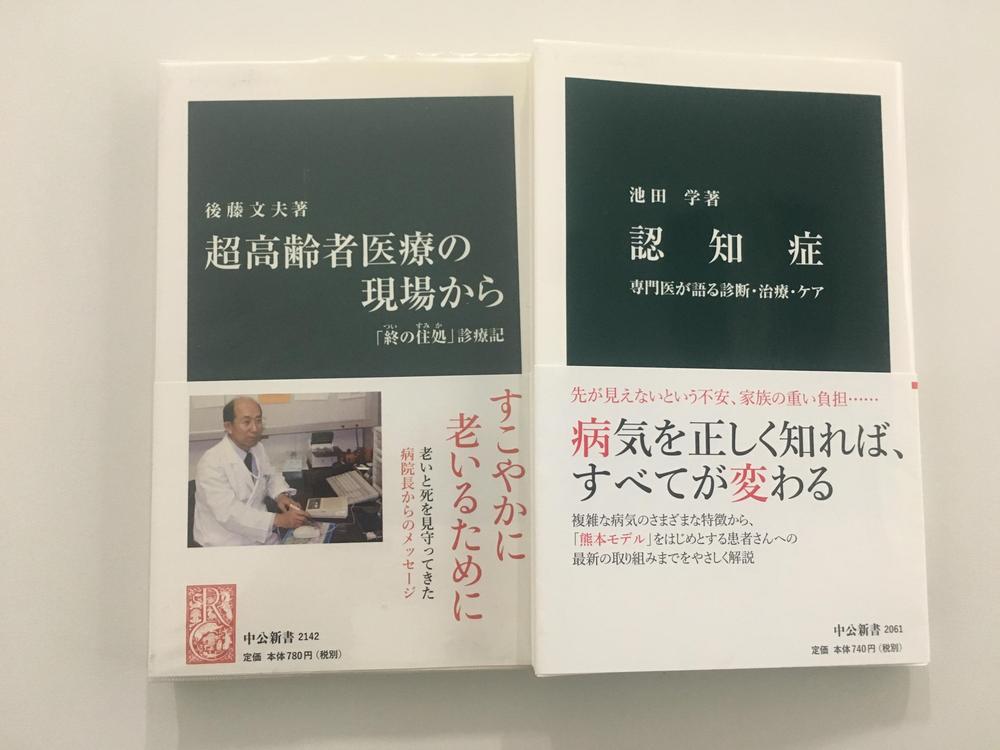
「もう私のことも誰だかわからないのよ」「こないだは、『お前は誰だ。何で私の家に居るんだ』と言うの」。母が電話口で父について話す。
父は88歳。認知症を患って10年以上経つ。この10年間で記憶したことは孫が生まれたことくらいだ。その孫も最近は「お前は誰だ」と言われ、泣いていた。
7年前にその生家に妻子とともに越したことがあった。引っ越して1週間後、封をしたままのダンボール箱に「焼却処分」といった札が付けられ、僕の靴のなかに手紙が入っていた。「恥知らずめ。離婚して戻って来るとは......」。息子をなじる文字が綴られていた。中学校の国語教師だった父の字は端正だ。論語の一節も添えられている。だが妻も一緒に住んでいることを理解していない。
早く帰宅し父と向き合った。「靴の中の手紙についてだけれど」と話すと、「え、何だ......」と記憶にない。母が隣にやってきて「だからお父さん、わかっていないのよ。認知症なの」と囁く。その声が聞こえたのか、「な、何だ、お前ら」と激怒する。同居するまでは父が認知症であるという母の話に懐疑的だった。だがこの日、一瞬にして理解した。
その晩、0時を回った頃、自室で仕事をしてると父がやってきた。バン! とドアが勢いよく開く。「何でお前がこの家に居るんだ」と父が掴み掛かってきた。
主治医は父の甥、つまり僕の従兄弟だ。「オヤジがこんな手紙を書いてきて、記憶があったりなかったりで。昨晩は襲いかかってきてさ」と話す。「お前の字より、圧倒的にうまいな」と従兄弟は笑いながら、そして急に真顔になり、「早く引っ越せ。お前だけでなく、そのうち嫁さんや子どもに何かあるかもしれない」と言う。
1週間後に近隣のマンションに引っ越した。20日間とはいえ僕らが一緒に住んでいた記憶は父にはもちろんない。
この正月、60代半ばから40歳の従兄弟たちが集まる。会話は認知症が絡んだ親の介護の話ばかり。昨年、90代後半の伯母を見送った最年長の従兄弟が、「お前らがこれからは地獄だぞ」と話す。「うちは小学生の子どもが病気がちで。介護はおふくろ頼みだけれど......」と僕が話すと、「子どもを優先しなきゃ」と言われる。元気とはいえ80歳になった母の負担は重い。さりとて同居も厳しい。
尊敬していた父だった。物静かで、時間があると本を読み、僕を叱るときも正座をさせ静かに諭すだけだった。手を上げられたことは一度もない。ここ10年の豹変は驚くばかりだが、それが現実である。どうなっていくのだろうか。
2012年段階で462万人いるとされる日本の認知症患者。25年には700万人にのぼると推計されている。フィンランド1国の人口、550万人(2016年)を越えることになる。身近に患者がいるだけに、この社会はどうなっていくのかと思う。人類が新しい段階に向かっているのではとも、思えてしまう。(白)
