ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10808件中 10710~10725件表示
-
中公新書
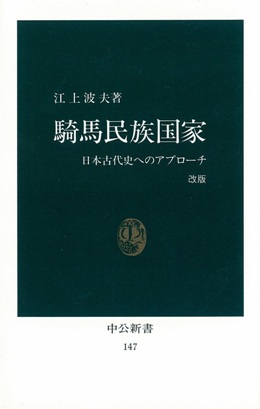
騎馬民族国家 改版
日本古代史へのアプローチ
江上波夫 著
日本国家と日本民族の起源は東北アジア騎馬民族の日本征服にあるという説にたつ著者が、大陸と古代日本との比較・対照によって、その社会・政治・軍事・文化などのそれぞれの面で具体的に符合することを証明する。第1部では、騎馬民族であるスキタイ・匈奴・突厥・鮮卑・烏桓などの興亡の歴史とその特質を描き、第2部では日本における征服王朝をとりあげて、大陸騎馬民族との比較研究を綿密に行なう。毎日出版文化賞受賞。
1991/11/30 刊行
-
中公文庫
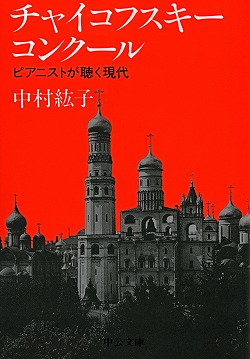
チャイコフスキー・コンクール
ピアニストが聴く現代
中村紘子 著
世界的コンクールの舞台裏を描き、国際化時代のクラシック音楽の現状と未来を鮮やかに洞察する長篇エッセイ。大宅壮一賞受賞作。〈解説〉吉田秀和
1991/11/10 刊行
-
中公新書
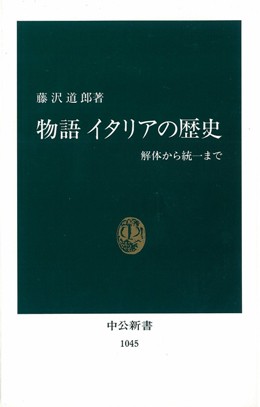
物語 イタリアの歴史
解体から統一まで
藤沢道郎 著
皇女ガラ・プラキディア、女伯マティルデ、聖者フランチェスコ、皇帝フェデリーコ、作家ボッカチオ、銀行家コジモ・デ・メディチ、彫刻家ミケランジェロ、国王ヴィットリオ・アメデーオ、司書カサノーヴァ、作曲家ヴェルディの十人を通して、ローマ帝国の軍隊が武装した西ゴート族の難民に圧倒される四世紀末から、イタリア統一が成就して王国創立宣言が国民議会で採択される十九世紀末までの千五百年の「歴史=物語」を描く。
1991/10/25 刊行
-
中公新書

物語 アメリカの歴史
超大国の行方
猿谷要 著
アメリカは民主主義の理念を具体的に政治に実現させた最初の国である。独立宣言(一七七六年)の中心「すべての人間は生まれながらにして平等である」は、今なお民主主義国家の道標として輝き続けているものの、人種間の問題や戦争など、建国から二百年余、その歴史は平坦ではなく、生々しい傷がまだ癒えることなくその跡をとどめている。この超大国の光と影を、戦後深いつながりをもって歩んできた日本との関係もまじえて描く。
1991/10/25 刊行
-
中公文庫
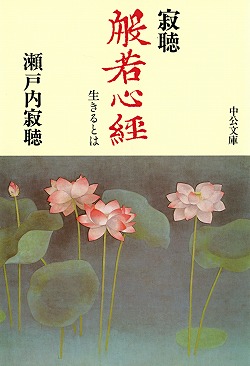
寂聴 般若心経
生きるとは
瀬戸内寂聴 著
仏の教えを二六六文字に凝縮した「般若心経」の神髄を自らの半生と重ね合せて説き明かし、生きてゆく心の拠り所をやさしく語りかける、最良の仏教入門。
1991/10/10 刊行
-
中公文庫
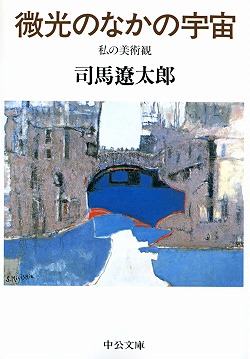
微光のなかの宇宙
私の美術観
司馬遼太郎 著
密教美術、空海、八大山人、ゴッホ、須田国太郎、八木一夫、三岸節子、須田剋太――独自の世界形成に至る軌跡とその魅力を綴った珠玉の美術随想集。
1991/10/10 刊行
-
中公文庫
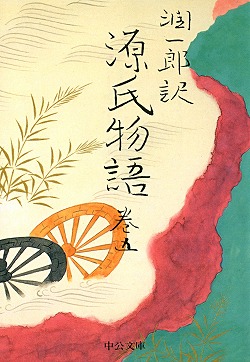
潤一郎訳
源氏物語
巻五
谷崎潤一郎 訳
文豪谷崎の流麗完璧な現代語訳による日本の誇る古典。日本画壇の巨匠14人による挿画入り絵巻。本巻は「早蕨」から「夢浮橋」までを収録。〈解説〉池田彌三郎
1991/10/10 刊行
-
中公新書
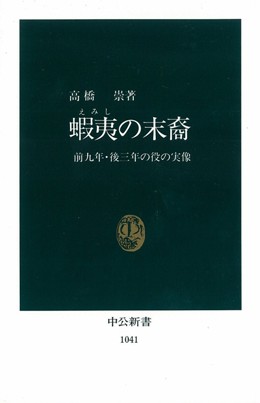
蝦夷の末裔
前九年・後三年の役の実像
高橋崇 著
平安時代中期、陸奥の北上川中流域を席巻していた安倍氏と、出羽の山北地方一帯を押さえていた清原氏は、その勢力が最大に拡張したとき、国家権力の介入を招いて滅亡の災禍に見舞われる。前九年の役、後三年の役の両合戦である。古代東北史を語る上で不可欠の大事件にも拘わらず、顛末を伝える史料に乏しく、検証も疎かにされてきた両合戦の実像を、厳密な史料批判のもと再検討し、蝦夷の末裔である安倍・清原両氏の興亡を描く。
1991/09/25 刊行
-
中公文庫
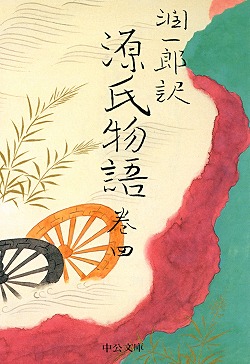
潤一郎訳
源氏物語
巻四
谷崎潤一郎 訳
文豪谷崎の流麗完璧な現代語訳による日本の誇る古典。日本画壇の巨匠14人による挿画入り絵巻。本巻は「柏木」より「総角」までを収録。〈解説〉池田彌三郎
1991/09/10 刊行
-
中公文庫
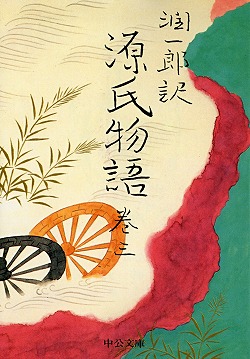
潤一郎訳
源氏物語
巻三
谷崎潤一郎 訳
文豪谷崎の流麗完璧な現代語訳による日本の誇る古典。日本画壇の巨匠14人による挿画入り絵巻。本巻は「螢」より「若菜」までを収録。〈解説〉池田彌三郎
1991/08/10 刊行
-
中公文庫
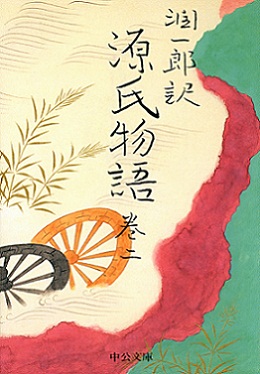
潤一郎訳
源氏物語
巻二
谷崎潤一郎 訳
文豪谷崎の流麗完璧な現代語訳による日本の誇る古典。日本画壇の巨匠14人による挿画入り。本巻は「須磨」より「胡蝶」までを収録。〈解説〉池田彌三郎
1991/07/10 刊行
-
中公文庫
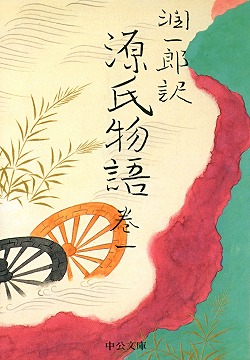
潤一郎訳
源氏物語
巻一
谷崎潤一郎 訳
文豪谷崎の流麗完璧な現代語訳による日本の誇る古典。日本画壇の巨匠14人による挿画入り絵巻。本巻は「桐壺」より「花散里」までを収録。〈解説〉池田彌三郎
1991/07/10 刊行
-
中公文庫
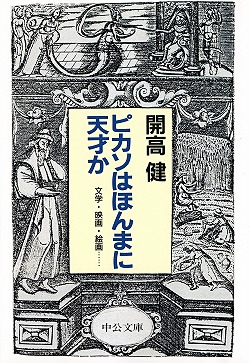
ピカソはほんまに天才か
文学・映画・絵画…
開高健 著
ポスター、映画、コマーシャル・フィルム、そして絵画。開高健が一つの時代の類いまれな眼であったことを痛感させるエッセイ42篇。〈解説〉谷沢永一
1991/06/10 刊行
-
中公文庫
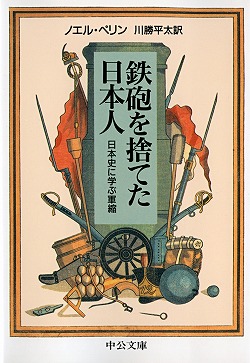
鉄砲を捨てた日本人
日本史に学ぶ軍縮
ノエル・ペリン 著 川勝平太 訳
十六世紀後半の日本は西欧のいかなる国にもまさって鉄砲の生産・使用国であったにも拘わらず、江戸時代を通じて刀剣の世界に舞い戻ったのはなぜか。
1991/04/10 刊行
-
中公新書

トルコのもう一つの顔
小島剛一 著
言語学者である著者はトルコ共和国を一九七〇年に訪れて以来、その地の人々と諸言語の魅力にとりつかれ、十数年にわたり一年の半分をトルコでの野外調査に費す日々が続いた。調査中に見舞われた災難に、進んで救いの手をさしのべ、言葉や歌を教えてくれた村人たち。辺境にあって歳月を越えてひそやかに生き続ける「言葉」とその守り手への愛をこめて綴る、とかく情報不足になりがちなトルコという国での得がたい体験の記録である。
1991/02/25 刊行







