ホーム > 検索結果
発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧
全10808件中 10215~10230件表示
-
中公クラシックス
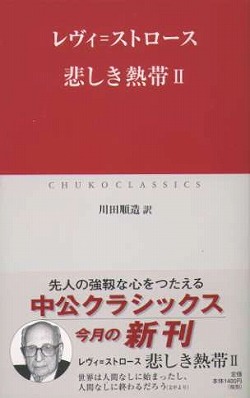
悲しき熱帯Ⅱ
クロード・レヴィ=ストロース 著 川田順造 訳
現存するもっとも偉大な人文学者レヴィ=ストロースのもっとも代表的な著作、それが本書である。Ⅱは、ブラジルの現地調査で得た民族誌的知見があますところなく盛りこまれている。
2001/05/10 刊行
-
電子書籍
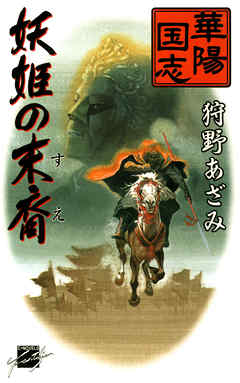
華陽国志1
妖姫の末裔
狩野あざみ 著
大陸統一を目指す強国秦の膨張は、小国ひしめく戦国の均衡を根底から突き崩そうとしていた。歴史の歯車が回り始めた激動の世。秦の侵攻に脅かされる山間の小国蜀の華陽に生を受けた3人の公子が、時の流れに翻弄されながら、新しい時代を夢見て鮮やかに生き抜いていく様を華麗に綴る中国歴史ロマン。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
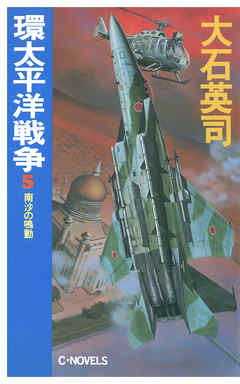
環太平洋戦争5
南沙の鳴動
大石英司 著
アジアでもっとも富裕な産油国ブルネイで奇妙なクーデターが勃発。民主化を訴える王女がムスリム勢力やグルカ兵を実行部隊にして王政を転覆したのだ。国連は直ちに現状回復を決議、自衛隊を平和創設軍(PMF)として派兵する。歪んだ王政に正義はないが、放置すればテロリズムの温床と化すのは明白だった。だがグルカ兵の巧妙なゲリラ戦術に自衛隊の犠牲が続出、事態は泥沼の様相を。燃え盛るアジアの戦火。背後で暗躍するCIA。地域安全保障の代償に苦悩する常任理事国日本の選択シミュレーション。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
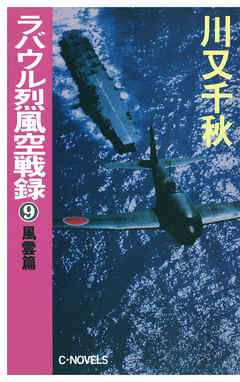
ラバウル烈風空戦録9
風雲篇
川又千秋 著
最高速度650キロ、2000馬力の発動機、20ミリ機関銃4挺、零戦をしのぐ旋回性能をもたらす自動空戦フラップ……待望の新型艦上戦闘機「烈風」がその姿を現した。しかも、同じく新鋭の艦爆「彗星」、艦攻「天山」とともに、シンガポールで鹵獲した元英空母「剛龍」を母艦とする、我が海軍最強の航空隊が編成されたのだ。そして、装甲空母と高性能艦載機で猛訓練を重ねる主人公らに出撃命令が下る。めざすは北太平洋の某海域!
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
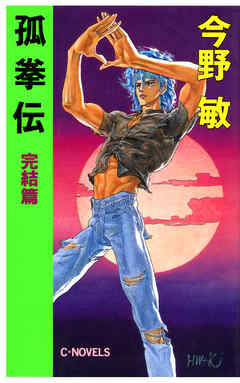
孤拳伝
完結篇
今野敏 著
戦うために生きている血に飢えた狼のような男、朝丘剛。香港の魔窟・九龍城に育ち、日本で母の仇を討った少年は、暴力団主催の闇試合を始め、凄惨な戦いに明け暮れる日々を送った。強い相手を求めて放浪する剛は、沖縄で出会った屋良照順老人のもとで訓練を積むと、これまでに自分が勝てなかった相手──由佐肇、劉栄徳に再び戦いを挑むため沖縄を後にする。剛は「本当の強さ」を見つけ、横浜で待つマリアを抱きしめることができるのか。感動のクライマックス!
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
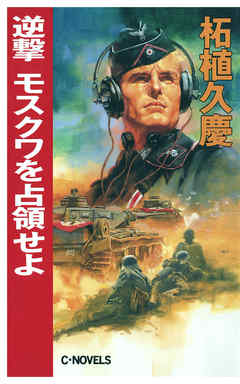
逆撃 モスクワを占領せよ
柘植久慶 著
フォン=タンネンベルクこと現代人軍師・御厨太郎は、ヒトラーの信頼を得、グーデリアン大将の機甲部隊に参加した。史実を知る御厨の作戦により、部隊は快進撃を続け、ついにイギリスを占領する。ヒトラーの次の狙いは、ロシアだ。冬将軍に敗れた現実のバルバロッサ作戦を踏まえ、開戦日を早めた電撃戦を立案する御厨の前に、物資補給、泥濘地、T-34戦車、そしてタイムリミットの難題が立ちふさがる──。独軍はモスクワに到達できるか!? ドイツ篇第3弾!
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
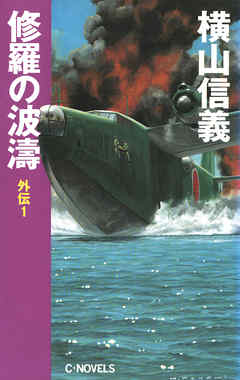
修羅の波濤 外伝1
横山信義 著
二式大挺に刻まれた桜のマークは、生還への希望──死闘が繰り返される中部太平洋最前線グアム島。そこに撃墜機搭乗員の救援活動に専念する部隊があった。二等飛行兵新見正樹は偵察員としての初仕事で見事な成果を挙げるのだが……。裏方に徹し、多大な功績を挙げた907空5号機。その始末記を少年兵の成長と重ね合わせた「生命は我が戦果」。他に「カムヒア、ミッキーマウス」「蒼海の牙」の2編。最前線の将兵たちの視点で見つめ直す「修羅の波濤」世界!
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
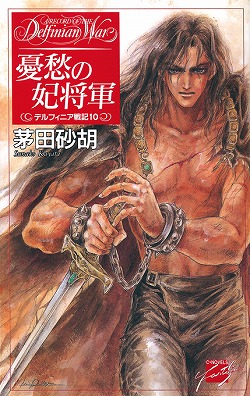
憂愁の妃将軍
デルフィニア戦記10
茅田砂胡 著
徒党を組んで反旗を翻したグラハム卿ら西部領主との決戦に、国王ウォルの軍は大敗を喫した。頼みのラモナ騎士団は壊滅し、ウォルは囚われの身に……。さらにパラスト・タンガの2国はこの機に乗じて同盟を結び、虎視眈々とタウ山脈の金銀鉱を狙う。内憂外患のデルフィニアの危地に、姿を消した王妃リィの真意は。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
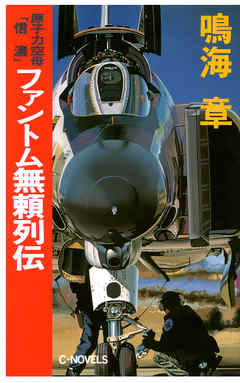
原子力空母「信濃」
ファントム無頼列伝
鳴海章 著
原子力空母「信濃」の搭載機F-4Jファントム改。「幽霊」の名に相応しいふてぶてしい面構えをした歴戦の名機も、新鋭機に比すればその設計の古さは否めない。だが大空へひとたび舞い上がれば、パイロットの技量がすべてを決めるのだ。F-15イーグル、F-16ファイティング・ファルコン、スホーイ27──基本性能ではるかに勝るスマートな最新鋭機に、鍛え上げた技量と抜群のチームワークで挑むファアントムライダーたち。意地と誇りを賭して蒼穹を翔昇る信濃航空団パイロットの列伝!!
2001/04/27 刊行
-
電子書籍

秘境西域八年の潜行 3
西川一三 著
チベットの無人境を経てラサに潜入した著者は、祖国敗戦の噂が流布されるなか、“ヒマラヤ越えのアルバイト”に自活の道を見出す。内陸アジアの厳しい自然と対して生きる純朴な人びととの接触を通し、人類平和の希求と人間性探求へと開眼してゆく。第3巻は無人境篇とチベット前篇1を収録。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
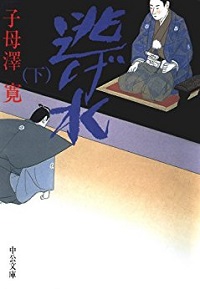
逃げ水 下
子母澤寛 著
高橋泥舟は、勝海舟・山岡鉄舟と共に幕末の三舟の一人として名高い。しかし、幕府崩壊後、彼は海舟や鉄舟のように明治政府に出仕することを潔しとせず、旧主徳川慶喜との誓いをまもり、終生世に出ることはなかった。徳川家に殉じ、赤貧に甘んじながらも清廉に生きた、一武人と江戸市井人への鎮魂の書。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍

アメリカのジャポニズム
美術・工芸を超えた日本志向
児玉実英 著
一八五一年の第一回ロンドン万博を契機に、十九世紀後半は、ヨーロッパで空前の日本ブームが沸き起こった。時を同じくしてアメリカでも同様の流行を見るが、その場合、際立っていたのは、日本趣味の及んだ範囲が、美術や文学といったハイ・カルチャーにとどまらず、服飾、造園、装飾品といった生活に密着した品々にも広がったことである。本書は多岐に亘る実例を示して、短いながらも広く深かった日本趣味流行の軌跡を辿るものである。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍
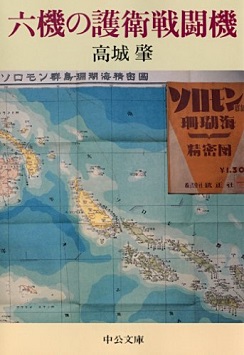
六機の護衛戦闘機
高城肇 著
昭和18年4月18日、悲劇は始まった。山本五十六搭乗機の護衛についた6機の零戦は、大任を果たしえず、その重責を負い、次々に南の空に消えていった。若きパイロットたちの非情な運命を悼み、その生の軌跡を関係者の証言に辿る、知られざる戦争の記録。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍

秘境西域八年の潜行 4
西川一三 著
チベットの無人境を経てラサに潜入した著者は、祖国敗戦の噂が流布されるなか、“ヒマラヤ越えのアルバイト”に自活の道を見出す。内陸アジアの厳しい自然と対して生きる純朴な人びととの接触を通し、人類平和の希求と人間性探求へと開眼してゆく。第4巻はチベット前篇2とヒマラヤ篇を収録。
2001/04/27 刊行
-
電子書籍

実務家ケインズ
ケインズ経済学形成の背景
那須正彦 著
官僚、政治家、実業家、投機家――。ケインズは現実経済の渦中に身を置いて活躍する。そのなかで培われた実感ないし現実認識と、自らが学び、祖述してきた古典派の教義との間の亀裂は次第に深まり、ついに『一般理論』で革命的なマクロの貨幣経済学を創り上げる。ケインズ経済学形成の背景にあるのは、痛切な実務経験なのだ。金融界から学界に転じた著者が、実務家としての共感をこめて、ヴィヴィッドに描き出す新しいケインズ像。
2001/04/27 刊行







