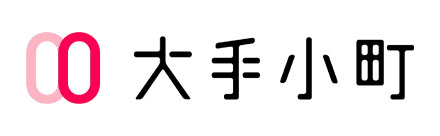ホーム > ニュース・トピックス > 単行本『狂伝 佐藤泰志』に関するお詫びと訂正
2022/09/06単行本『狂伝 佐藤泰志』に関するお詫びと訂正
4月25日に刊行いたしました中澤雄大著『狂伝 佐藤泰志』に誤りがありました。
571ページ最終行において、「地元『北海道新聞』などに配信された記事を読むと」として、同ページ19行目および20行目から572ページ2行目にかけて引用している『北海道新聞』の記事を、共同通信社の小山鉄郎記者が執筆し、共同通信社から配信されたものとして記述していますが、これは小山記者が執筆した、共同通信の配信記事ではありませんでした。
これらを踏まえ571ページ5行目から572ページ7行目の上から7字目までを、以下のように訂正・修正いたします。
確認が不十分だったことにより、共同通信社ならびに共同通信社の小山鉄郎記者、そして読者の皆様に多大なるご迷惑をかけました。お詫び申し上げます。
【訂正・修正前】
これまで流布した「定説」によると、その日は、『文學界』編集部の和賀正樹と恋ヶ窪駅そばの喫茶店で落ち合い、久しぶりに書き上げた小説「虹」を渡したことになっている。私が和賀に取材を重ねた折には既に記憶は薄れていて、「文春本社のサロンで会ったような記憶もある」とも話したが、和賀の当時の住まいは恋ヶ窪にあったことから、地元で落ち合ったと考えるのが自然だろう。前述した通り、「虹」は家族で奥多摩を訪ねた経験をモチーフにしていて、ラストも前向きなシーンで終わる。原稿を読んだ喜美子が素直に「良かった」と感想を伝えると、作家は「今までにない明るい終わり方になっているだろ。こんな風になっていけばいいよな」とご機嫌だった。
共同通信の小山鉄郎の著作『文学者追跡』(文藝春秋、平成四年)によれば、泰志が〈「女房の誕生日だから、この作品が女房へのプレゼントになる」といって受け渡しの日〉を決めたという。その日の晩には〈原稿も上がり、夫人の誕生日でもあり、佐藤さんはしばらくやめていた酒を少し飲んだ。そこでささいな喧嘩になり、家を出たようだが〉と記している。
泰志の死が伝わった十一日は、ノーベル文学賞の発表日に当たり、報道各社の文化部や学芸部の記者は予定稿の確認などに追われて一年で最も慌ただしかった。昼過ぎ、知り合いの編集者から小山の元に「佐藤泰志が自殺した」との一報が入った。驚いた小山は急ぎ作家宅に電話を掛けて、喜美子から話を聞いて〈自宅近くの雑木林で首つり自殺していたことが十一日、分かった〉という事件原稿を書いた。地元『北海道新聞』などに配信された記事を読むと、〈九日午後十一時ごろ、佐藤さんは妻喜美子さん(三九)から酒をやめるように言われたことから口論となり、怒って外出......〉とある。
ただ、喜美子の記憶とは食い違っていた。
「小山さんには〝あの日に飲んだ〟とは言ったわけではなくて、これまでのいきさつを伝えたつもりだったんですよ。こうだった、ああだったって、いっぱい話したの。そしたらああいう記事が出ちゃって......。あの年の六月に酔って血だらけになる事件があったので、きっぱりと飲まなくなっていたんです。
【訂正・修正後】
これまで文壇で語られてきた話によると、泰志はその日、『文學界』編集部の和賀正樹と恋ヶ窪駅そばの喫茶店で落ち合い、久しぶりに書き上げた小説「虹」を渡したという。泰志が女房の誕生日だから、この作品が誕生プレゼントになると言って、受け渡しの日を決めたとされる。原稿を仕上げた解放感に加えて、喜美子の誕生日でもあり、その晩、しばらくやめていた酒を少し飲み、ささいな喧嘩になって家を出たことになっている。
私が和賀に取材を重ねた折には既に記憶は薄れていて、「文春本社のサロンで会ったような記憶もある」とも話したが、和賀の当時の住まいは恋ヶ窪にあったことから、地元で落ち合ったと考えるのが自然だろう。前述した通り、「虹」は家族で奥多摩を訪ねた経験をモチーフにしていて、ラストも前向きなシーンで終わる。原稿を読んだ喜美子が素直に「良かった」と感想を伝えると、作家は「今までにない明るい終わり方になっているだろ。こんな風になっていけばいいよな」とご機嫌だった。
泰志の死が一部マスコミに伝わった十一日はノーベル文学賞の発表日に当たり、学芸部や文化部の記者は日本人作家の受賞に備えた予定稿の確認などに追われて一年で最も慌ただしかった。自身の訃報が少年時代に夢みた賞に重なるとはなんとも皮肉な話だった。
翌十二日の地元『北海道新聞』朝刊社会面にも死亡記事が載った。〈小金井署の調べによると、九日午後十一時ごろ、佐藤さんは妻喜美子さん(三九)から酒をやめるように言われたことから口論となり、怒って外出......〉とある。
ただ、喜美子の後年の記憶とは食い違っている。家には酒瓶はなく、外で酒を飲む金も夫は持たなかったからである。真相は藪の中だが、事態は深刻であった。
「あの年の六月に酔って血だらけになる事件があったので、きっぱりと飲まなくなっていたんです。