
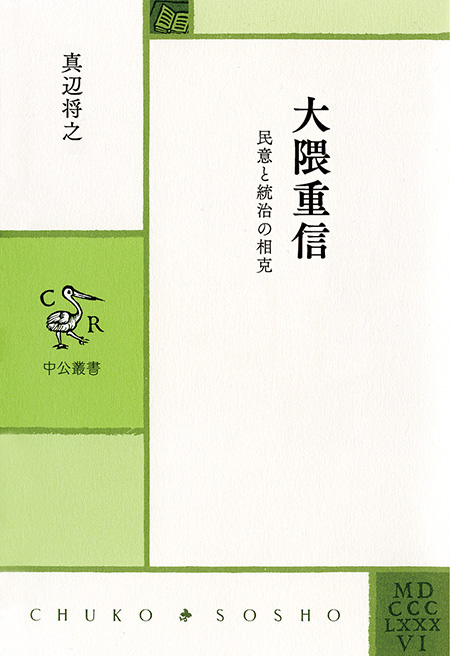
大隈重信民意と統治の相克
真辺将之 著
本書では、あくまで史料に即して大隈の活動を「検証」することを目指した。その際、大隈と政治的に対立していた人物の史料や、出所の怪しい密偵情報などはなるべく使用を避け、使用する際にはしっかりとした史料批判を経て使用するように心がけた。その上で、本書では、大隈の日本近代史における軌跡を、その挫折や失敗、負の部分までをも含めて明らかにしていきたい。というのも、大隈の栄光だけでなく、そうした挫折や負の部分のなかに、現在の我々にとって新たな発見をもたらしうる材料が含まれていると信じるからである。現代社会のあり方や我々の生き様につながる何かを、本書のなかから見つけていただければ幸いである。(はじめにより抜粋) 第一章 近代西洋との遭遇――佐賀藩士・大隈八太郎新時代のきざし生誕幼少年時代の修学父の死と母の愛内生寮に入学藩校教育への反発経学派と国学派の対立厳しい課業制度『葉隠』批判南北騒動義祭同盟佐賀の蘭学「愛国心」の誕生蘭学寮での学習桜田門外の変蘭学寮教官となる藩の富国策長崎遊学と「蕃学稽古所」の設立フルベッキから学んだもの大政奉還を説く出遅れた佐賀藩低すぎるスタート地点第二章 近代国家日本の設計―明治新政府での活動明治維新の理念「統治」と「民意」長崎鎮定井上聞多(馨)との出会い浦上キリシタン処分問題パークスとの舌戦横須賀造船所問題外交的能力外交から会計へ金札の信用回復と「円」の誕生全国統一を目指す築地梁山泊維新派と復古派鉄道敷設を主張レイ借款問題進歩的施策の断行地方官の反撥民蔵分離問題当時の大隈の性格参議に就任大久保の大蔵卿就任廃藩置県の断行使節団派遣の提案約定書の取りまとめ留守政府の取りまとめ役として留守政府の改革財政をめぐる衝突改革と井上との板挟み参議増員と太政官制潤飾予算の公表征韓論大久保、大隈、伊藤の結束江藤との訣別台湾出兵出兵中止命令と臨機の決断三菱との関係島津久光による弾劾大隈の反撃と大久保、伊藤の支援地租改正の完遂秩禄処分産業発展の基盤整備と輸出奨励明治初年の大隈第三章 「立憲の政は政党の政なり」―明治一四年の政変参議筆頭としての大隈大久保利通の死大隈財政の基本路線西南戦争後のインフレとそれへの対処洋銀相場対策準備金の運用参議・省卿再分離外債五千万円募集案伊藤の疑念伊藤との共同提案福沢諭吉との接近福沢門下の推薦会計検査院と統計院『法令公布日誌』発行計画井上・伊藤の議会開設構想大隈の憲法意見書政府主導の政党政治大隈意見書への反応井上毅の暗躍大隈に陰謀があったか開拓使官有物払下げ事件掘り返される過去の「失敗」退職勧告民権運動と藩閥政府のはざまで大隈の「不幸」と「失敗」第四章 漸進主義路線のゆくえ-立憲改進党結成から条約改正交渉まで「第三の道」のゆくえ洋行の風評立憲改進党の結党改進党の政治綱領明治会堂大演説会における政綱解説改進党内の勢力構造東京専門学校の設立外国の学問からの独立政治権力からの学問の独立政府による弾圧と鍋島家からの後援自由党との関係改進党の地方への発展黒田清隆との接近甲申政変への対応改進党員と政府要人の接近改進党解党問題大隈の脱党大隈の資金繰り大同団結運動外相就任交渉伊藤博文の芝居条約改正の方針世論の沸騰条約改正時の改進党の団結力の強さ閣内での反対意見と交渉の頓挫遭難後の改進党と政府憲法発布と大隈超然主義か政党内閣か民意の反撥のなかで第五章 理念と権力のはざまで―初期議会期の政党指導苦境のなかでの議会開設矢野竜渓の政界引退条約改正による打撃進歩党合同問題民党連合路線第一議会の予算審議予算案に対する大隈の意見板垣との接近と枢密顧問官辞任第二議会の解散と選挙干渉第三議会第四議会と民党連合破綻の兆し「責任内閣」の主張条約励行路線の採択第五議会日清開戦日清戦争と大隈母の死日清戦後経営論日清戦後の政局進歩党の結成公衆の面前へ松方との接近入閣交渉二十六世紀事件第一〇議会新聞紙条例改正と金本位制施行農商務大臣兼任勅任参事官設置問題松隈内閣倒れる早稲田での初演説第三次伊藤内閣憲政党の結党隈板内閣の成立政党内閣の誕生第六章 政党指導の混迷―第一次内閣以後の政党指導政党内閣の失敗と長い混迷の時代隈板内閣の組閣内閣の方針過大な猟官要求とのせめぎ合い第六回衆議院議員総選挙尾崎文相の「共和演説」事件予算の策定行政整理文相後任問題解党と再編支那保全論の提唱と康有為・梁啓超の保護第二次山県内閣と地租増徴問題山県内閣による文官任用令の改正義和団事件と「支那保全論」清国人教育への貢献立憲政友会結成と尾崎行雄脱党も問題総理就任増税問題をめぐる分裂桂太郎内閣の成立と憲政本党大隈邸の火災と資金難新築された大隈邸と台所温室大隈の園芸趣味早稲田大学の開校「私立」へのこだわり日本女子大学校への援助第七回・第八回総選挙伊藤と桂の接近憲政本党の苦衷党幹部による政党指導日露開戦論の高揚奉答文事件と日露開戦桂と政友会との接近ポーツマス条約と大隈「支那保全論」の継続西園寺内閣の成立と大隈大隈排斥運動の発生改革派による党内「民主化」の提案大隈の敗北と積極主義の採用大隈の「告別演説」「国民」に立脚して「政治は我輩の生命である」大隈・憲政本党不振の背景二大政党か一大政党か「民衆政治家」としての再出発多事争論からの公論形成第七章 日本の世界的使命―東西文明調和論と人生一二五歳説党首引退後の活動「文明運動」とは何か日露戦争と『開国五十年史』編纂の開始『開国五十年史』の出版とその結論『国民読本』の刊行天皇の権威と国民の権利国民教育への邁進なぜ国民教育か同仁会同仁会への国庫補助を求めて『日本百科大辞典』編纂総裁国書刊行会総裁文芸協会日印協会外国人との交流大日本文明協会南極探検の後援日本自動車倶楽部会長帝国飛行協会会長大日本平和協会会長帝国軍人後援会会長軍事知識の普及弱者への目線スポーツの振興と大隈雑誌『新日本』の発刊人生一二五歳説の提唱怒らない大隈永遠の青年として大隈の生活大隈の読書旺盛な講演と談話憲政本党の紛擾と仲介伊藤博文の死辛亥革命への態度孫文との関係辛亥革命後の中国情勢と大隈?州・漢口・南京事件と世論の沸騰文明論の陥穽憲政擁護運動の勃発と「中心勢力移動論」の提唱護憲運動への批判桂内閣への好評価桂新党への賛同桂の政治指導への期待文明運動時代の大隈「民意」への批判大隈発言の真意第八章 世界大戦の風雲のなかで―第二次大隈内閣の施政「薩長劇より国民劇へ」大隈推薦の経緯元老との交渉組閣と内閣の顔ぶれ内閣成立に対する反応政綱発表と財政整理絶対的非募債政策減債基金振替による鉄道改修地方官の更迭臨時議会の開催第一次大戦の勃発と参戦問題元老との亀裂加藤と大隈国定教科書批判と第三期国定教科書第三五帝国議会総選挙大隈伯後援会選挙の取締り与党の大勝利と課題第三六特別議会二十一箇条要求の内容大隈と二十一箇条要求二十一箇条要求に対する元老山県からの批判二十一箇条要求に対する野党からの批判参政官・副参政官の設置大浦事件留任と内閣改造袁世凱帝政延期勧告大正天皇即位大礼と第三七議会減債基金還元問題山県有朋による調停簡易保険制度ならびに理研の創設加藤内閣成立運動日露協約の締結寺内・加藤連立工作三派合同運動大正天皇に賭ける民意と統治のはざまで第九章 晩年の大隈重信―国民による政治と世界平和を求めて大隈の二つの目標大隈は「元老」か?第一三回総選挙と大隈政党批判国民教育の継続『大観』発行早稲田騒動と一時的危篤軽井沢別荘寺内内閣倒壊に伴う御下問原敬内閣の誕生と第一次世界大戦の講和「東西文明の調和」の探究英国労働党政策提言書での言及東西文明論の研究時事問題研究会国際聯盟への態度驕慢なる日本人を戒める自己反省なき平和論デモクラシーの勝利と階層的分断の深刻化国民への期待「教化的国家論」の提唱「教化的国家論」と軍縮平和への楽観対外政策批判日本人への期待元老権力の行使山県との接近山県との面会病に斃れる摂政就任御沙汰書国民葬の挙行おわりに―歴史の「大勢」のなかで
書誌データ
- 配信開始日2025/6/30
- 判型中公eブックス
- 希望小売価格2420円(10%税込)







