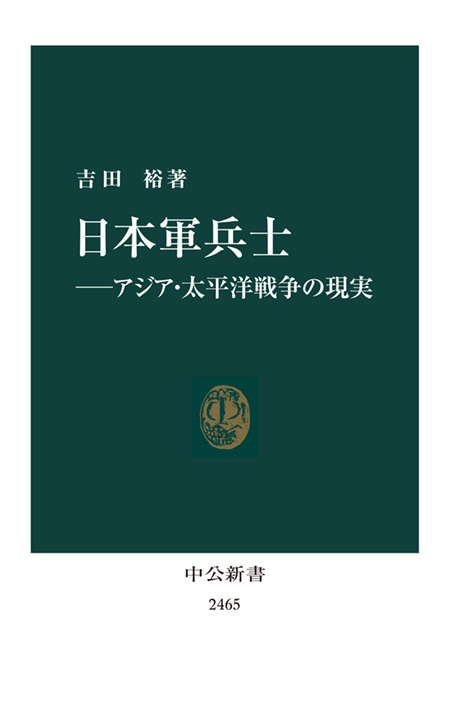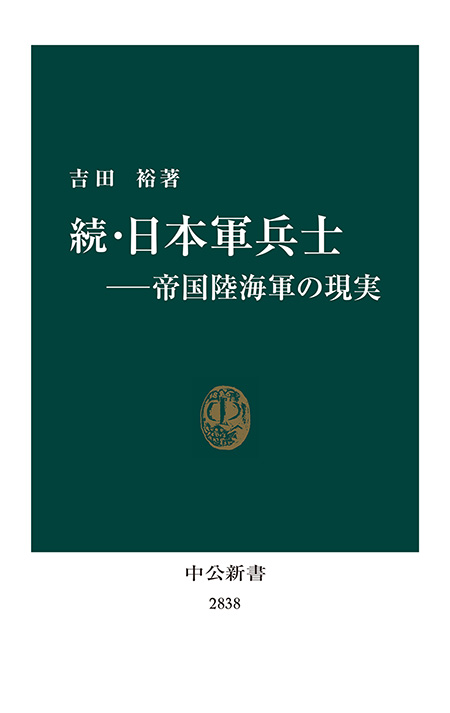
続・日本軍兵士―帝国陸海軍の現実
吉田裕 著
先の大戦で230万人の軍人・軍属を喪った日本。死者の6割は戦闘ではなく戦病死による。 この大量死の背景には、無理ある軍拡、「正面装備」以外の軽視、下位兵士に犠牲を強いる構造、兵士の生活・衣食住の無視があった。 進まない機械化、パン食をめぐる精神論、先進的と言われた海軍の住環境無視......日中戦争の拡大とともに限界が露呈していく。 本書は帝国陸海軍の歴史を追い、兵士たちの体験を通し日本軍の本質を描く。【目次】はじめに序 章 近代日本の戦死者と戦病死者――日清戦争からアジア・太平洋戦争まで疾病との戦いだった日清戦争 戦病死者が激減した日露戦争 第一次世界大戦の戦病死者 シベリア干渉戦争の戦没者数 伝染病による死者の激減 軍事衛生の改善・改良と満州事変 退行する軍事衛生――日中戦争の長期化 アジア・太平洋戦争の開戦 陸海軍の戦没者数 日露戦争以前に戻った戦病死者の割合第1章 明治から満州事変まで――兵士たちの「食」と体格1 徴兵制の導入――忌避者と現役徴集率徴兵令の布告 現役徴集率二〇%の実態 徴兵忌避の方法 沖縄の現実、徴兵忌避者の減少 軍医の裁量権――高学歴者への配慮と同情2 優良な体格と脚気問題――明治・大正期明治の兵士――身長一六五センチ、体重六〇キロ 脚 気――総人員三割から四割の罹患 兵士たちを魅了した白米3 「梅干主義」の克服、パン食の採用へ栄養学の発展――第一次世界大戦後の日本 陸軍の兵食改善 一九二〇年のパン食導入 冷凍食品の導入と大型給糧艦 洋食の普及と充実――満州事変期 壮丁と兵士の体格4 給養改革の限界――低タンパク質、過剰炭水化物シベリア干渉戦争の失敗 飯盒炊さん方式による給養 兵食における質の問題 陸軍でのパン食のその後 揺れる海軍のパン食――「皇軍兵食論」の登場第2章 日中全面戦争下――拡大する兵力動員1 疲労困憊の前線――長距離行軍と睡眠の欠乏苦闘を強いられる日本軍 萎縮し「奮進」できない兵士たち 多発する戦争栄養失調症 「殆ど老衰病の如く」2 増大する中年兵士、障害を持つ兵士低水準の動員兵力 軍隊生活未経験者の召集 召集が原因の出生率低下 国民兵役までも 知的障害の兵士 吃音の兵士 野戦衛生長官部による批判 攻撃一辺倒の作戦思想3
書誌データ
- 配信開始日2025/1/22
- 判型中公eブックス
- 希望小売価格990円(10%税込)