- 2026 01/14
- まえがき公開
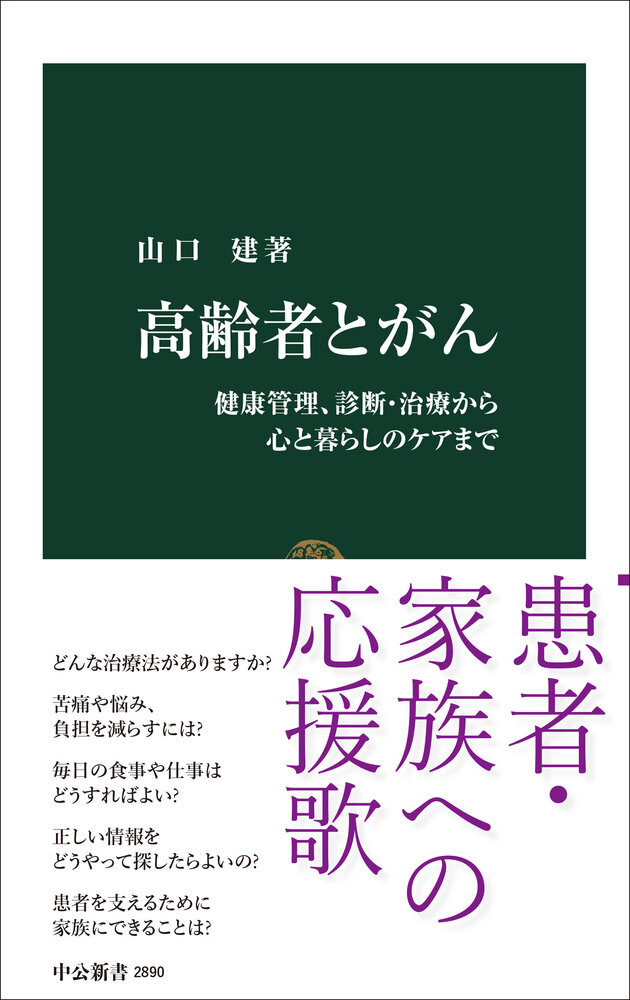
2人に1人はがんに罹り、その75%が65歳以上の高齢者である。今では6割の人々が治癒するが、それでも患者は時として「身体と心の弱者」になってしまう。本書は、がん発生のメカニズムから健康管理、正しい診断と最善の治療、退院後の注意点まで、最新の医学を解説。さらに、高齢がん患者と家族の心をケアするために何ができるか、がんと向き合うための心構えをどう持つか、1万人以上の患者・家族の証言をもとに説く。
『高齢者とがん 健康管理、診断・治療から心と暮らしのケアまで』(山口建著)の「はじめに」を公開します。
はじめに
我々は、2人に1人ががんに罹るという「がんの時代」を生きている。毎年約100万人ががんと診断されるが、年齢は9割以上が50歳以上で、さらに、全体の7割5分は65歳以上である。このように、がんは高齢者に多い病気である。
不治の病と恐れられていたがんも今では6割は治せるようになった。現在、数百万人の人々ががんを治し、元気で暮らしている。そこには、がんの克服を信じて地道な努力を続けた医療スタッフや研究者とともに、患者会や行政など社会の人々の貢献があった。
筆者が、がん医療を志して半世紀が過ぎた。最初に勤務した国立がんセンター(当時。現在は国立がん研究センター)では、治癒が困難な進行・再発乳がんの診療の傍ら、膵臓がんについての基礎研究を担当していた。当時、膵臓がんは、高齢者に多く、治すことが困難な難治がんの代表だった。国立がんセンターの膨大な膵臓がん治療成績を見ても治癒例はほぼ皆無で、「膵臓がんは治せない病気」との印象が強かった。それでも医療スタッフは来る日も来る日も患者に向き合い、治療成績向上のための努力を続けていた。やがて、早期発見例が見つかるようになり、治癒例が少しずつ増え、条件さえ整えば、膵臓がんでも治癒を目指せるようになった。いまだ少数にとどまるが、膵臓がんを克服し、元気に暮らしている街の商店主やスポーツ指導者や公務員の姿を身近で見て、「治せなかったがんが、半世紀をかけて治せるようになった」と実感する今日この頃である。
本書では、がん医療の現況を伝えるとともに、1人でも多くの人々が、がんに罹らず、また、がんに罹ってもできるだけ良い結果を得るための手立てを伝えたいと考えた。そこで本書では、がんから身を守る健康管理や、がんに罹ったときに最善の治療を受けるための手続きや心構えなどを具体的に記述した。こうした取り組みにより、現在の医療技術のままでも、がん患者の8〜9割は、苦痛を和らげて治すことができるだろう。
がん医療の進歩を伝えることも本書の目的の一つである。
まず、がんはどのようにして発生するのか、そのメカニズムが解明されつつある。その成果は、がん予防や新しいがん診断技術や薬剤の開発に生かされている。
がんの診断・治療に用いる医療機器も画期的な進化を遂げた。診断分野では、CTスキャン、MRI、超音波検査(エコー)、内視鏡、PETスキャンなどの新たな機器が生まれ、がんの早期発見や確定診断に寄与している。今では、これらの機器を活用し病理診断を行うことによって、がんか否かの判断をほぼ確実に行えるようになった。
手術と放射線と薬剤はがん治療の三大療法である。半世紀前を振り返ると、がん患者の多くは、手術後、傷の痛みで七転八倒し、放射線療法では後遺症に悩み、薬物療法では、激しい吐き気や血液障害などの副作用に苦しんだ。また、がんが悪化した場合の強い痛みなどの症状もあまり抑えることができなかった。
それが今では、患者の負担を和らげる様々な治療技術が普及している。手術については、患者の負担を抑える「低侵襲性手術」が確立され、麻酔法の進歩も相まって、患者の苦痛は大きく改善された。放射線療法では、高精度照射や粒子線治療のような「ピンポイント照射」により、治療効果が高まり、副作用を抑えることが可能となった。薬物療法の分野でも、治療効果が高く、副作用や合併症が少ない新たな薬剤が開発されている。
加えて、がんによる症状や治療に伴う副作用・合併症・後遺症を和らげるための「支持療法」や、患者の深い悩みや苦痛に対処し、あるいは最期を看取るための「緩和ケア」も広く普及した。その結果、がん治療を受ける患者の身体的苦痛はかなり抑えられている。
がん患者は「身体と心の弱者」である。がんを攻撃する治療技術の進歩とともに、一人の人間としての患者の心のケアも重視されるようになった。がん患者やその家族の心のケアを推進するために、筆者らは、多くのがん患者やその家族が頻繁に体験する苦痛・悩み・負担などを和らげるための「がんの社会学」研究を進めてきた。
がんと診断されたとき、患者・家族は、あまり知識を持ち合わせていない。患者とその家族は人生最大の危機に直面したと考え、心は千々に乱れてしまう。その状況を乗り越えるには、ある程度の知識を身につけたうえで、患者自身ががんと向き合い、必要な情報や支援を入手することが大切である。
本書では、全国調査によって収集された1万2000名の患者・家族の証言や静岡県立静岡がんセンターの「がんよろず相談」での経験などをもとに、随所で患者・家族の証言や思いを紹介し、その対処法について言及した。がんと診断された患者や家族は、多くの先人たちが今の自分と同じ苦痛や悩みや負担に向き合ったことを知り、孤独感を和らげることができるだろう。
さらに本書では、「身体と心の弱者」としての、がん患者の心の動きを説明したうえで、患者を支える家族や周囲の人々の役割についても述べた。また、困難な状況に置かれた患者・家族が、それを乗り越え、心の平穏を取り戻せるよう、心の在りようについても紹介している。
がん医療が進歩し、治癒率が向上し、身体への負担が少ない治療法が普及するなかで、いまだ解決が難しい課題が残されている。
その一つは、本書のテーマでもある高齢がん患者への取り組みだ。高齢のため、最善のがん治療を実施できない患者が増えている。生活面でも、ひとり暮らしの高齢患者や老老介護の家庭が増え、身体や心のケアや暮らしの支援に難渋するケースが目立つようになった。
また、今でも4割のがん患者は、がんのため命を失っている。こうした治癒困難な進行・再発がん患者の治療・ケアには、今まで以上に、生活の質(Quality of Life、QOL)や死の質(Quality of Death、QOD)を向上させる努力が求められている。その取り組みの一つは、科学的根拠に基づく医療とともに、「物語に基づく医療」の実践だと思う。患者やその家族は悲しみを乗り越え、死を受け入れるために、自分たちの物語を紡ごうとする。
再発乳がんが悪化し、余命幾ばくもないと悟った高齢の女性は、ある日、「先生、お願いがあります」と切り出した。「自分は、もう長くは生きられないのでしょう。でも、心配なことがあります。夫はひとりで暮らすことができません。食事も洗濯も家計も……。大変申し訳ないが、先生に後のことをお願いしたいのです」。そう言って患者は、夫の食事の嗜好、服装のこと、貯金通帳の置き場などについて話しはじめた。「先生にそんなことを言っても」と何度も話を遮ろうとした夫も、やがて嗚咽を漏らしながら病室の外に出ていってしまった。
夕闇が迫る病室で、真剣な患者と途方に暮れた医師との2人きりの会話は、こうして1時間ほど続いた。話し終えると、患者は晴れ晴れとした顔になり、疲れたのか目を閉じた。彼女が旅立ったのはその数日後のことだった。このとき患者の意識は少し混濁していたかもしれないが、死を前にして「やるべきことを終えた」という気持ちになれたのだと思った。
2024年、日本では、がんによる死者約38万人を含め、約161万人が亡くなっている。その一人ひとりと家族には、百数十万の物語があるはずで、それぞれの物語を大切にすることが、悲しみを乗り越えるのに役立つと考えている。
本書は、単なる知識の提供というよりは、一人ひとりの読者が、健康人として、あるいは患者・家族として、がんに向き合うための手ほどき書のつもりで記述した。がんの予防や早期発見・早期治療への理解が深まり、最善の治療を受けることによって、1人でも多くの患者が救われることを願っている。そして、がんで悩み、苦しむ患者・家族が体験する辛さを、少しでも和らげることができれば幸いである。
(「はじめに」、著者略歴は『高齢者とがん』初版刊行時のものです)
