- 2025 11/13
- まえがき公開
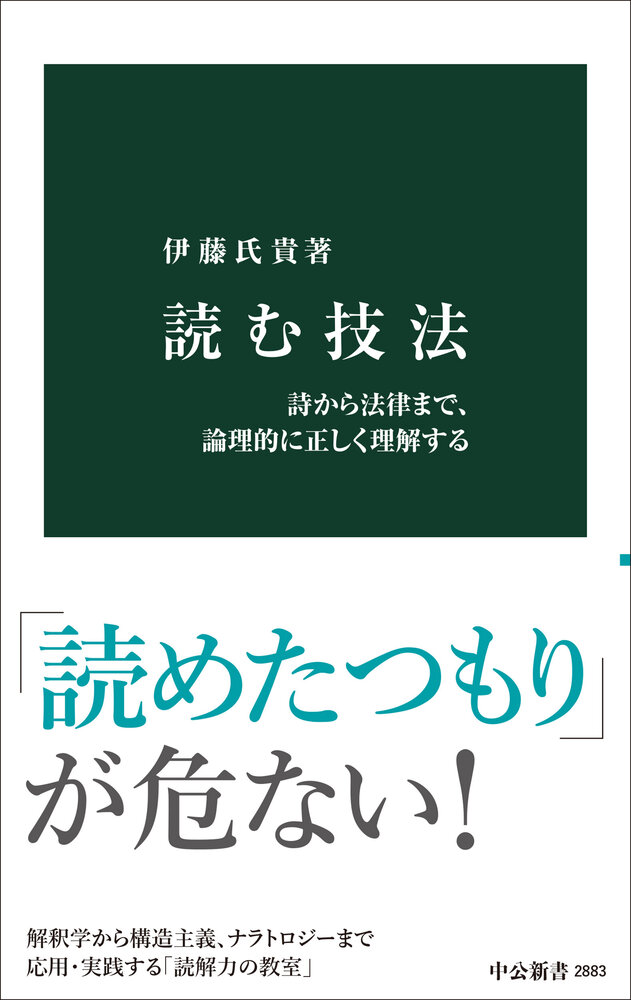
あふれる情報の中で時間に追われ、なおかつプレゼン能力が重視される昨今、読むという行為が疎かになっていないだろうか。本来、書き手の意図を正しく汲み取れて、初めて議論や思索は成り立つのに。本書は解釈学、構造主義、ナラトロジーなど、西欧で発展した読む技法を紹介。詩、小説から評論、法律まで多様なテクストを例示し、技法を応用して読み解く。より深い読解力を身につけたい読者のための、実践的な入門書。
『読む技法 詩から法律まで、論理的に正しく理解する』の 「はじめに」を公開します。
はじめに――「読めたつもり」の危うさ
太郎はクマと同じくらいハチミツが好きだ。
この文章はどう「読める」か。おそらく本書を手にしておられる方のほとんどは、「太郎とクマはどちらもハチミツが好きだ」という意味で理解されたのではないか。
だがこれを、「太郎は、クマとハチミツのどちらも好きだ」という意味にはとらなかったとすれば、それは一体なぜなのか。
「AはBと同じくらいCが好き」は、「AはCが好き、かつBはCが好き」とも、「AはBが好き、かつAはCが好き」のどちらの意も表しうる、構造だけ見れば危うい文である。
だが冒頭の文に関しては、前者、すなわち太郎とクマのどちらもが主語であると無意識の裡に判断していたとすれば、そこにはたんに語の意味や文法や文構造を理解できるというレベルの「読める」とは異なる知が働いているはずだ。
つまり、ここでは「ハチミツはクマの好物だ」という前提知識が暗黙知となって「読み」を確定しているのである。おそらく語り手(書き手)は、太郎がどれほどハチミツ好きかを強調したくてクマを引き合いに出したのだろう。ミツバチに襲われるのを物ともせずにハチミツを貪るクマのイメージがこの発言の背後にあり、読者も当然そのことを知っているだろうと思ってこういう表現をしたのではないか、という推測はおそらく妥当だ。
クマの好物に関する前提知識を無視して、あるいは無知ゆえに、これを「太郎はクマも好きだしハチミツも好きだ」と解するなら、それは読めたことにはならない。文法構造を盾にとって、こうも読めるじゃないか、と声を荒らげるのは不毛な抵抗だ。
文学作品の読解においては、近年特に、作者の意図よりも読みの多様性が重視される傾向がある。だが、ああも読める、こうも読めるという解釈の多さがすなわち読みの豊かさだというわけではない。無用な混乱を招くだけのこともままある。
本書はむしろ、そのような多様な可能性の中から一つの中心へと絞り込んでいくことを目指す。冒頭の文で言えば、「太郎とクマはどちらもハチミツが好きだ」という表層の意味に加えて、「太郎がいかにハチミツ好きかを強調したい」という意図を汲むところまでを読むのが当面の目標である。
もちろん、テクストが書き手の意図を超えて何かを意味することはしばしばある。たんに文構造のあいまいさから別様の読みの可能性が生じてしまうという意味合いではなく、たとえばテクストの表面には現れていない書き手の深層心理や時代の精神などが読み取れるような場合である。
たしかにこれは読みの豊かさと言えるだろう。「テクスト」という語自体、文章や作品と異なり、書き手や作者から離れてことばだけに注目するために、文学理論の分野で使われ出したところもある。
だが、文学にかぎらず、どんな種類のテクストであっても、書き手がいるかぎり、そこには必ずや伝えたい何かがあった。
いや、ただ事実を記述するだけで、それ以外のなんの意図も籠められていない文は存在する、と思うかもしれない。たとえば「2×2」という数式は、クマやハチミツのような具体的なものを一切指し示さず、それゆえ「4」という答え以外の何ものをも含意しないだろう、と。たしかにこの数式だけを取り出していくら眺めまわしても、それを書いた人間の意図を汲むのは難しい。だが、この式がいきなりなんの脈絡もなく出てくることなどありえない。たとえば、これがドストエフスキーの小説の中に置かれていたらどうだろう。2×2=4というたんなる等式であっても、作者がそこに籠めている意図を無視して読んでは、作品全体の意味もわかるまい(注1)。
言語は孤独な思索の道具でもあるが、それ以前にまずは他者との意思疎通のための手段としてある(注2)。人類史の上でも、赤ん坊からの個人の発達史の上でもだ。
書かれたテクストの場合も、まずは他者に伝えようとした意図をしっかり捉えてからでなければ、その裏にある作者の無意識や時代精神を暴くこともできない。相手の意図を汲みとることをもってひとまず「正しく読める」と言おう。その先まで理解できるのは「深く読める」ことであり、望ましくはあるが、まずは書き手の意図という読みの中心を通ってからでなければ、深みに辿りつくどころか、表層をさまよいつづけるだけだ。
冒頭の文を「太郎はクマも好きだしハチミツも好きだ」と解するならば、書き手の意図に辿りつくことはないだろう。これは多様性というより誤読である。誤読の上に展開される議論は、しばしば相手のことば尻を捕らえた論破だけが目的化してしまう。議論をするにせよ、自分の思索を深めるにせよ、書き手の意図を土台としなければ空回りするだけだ。
このことをしつこく強調するのは、実際には書き手の意図ではないものを読んで読めた気になってしまうケースが少なくないからだ。これは、「読めない」と自覚している場合よりたちが悪い。読めなければもっと読もうと試行錯誤する余地も生まれるが、読めたという勘違いは誤読をそのまま定着させてしまうからだ。
書物から書類、ネットニュース、メール、SNSに至るまで、われわれが日々読まねばならない文字テクストはきわめて多い。この洪水のなかで表層的な読みによって他者の意図を誤解してしまう危険はかつてないほど高まっている。生産的な反論をするためにも、相手の意図をきちんととらえることが必要だ。
さてでは、読む目標を他者の意図を汲むことに置くならば、それなりの苦労は避けて通れない。それはしばしば表面的な意味の奥深くに隠されているからだ。ただし、文字テクストはメディアの中でも最古の部類に属し、それゆえその読解の技法も長らく研究され、積み重ねられてきた。とりわけ西洋において、二十世紀後半には、いささか先鋭的すぎるほどまで研ぎ澄まされてきた。
「nani gigantum umeris insidentes(巨人の肩に乗る小びと)」とは、ニュートンも書簡の中で自身を指すのに用いた、よく知られた慣用句だ。われわれがより遠くを見通すためには、これまで先人が積み上げてきたものの上に乗る必要がある。
ただし、巨人は地面にいるわれわれをつまみ上げて肩に乗せてくれるわけではない。われわれは自力でそこまでよじのぼっていかねばならないのである。時代が変わり、どれほどテクノロジーが進んでも、この「巨人の肩に乗る」構造は変わらない。「読解力」が要請される所以である。
本書は、先人の積み上げてきた「読む技法」を紹介しつつ、それを実際に個別のテクストにどのように応用するのかを実践するものである。いわゆる批評理論の網羅的紹介ではない。批評という書く行為の前に、まずテクストをどう丁寧に読むのか、という点に集中する。今はアウトプットの方が強調される時代だが、良きアウトプットには、その前にまず良きインプットがなければならないからだ。
また、近年の批評理論は基本的に文学的テクストの読み方として発達したもので、ときに作者の意図を超えてでもおもしろく読むことを目標とするが、本書はテクストのジャンルにかかわらず、あくまで慎ましく書き手の意図を重視する。
オリエンテーションにあたる序章を除き、各講は独立しており、興味のあるテクストを扱っている講から読んでいただいてかまわないが、可能なら講順に読み進められたい。あとの講にいくほど、前の講で学んだ技法を組み合わせて用いるし、特に、最後の第八講は、それまでの技法を集大成したおさらいのような意味合いを持っている。ちなみに、第一講は共通一次試験(現・共通テスト)、第八講は東大入試に出題されたテクストを扱っており、テクスト自体もだんだん手強いものになっていく。
第一講以降は、実際にどのように読むのかを具体的に理解するために、特定のテクストに基づいて展開される。インターネット上ですぐに読めるものについては基本的に割愛しているが、その場合も、必ずまずテクスト本文を読んでから本書に戻っていただきたい。本文を読まずにその読解法だけを見ても、得られるところは少ないだろう。
さらに読み方の解説部分も、テクストに適宜立ち返りつつでなければ、十分に理解できないかもしれない。大いに手間がかかると思うが、理論はこうした実践を通じてでなければ決して身にはつかない。ここで習得した技法を、今後広く他のテクストでも実践していただくことが本書の目指すところである。
なお、「テクスト」という語は、主に文学の世界で、作者の権威の下に置かれた「作品」という概念と対比的に、読者が自由に読む対象として使われるが、本書ではジャンルを問わず書かれた文章という意で用いる。一方、「作品」は、一つの文学のテクスト全体を指すときに用いる。
(まえがき、著者略歴は『読む技法』初版刊行時のものです)
(注1)『地下室の手記』において、この等式は自然科学の象徴として登場する。
(注2)たとえば、アリストテレスは『政治学』で、人間を「社会的動物(zōon politikon)」と呼び、一方でまた「ロゴスを持つ動物(zōon logon echon)」と呼んでいるが、ことば(logos)が共同的(politikon)な生を支えているのであり、二つの定義は別のものではない。つまりことばを通しての共生が人間としての条件だということだ。
