- 2025 06/23
- まえがき公開
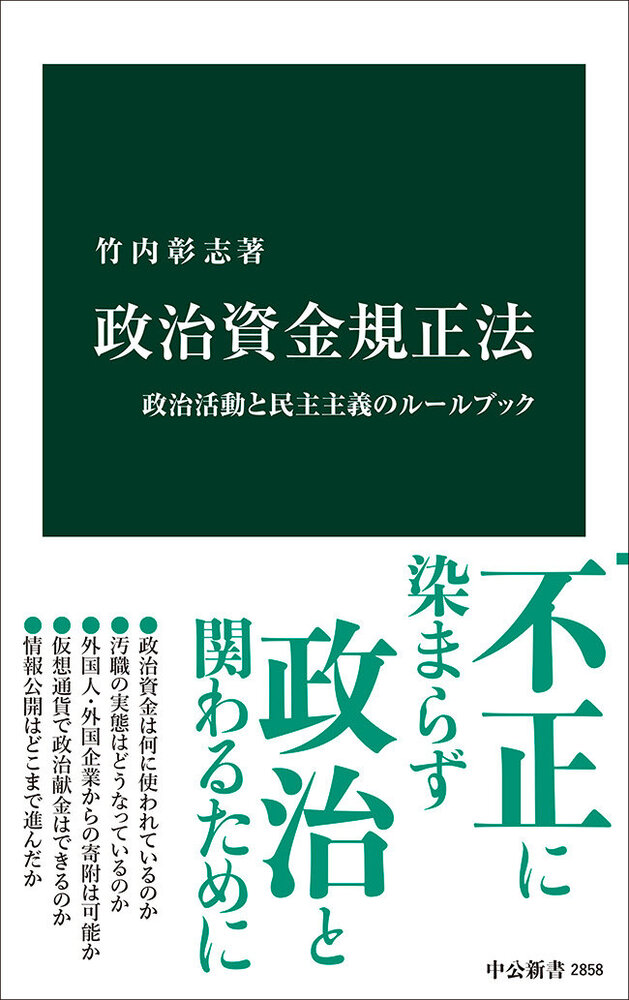
政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与するため、一九四八年に施行された政治資金規正法。だが、政治とカネの問題は絶えず、これまでに何度も改正されてきた。本書は、議員の収入と支出の実態や、歴史的経緯を踏まえ、同法の見取り図を示す。さらに政治資金パーティーなどの事例を通じ、具体的な金銭の動きも解説。情報公開のあり方や、政治活動で注意すべき点などを論じ、今後の課題と展望を記す。 『政治資金規正法 政治活動と民主主義のルールブック』の 「まえがき」を公開します。
「政治とカネ」という言葉からは、多くの人がダーティーな印象を受けるのではないか。これまで、政治資金をめぐって数多(あまた)の事件が起きている。国民が政治に懐疑的な目を向けるようになって久しいのは、そうした政治腐敗によるところも大きいだろう。
政治資金に関する事件を法的に扱う際、我が国では政治資金規正法の出番となる。政治資金とは、選挙を通じて選ばれる政治家や、政策実現のために活動する団体が、日常の政治活動を行う際に用いる資金をいう。際限なく政治資金を使えるとすれば資金力や集金力のある者のみが有利となり、民主主義制度の根幹を危うくしてしまう。
そこで、同法は、どのように政治資金を集め、何に使用しているのかを、政治資金収支報告書を通じて公開させる役割がある。政治資金を国民の監視下に置いたのだ。
遡れば、一九四五年の第二次世界大戦終結を経て、四八年に成立した政治資金規正法は、アメリカ合衆国の腐敗行為防止法を基礎として制定された。当時は、政治団体の収支の公開を限定的に行う法律に過ぎなかった。端的にいえば、政治団体は収支の公開を一部行うことと引きかえに、繰越金が出ても課税されないという取り扱いになっている。
多くの政治家は、政治活動の原資として政治資金を必要としている。課税されないとなれば、当然、政治家は政治団体を経由した政治資金の出入りを増やすことになる。結果、たとえばリクルート事件のような政治家の資金をめぐる不祥事が生じた。その都度、政治資金規正法は改正され、規律が強化されていった。
不祥事を見ていくと、国会議員をめぐる話題が多い。しかし実は、政治資金規正法によって規制を受ける対象は、政治家個人ではなく政治団体である。そして政治団体は、国会議員に限らず、地方議員、自治体の首長も設立できるほか、立候補を予定している段階の者でも作ることができる。また公職に立候補せずとも、一定の政治活動を行う者ならば、都道府県選挙管理委員会に届け出さえすれば設立できる。収支の内容は毎年公開され、一般の会社や個人と異なり、基本的に課税を受けないという、特殊な団体である。
二〇二三年から二五年にかけての自由民主党(自民党)の派閥裏金問題は、政治資金収支報告書に記載すべきパーティー券収入を計上せずに処理したものだ。これは、国会議員自らが作った政治資金規正法の公開機能を損なわせてしまった事案である。本書では、政治の実態と、政治資金規正法の乖離(かいり)を明らかにし、また国会での政治資金規正法改正の議論を踏まえ、同法の到達点と残された課題を確認したい。
以下、簡単に本書の構成を記そう。
序章では、政治資金規正法の目的などをコンパクトに解説する。当事者には自明かもしれないが、一般的には不明瞭な政治資金の位置付けを整理して、政治資金規正法は機能しているか、という問題提起をする。
第1章では、政治団体や政治家の実際の活動を、資金の側面から分析する。政治家、とりわけ国会議員が負担する経費の実態を示すべく、政治家側の視点に立って書いた。続く第2章では、政治資金をめぐる不祥事や大型事件のたびに改正された同法の内容を確認し、その裏にある国会論戦を整理した。政治史と政治資金規正法改正を並列的に検討した結果、時々の事件と改正の内容とのチグハグな関係が見えてきた。
政治資金の統制の仕方には、大きく分けると二つの手法がある。一つは政治資金の移動そのものを規制する考え方で、もう一つは政治資金の公開によって国民の監視下に置く考え方だ。前者については、第3章で政治資金がいかに集められているかに焦点をあわせて政治団体への資金移動を取り上げる。後者を扱う第4章では、政治資金がどこまで公開されるのかを論じた。政治資金収支報告書を読む際のヒントになるように書いたので、これから政治に携わったり、政治参加に関心がある読者は特に参照してほしい。
第5章では、自民党の派閥裏金問題を中心に、政治家らが既存の政治資金規正法をどう守らなかったのかについて整理していく。また、法改正に対する各政党のスタンスと、国会での議論にも触れる。
終章では、法改正を経てもなお残る課題を指摘し、今後の制度改正にあたって、考慮すべき方向性を示す。
筆者は、弁護士として、政治資金規正法、公職選挙法といった政治や選挙にまつわる分野を担当してきた。また、政治資金規正法が定める登録政治資金監査人として総務省政治資金適正化委員会に登録しているほか、東京・永田町で国会議員政策担当秘書として活動した経験がある。秘書をしていた際には政治団体や政党支部の政治資金収支報告書の会計責任者を務め、政治資金収支報告書を作る側として、外部の登録政治資金監査人による政治資金監査にも対応した。
本書では、政治資金収支報告書を内部で作成した経験と、外部でチェックしてきた立場の双方を活かし、一般読者にとってなるべくわかりやすく解説を行いたい。
(まえがき、著者略歴は『政治資金規正法 政治活動と民主主義のルールブック』初版刊行時のものです)
