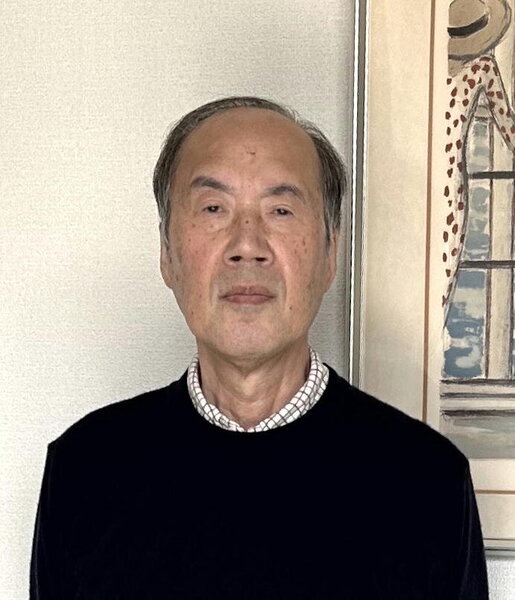- 2025 05/22
- 著者に聞く

「会社の常識は社会の非常識」とよく言われます。ひとりひとりの個人が善良であったとしても、集団になると非常識な意思決定や行動をすることがあります。それがとくに強く現れるのが、異常事態においてです。この、極限状態における集団心理を追求した『集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか 理不尽な服従と自発的人助けの心理学』の著者の釘原直樹先生にお話を伺いました。
――「集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか」とは、聞き捨てならないタイトルです。釘原先生の前著は「人はなぜ集団になると怠けるのか」というタイトルで、そのときのテーマは「社会的手抜き」でした。今回のテーマは何でしょうか。
釘原:このタイトルは、集団には残酷な側面(影)と人間愛が顕在化する側面(光)が存在することを表現したものです。
集団の残酷な側面には、偏見や差別、スケープゴート、暴動やパニックやリンチなどの群集行動など、他にもありますが、本書で取り上げたのは、主に服従や同調行動です。
服従行動は権威者の命令に従い、良心や自由意志をかなぐり捨て、時に非人道的行為を行うものです。
なぜ良心や自由意志を捨てるのか、そのメカニズムの背景にはいくつかの巧妙な説得効果が機能していることが考えられます。例えば、要求を小出しにして、エスカレートさせ、最終的にはとんでもない行動をさせる「スモール・ステップの原理」とか、教師や殉教者などの役割を与えてその気にさせるとか、目的を偽装して正しいことを行っていると見せかけるとか、権威者の信頼性や信憑性を高める情報を与えるとか、様々です。服従行動はそのような様々な心理学的説得の原理が組み合わされた結果により、現れると考えられます。
そして、同調行動は他者の行動に自分の行動を能動的に合わせるものです。もし集団の中に差別や偏見が蔓延していれば、それに同調することは悪に加担することになります。当人はそれに気づいていないこともありえます。
一方、集団の中では人間愛が顕在化し、時にわが身を犠牲にした援助行動が行われることもあります。災害発生時には、被災者は「運命を共にしている」といった感覚が高揚して、彼らの間で助け合いが行われることが珍しくないと言われています。
本書で取り上げた航空機事故に巻き込まれた乗客の証言や行動はそのことを明確に示しています。
結局、本書の内容は心理学的には、「異常事態の服従や説得、同調や援助行動」といったものになるでしょう。
――先生が上記のようなテーマに関心を抱かれたのは、そもそもどういうきっかけですか。
釘原:私は一貫して、集団や人間のネガティブな側面に興味を持ち続けてきました。
その最初のきっかけは大学の教養課程の社会学の授業で取り上げられたフロイトの精神分析学です。この荒唐無稽の考え方(当時はそう思えた)をほとんど信用しなかったのですが、人間の負の側面を面白く物語っていると思いました。心理学を専攻したのはこれがきっかけです。
それから、いくつかの心理学実験の被験者にもなりました。当時(1970年頃)、社会心理学では認知的不協和理論を証明する強制承諾実験が行われていました。この実験手続きは次の通りです。
まず最初に、被験者に1時間ほどネジ回しのようなつまらない退屈な単純作業を課した後に、別の待機中の被験者に「面白い実験だった」と嘘を言うように要請します。
第2にそのさいに被験者に謝礼が支払われます。謝礼は高額のものと低額のものが用意されています。私が受け取ったのは低額のもので、確か生協の昼食券(100円程度)でした。高額のものは1000円の現金だったようです(これは後で実験者に返還するようでした)。
その後、課題の面白さについて評定を行いました。不協和理論からの予測では、高額謝礼の場合は、嘘をついたモヤモヤ(不協和)を「金のために言った」と言い訳ができるために「課題は面白くなかった」と正直に回答することが考えられます。一方謝礼が低額の場合はそのような言い訳ができないので、「課題は結構面白かった」と考え、自分をごまかすというものです。要するに、給料が少ないとつまらない仕事にやりがいを見出そうとしますが、給料が多ければ、つまらない仕事はつまらないと正直に思うという話です。
当時私は「これは常識とズレている」と思いました。学習の強化理論では、報酬が多いほど、行動が促進されるというものがあります。そして常識もこれと同じであると考えられます。つまり、給料が高ければ、つまらない仕事でも、その価値を高く見積もるというものです。
でも、認知的不協和理論では、ここで書いているように、それと逆の予測をすることになります。この強制承諾実験の結果は、不協和理論の予測を支持したということになります。要するに給料が多ければ、つまらない仕事はつまらないと素直に認識するということになります。
私は当時、この体験から「人は自分をごまかしながら生きている」と思いました。この実験も、人間の認知の影の側面を明らかにするものでした。ちなみに、先輩の実験者からは、「君は良い被験者だった。理論通りの行動をしてくれた」とほめられました。
このような体験を積み重ねることによって、研究の指向性がおのずとはっきりしてきたように思えます。その後、社会的手抜き(集団による怠け)や、少数者をやり玉にあげるスケープゴート現象、緊急事態からの脱出や攻撃と混乱、集団同士の物理的衝突、などに関する実験を数多く行ってきました。
本書で取り上げた服従や同調行動の研究も、これらの一連のものと言えるでしょう。
――本書を読むと、先生ご自身による実験、あるいは先生の研究室の学生による実験がいろいろと出て来ます。これらの実験のなかには今となっては実施できないものもあるのでしょうか。
釘原:現在の心理学では、参加者(被験者)の心身に悪影響がないように、非常に厳密に実験の手順が定められています。本書で取り上げたほとんどの実験は、現在の倫理基準では実行不可能でしょう。とくに人間行動の負の側面に関する実験的研究は、その内容が深刻であるほど実施できないという問題があります。実験室実験に代わる何か画期的な方法があればよいのですが……。
その一つとして、本書でも取り上げた航空機事故発生直後の乗客に対するインタビュー研究やタイタニック号遭難に関するアーカイブデータの分析のようなものはありえます。現実に起きた事件や災害を実験室と見立て、そこからデータを得るような努力が必要なのかもしれません。
――本書執筆にあたって、とくに苦労した点があったらお教えください。
釘原:本書では被験者の発言を詳しく述べているのですが、これに関する資料が散逸していて、再構成するのに苦労しました。
大阪大学を退職するときに、ほとんどの本は廃棄しました。そのさい、ついでに服従実験や航空機事故のデータなどが記載されている紙の資料も、いくつかの段ボール箱に投げ込んで全て処分しようと思ったのですが、「自分には何も残らない」という寂寞感を覚えました。これらの資料は現在も自宅の押し入れの中に押し込んでいます。
本書で取り上げた被験者の証言はこの整理されていない段ボール箱の中の資料から再構成したもので、これに相当な時間を費やしました。
退職するときに資料を廃棄しなかったのは、「いつか何かの役に立つかもしれない」というあきらめの悪さであったのかもしれません。
――とくに福岡空港の航空機離陸失敗事故の証言を読んでいると、極限状態での人間の冷静な行動、他者への援助が印象的でした。思わず事故に遭った人々の行動の崇高さに涙しましたが、先生は実際の調査で、どうお感じになりましたか。
釘原:確かに人々の行動は崇高であったと思いますが、当人たちにはそのような意識はあまりなかったように見受けられます。ごく自然に他者への思いやりに満ちた行動や援助行動が行われていました。援助を受けた人も援助者の発言を「神の声」と感じたと証言しています。
人々は極限状態のなか、特別な英雄的行動あるいは卑屈な行動をするわけでもなく、自分の役割を果たしながら行動していたことが印象に残っています。
そこに普通の人々が示した崇高さが顕著に現れていることを感じました。
――最後に読者に、これだけは伝えたいということがありましたらお願いします。
釘原:心理学は実証科学を標榜しているので、研究の再現性が問われます。
私はもちろんそれは重要だと思いますが、心理学のもう一つの役割は、一つの現象を複数の視点からながめること、その視点を提供することだと思います。再現性を厳しく問うほど、結局はありきたりの常識に収斂し、つまらない学問になってしまうのではないかと思います。
哲学者ウィトゲンシュタインの言葉に「間違った思想でも、大胆にそして明晰に表現されているなら、それだけで十分な収穫といえる」(永井均『ウィトゲンシュタイン入門』ちくま新書、1995)というものがあります。私は、この言葉の真意を十分理解しているわけではありませんが、若い人には実験手段の制約が厳しいなか、大胆な思想や理論の構築をお願いしたいのです。