- 2025 05/08
- まえがき公開
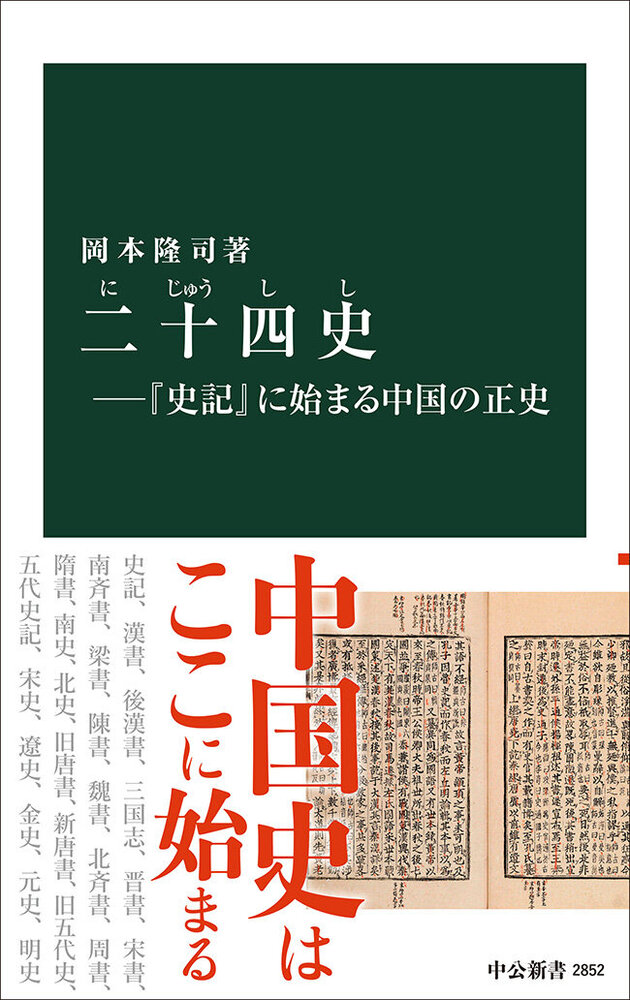
史記、漢書、三国志、後漢書……元史、明史。中国では、前王朝の歴史を次の王朝が国家をあげて編纂することが多かった。これらは「正史」とされ、統べて二十四史と呼ぶ。中国史の根本史料であり、ここから歴史が記されてきた。本書は、正史の起源から現代まで、各書の特徴や意義、歴史を追う。さらに、日本の史書との差異や、清史をめぐる中華民国と中華人民共和国の編纂方針の対立など、時の政治の影響を受けた問題を記す。 『二十四史ー『史記』に始まる中国の正史』の 「はしがき」を公開します。
俗に「中国四千年」「中国五千年」という。いな近年は考古学が発達して、地質学などとも協働するから、マジメに考えても過去をさかのぼっていけば、そのくらいまで達するのかもしれない。
わが日本の隣国は、このように悠久の文明を誇る。しかも古いだけではない。そのうち二千年くらいなら文字の記録、つまり歴史が途切れることなく備わっている。
そこで百年前も、
中国で最も発達した学問は、史学である。世界で史学が最も発達した国は、中国である。二百年前までは、そうだといってよい。
といわれていた。引いたのは当代一流の知識人・梁啓超の『中国歴史研究法』(一九二二年)という著述の一節ながら、稀少な卓説というわけでもない。ごく一般的な認識であって、その影響であろうか、われわれ無学の徒も「中国は歴史の国である」とは、普通に口にする言い回しではあろう。
歴史の古い世界は少なくない。けれども系統的な記録が連綿と残って、具体的な史実をたどれる地域は、かえって稀少だ。中国はそんな希有の一例にほかならない。「史学が最も発達した」「歴史の国」というゆえんでもある。
ここまでなら、ひとまず常識の範囲といってよい。そうした歴史記録の根幹をなすのが、「二十四史」である。さすがにこの名辞まで来ると、おそらく見聞は稀で、なじみが薄くなってしまうかもしれない。
「二十四史」を「正史」といいかえてみれば、どうだろう。少しは見知った語彙ではなかろうか。やや古くて堅苦しい文章ながら、印象的なくだりを思い出した。
野史は書いたところに偽があるとすれば、正史は書かないところに偽がありうる。
引いたのは、石川淳「偽書」(『夷斎風雅』一九八八年)の一節である。民間に流布する「野史」の対が、官製の「正史」というのは正しいし、その正史に「偽がありうる」のも正しい。もっとも「書かないところに」は、歴史家にいわせれば、誤解であり蛇足ではある。正史の「書いたところに」虚偽がないわけはない。
いずれにせよ、これだけで「正史」といっては、およそ不十分である。わが専門の東洋史・中国学では、「正史」=「二十四史」が定式にほかならない。常識にして基礎知識である。
しかし日本人一般の常識的な語彙・認識では、必ずしもそうではない。石川淳の文章も日本の江戸時代の史書を述べたものだから、われわれの常識からいえば、およそ論外である。字面は日中同じでも、どうやら多分にかけ離れた常識ではあるらしい。
「正史」とは中国では、司馬遷『史記』からはじまる史書の系列の総称である。おおむね中国の歴代王朝を単位にして編纂を重ねた書物群で、二千年をカバーする記録にひとしい。それが合計「二十四」ある。しかも「正史」といえば、厳密にはその「二十四史」しか指さない。まずそんな日中の語彙・認識・理解のギャップに注意しておく必要がある。
いくら「正史」におなじみな日本人でも、「二十四史」を知らない向きもあろうし、ましてや「二十四」個々の書名・体裁を思い浮かべるのは難しいかもしれない。まずは全体をみわたすため、一覧にしたてた表を出しておこう。
もっともこれだけでは、やはり詳細な中身までうかがえない。いやしくも外国の歴史・古典であるからには、不案内なのはむしろ当然であって、ギャップはやはり小さくないといえる。
だとすれば、日本人も知るはずの「正史」をあらためて理解、考察するためにも、中国の「正史」、「二十四史」をひろく紹介しなくてはなるまい。小著のあるゆえんである。
なぜ「正史」なのか、そこにどんな経緯と意味があるのか、なぜ「二十四」なのか。そんな基本的なことから、中国の史学・史書、ひいては歴史そのものをみてみたい。
二千年の歴史の果てに、今の中国がある。「二十四史」が連綿と続くのは、実に現在進行形であることも忘れてはならない。
(まえがき、著者略歴は『二十四史ー『史記』に始まる中国の正史』初版刊行時のものです)
