- 2025 04/28
- まえがき公開
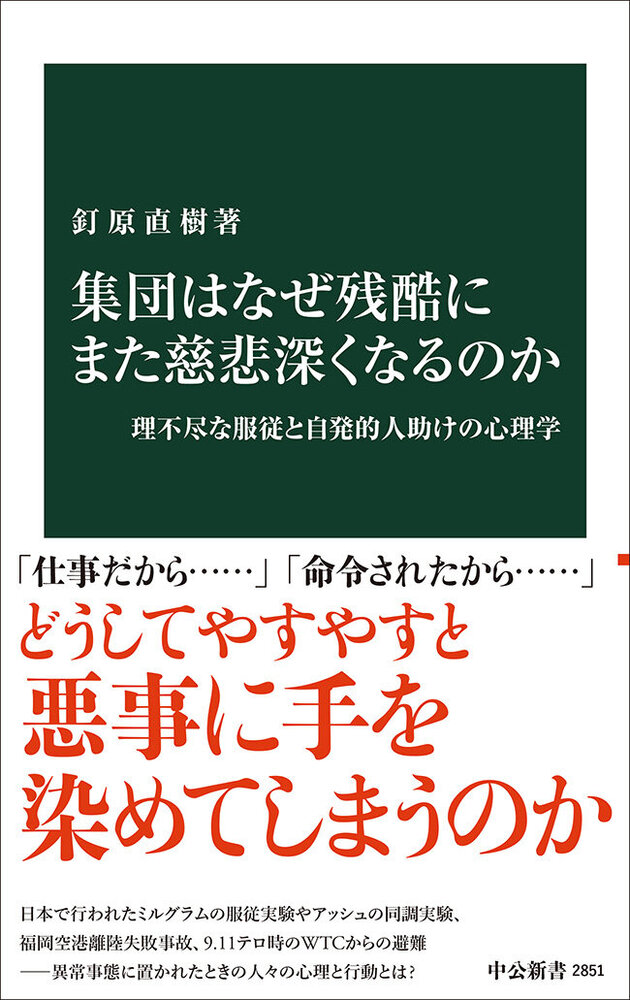
組織の不祥事が報道されると「自分なら絶対にやらない」と思う。だが、いざ当事者になると、個人なら行わない悪事でも多くの人は不承不承、あるいは平気でしてしまう。なぜ集団になると、簡単に同調・迎合し、服従してしまうのか。著者は同調や服従に関する有名な実験の日本版を実施し、その心理を探る。一方でタイタニック遭難など、緊急時に助け合い、力を発揮するのも集団の特性である。集団の光と闇を解明する試み。
『集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか 理不尽な服従と自発的人助けの心理学』の「はじめに」を公開します。
□ ■ □ ■ □ ■ □
はじめに――集団心理の光と影
人はだれでも家族や職場集団、地域共同体、国家など何らかの集団に所属している。われわれは古来、集団に所属することで危険や災害から身を守ってきた。人間を知るためには集団を理解することは不可欠である。
集団は人の生存にとって必要不可欠であるが、それには光の部分と影の部分がある。この光と影が際立つのは極限状況である。フランクル著『夜と霧』はそのことを鮮やかに示している。この本は、第2次世界大戦中のアウシュヴィッツ強制収容所に囚人として収監されたユダヤ人の精神科医による実体験に基づいた手記である。同書の特徴は、飢えや暴力、強制労働による疲労、人間の尊厳を損ねるような理不尽な命令や処置、日常的な死との直面といった過酷な状況における人々の行動が、科学者の視点を失うことなく客観的かつ詳細に述べられているところにある。
同書では監視兵やカポー(収容者の中から選ばれた監視人)のサディスティックな行動と監視される収容者の無感覚、感情の鈍麻、冷淡と無関心、理不尽な同調、それから卑屈な服従行為といった集団行動の影の部分について淡々と述べられている。たとえば1人の収容者が死ぬと仲間が次々に、まだ温かい屍体に近づき、1人は遺体のポケットから泥をかぶったジャガイモを、もう1人は自分のものよりましな木靴を、さらに別の者は上着を、そして結び紐を取り、喜ぶ様子が描写されている。さらにカポーの中には命令に過剰に服従し、ナチスの監視兵よりもかえって残虐非道な行為をする者がいたことについても綿密に描かれている。
一方、そのような極限状況でも仲間同士の助け合いといった集団の光の部分についての記述もある。著者が下水溝の蓋の上に座って休憩していたとき、仲間が逃亡を試み、下水溝に這い込んできたのであるが、著者は平気を装うことで、監視兵の目をごまかして仲間を助けたという。それから親衛隊員の中には私費で町の薬局から結構高価な薬を購入し収容者に与えた者もいたという。またある監視兵は自分に配給されたパンを倹約し、その小片をそっとある収容者に渡したこともあったらしい。このように集団が極限状況に置かれた場合、同調行動や服従行動といった集団の影の部分と、自分の不利益も顧みず他者に尽くす光の部分が顕在化するのである。
心理学の研究分野の中でも、社会心理学や集団力学は重要な領域を占めている。内外の心理学、特に社会心理学関連の書籍をひもとけば服従や同調行動に関する研究が紹介されていることが一般的である。読者は常識に反するその内容に衝撃を受けるのではないだろうか。
それを一言で表現すれば、普通の一般的な市民でも状況によっては大量殺人のような非人間的な行為を行う可能性があるということである。すなわち、特別な悪人が悪を行うのではなく、状況が普通の人を悪に転換させるのである。
ただし、服従や同調に関する研究は、わが国では数少ない。特に服従に関する研究は、研究手法が倫理基準に抵触する可能性があるために実施が難しかった。さらに服従や同調には文化の違いが反映されると想定され、外国と日本では事情が異なる可能性がある。そこで、本書は筆者が国内で行った服従や同調に関する実験を含めて、いくつかの実験を紹介し、外国で行われた実験結果と比較することによって、考察を深めることにする。
一方、異常事態でも理性を失うことなく、人道的に振る舞うことも人間の一側面である。危機事態では、人は自分が助かりたいがために自己中心的、非理性的行動をするというイメージがある。しかし数々の事例研究によれば助け合いが行われ、わが身を危険にさらしながらも他者を救助したり、名誉のために命を懸けたりする場合があることが明らかになっている。
本書では、タイタニック号沈没事故、ドイツ軍戦闘機搭乗員の行動、9・11同時多発テロ時に崩落した世界貿易センタービル内の避難行動、ガルーダ・インドネシア航空機の福岡空港離陸失敗事故などの危機的状況における人々の行動に関する事例研究を紹介することによって、集団の光の部分(理性的行動や助け合い)も明らかにする。
「疾風に勁草を知る」という格言がある。それは人が極限状況に置かれたとき、当人の勇気や美徳だけでなく、邪悪で自己中心的な側面も顕在化することを表している。その意味で極限状況は人間性を試すリトマス試験紙のようなものといえるかもしれない。本書が、そのような状況を読者の方々がイメージすることや、自分の行動を振り返る手がかりになれば幸いである。
(はじめに、著者略歴は『集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか』初版刊行時のものです)
