- 2025 06/26
- まえがき公開
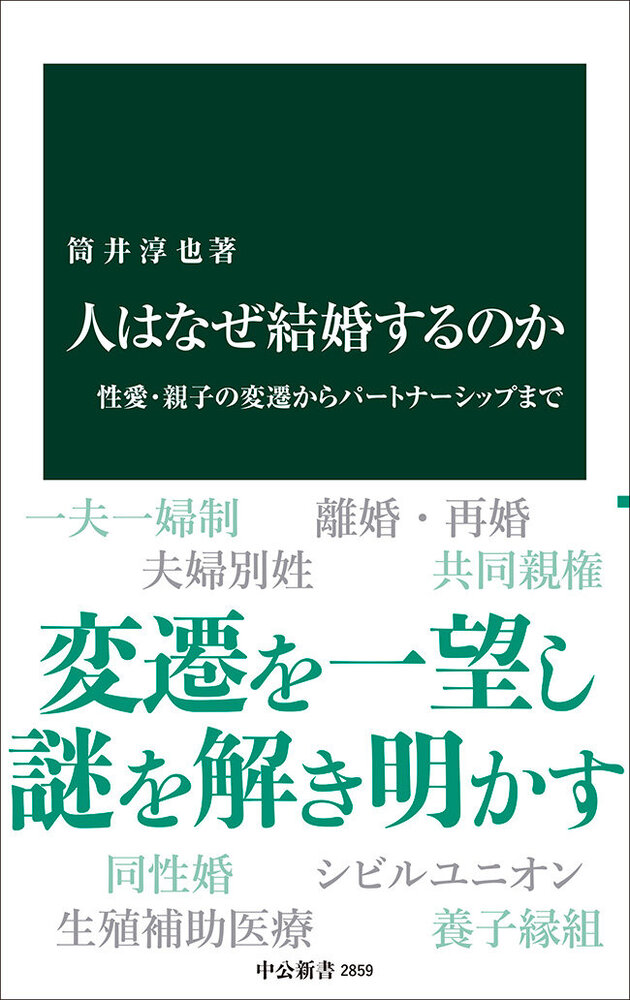
離婚・再婚、選択的夫婦別姓、共同親権、同性婚、パートナーシップ制度、事実婚、生殖補助医療、養子縁組......。いま結婚のあり方が大きく揺らいでいる。リベラル派と保守派に分断され、個々の論点で議論がすれ違うなか、本書では共同性、性愛関係、親子関係の3点で結婚制度の歴史的変遷を根源から整理する。自由化した結婚が抱える「しんどさ」とは何か? 現行制度の本質と、今後のゆくえを展望するための羅針盤。
『人はなぜ結婚するのか 性愛・親子の変遷からパートナーシップまで』の 「はじめに」を公開します。
結婚は、当たり前すぎて説明が不要であるように思えて、その実不思議な関係でもある。
ひとことで言えば、結婚は複合的・包括的なサービス関係だ。何かひとつの目的があって取り結ぶ関係ではない。会社と会社が業務委託などで関係を持つ場合、その業務内容はたいてい特定のもの――自動車の部品の製造であったり、清掃サービスの提供であったり――になるが、結婚となると、家計を共有して助けあうことはもちろん、実にさまざまな要素を含む。たとえば家事、育児、病気のときの看護、情緒的なサポート、レジャーの際の同行などが思い浮かぶだろう。結婚は「一緒に暮らす」という漠然とした趣旨で行われるものであり、関係のなかにさまざまな部分を内包している。
しかし、結婚はその意味や役割を時代に応じて変化させてきたものだ。したがって、どの時代も、またどの社会においても「結婚」の共通理解よりも、むしろ違いが目立つ。
たとえば昔の社会では、結婚と父子関係の確立は強く結びついていた。結婚は父子関係の確立の手段であったのだ。この考え方は、現代人にはいまいちピンとこないであろう。しかし実際、子にしっかりと父を、また父にしっかりと子を割り当てなくてもよい社会では、結婚はその意味が小さかったのだ。
また、昔の結婚概念からすれば、同性婚は「許容されないもの」ではなく「理解されないもの」であった。同性間の性愛の存在は認識されており、地域によっては当たり前に実践されていたものの、それと結婚が結びつかなかった。
結婚は、近代化を通じてその意味を変容させてきた。かつて結婚は、広い意味での「仕事」(家族で行う生産や経営の活動、家族間の関係の構築、権力者の統制)の領域に埋め込まれていた。結婚はそれらの目的のための重要な手段だった。今では、結婚は私的な幸福という人生の目的のための手段のひとつになった。この変化が最も大きなものだ。
ただ、手段と言っても、かなり大きな人生の部分であることに違いはない。なにしろ、すでに述べたように結婚とは、他者と包括的な共同性を構築することである。私生活が深くその共同性に絡み合うため、いったんそれをつくってしまうと離別することが大変になる。
この時点でも、いろいろ謎が生まれる。なぜ、こんな面倒な共同性を他人と構築してしまうのだろうか。また、なぜ政府はその関係を法的に規制し、また権利を与えるのだろうか。なぜこの共同性のほとんどは友人関係ではなく性愛関係なのだろうか。
本書ではこういった問いにゆっくりと答えていく。それと同時に、現代の結婚をめぐるさまざまな変化を、できるだけ一貫した視点から説明することも試みる。同性婚、同棲(どうせい)・事実婚、シビルユニオン(登録パートナーシップ制度など)、離婚法制(無責離婚)、選択的夫婦別姓などである。それと関連する親子関係に関する論点、たとえば共同親権、養子縁組、生殖補助技術(医療)なども、体系的な枠組みのなかで説明する。
多くの家族や結婚に関する議論は、しばしば個別の問題にとらわれすぎて、互いに結びついて理解されていないことも多い。もちろん個別の問題を詳しく理解することも重要なのだが、同時に個々の論点が全体のなかにどう位置づけられるかを確認することも重要である。本書は、できるだけ一貫した視点から結婚をめぐるさまざまな変化や論点を見渡すことを試みる。たとえば同性婚を、結婚をめぐる数百年間の変化の延長線上に位置づけ、それが結婚制度の「革命」というよりは、ある意味でこれまでの結婚制度の変化の「到達点」であることを示す。また、生殖補助技術、離婚と再婚、共同親権といった、一見独立して見える論点は実は問題を共有しており、一貫した観点から位置づけられることを示す。
キーワードは三つである。共同性、性愛関係、そして親子関係である。現代でも、私たちが出身家族から離れて誰かと共同生活を送る場合、ほとんどは性愛関係を軸としてそれを構築する。そうではないケースはほんとうに例外的だ。共同性と性愛関係が結びついていることもあり、成人間の共同性は親子関係と深く結びついている。つまり、性愛関係にある二人が共同生活を営んで子をなすということである。この枠組み自体にはそれなりの歴史的持続性があるものの、同性婚やパートナーシップ制度、離婚再婚の増加、生殖補助技術などは、従来型の結婚が想定しなかったいくつかの課題を突きつける。
本書では、一見複雑に見えるこういったケースのそれぞれを、一貫した視点で説明することによって、見通しを良くしたいと思う。その上で、ありうべき改革の方向性を議論する際に有用なマップを提示することで、無駄な混乱を減らしたい、と考える。
ところで、結婚をめぐる世界の動きを、「自由化」として理解している読者も多いのではないか。年齢と一夫一婦の規制はおそらく残り続けるが、姓や性別の規制が自由化の方向に進んできた。結婚より自立的な関係を維持したい場合、本文で詳述するシビルユニオン(市民パートナーシップ制度)を利用できる国も増えた。離婚も、特定の理由がなければできないという時代は終わり、こちらも自由化しつつある。離婚後の親子関係もそうだ。親権の付与について、一律の規制はなくなりつつある。
ただ、これは決して、自由で過ごしやすい世界の実現ではない。個々人の状況に応じたケース・バイ・ケースの判断が要求される世界であり、ある意味では個人で引き受けられないほど負担の大きい世界だ。結婚するかしないか、あるいは別の制度を利用するか。別姓にするか。別姓になったとき、子の姓をどうするか。子を持つ手段でも選択肢が増えている。生殖補助技術を利用する場合、複雑化する親子関係をどうするか。離婚した場合の親権のあり方をどうするか。
「選べる」ということは、それぞれの段階で総合的な判断や関係する相手との交渉が必要とされる、ということだ。多様化した世界で、私たち一人一人は、ますます多くの課題を自分で引き受けることを求められる。人によっては、こういう課題は非常に面倒だと感じ、いっそのことそういった関係からまるごと撤退したいと考えるかもしれない。
行政や司法も、一律の規制をしてそれで終わりという時代から、広く共有できるガイドラインがない状態で、個々の担当者の適切な判断が要請される時代になる。諸外国を見渡すと、このようなシフトを政府が促しているところもあるが、残念ながら日本の政府にはこういった認識が足りていない。
こういう時代だからこそ、できる限りシンプルな枠組みで変化の方向性を説明することは重要であろう。自由な社会で他者との深い共同性をいかにして構築するか。結婚はその答えのないプロセスの一部分になった。個々の論点にとらわれすぎず、その指針を本書で示してみたい。
結婚の変化について理解することは、一部の理科系の学問のように、ブロックを積み立てるように段階を踏んで達成されるものではない。本書では、若干の繰り返しが入ることをいとわず、らせん状に議論を進めているところもある。同じような内容でも、少し表現が異なればより理解が促されることもあるだろう。結婚に対する社会学的なアプローチの特性として、この点を先に踏まえておいていただきたい。
(まえがき、著者略歴は『人はなぜ結婚するのか 性愛・親子の変遷からパートナーシップまで』初版刊行時のものです)
