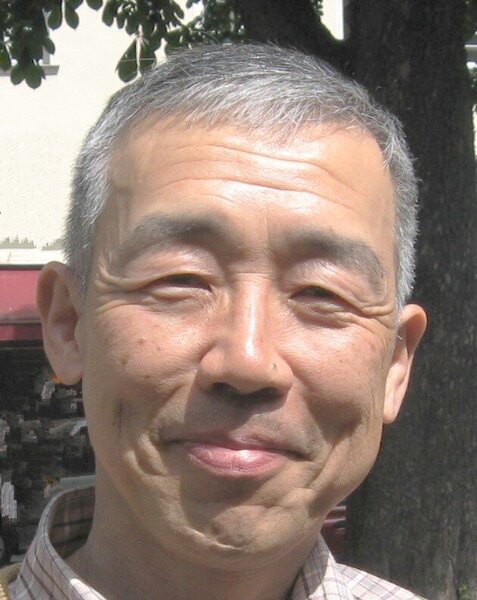- 2025 04/03
- 著者に聞く

昨年(2024年)は、戦後最大の大学改革「法人化」から20年。そんな節目に噴出したのが、東大の学費値上げであり、国立大学の厳しい台所事情でした。「窮状の原因は法人化」としばしば言われますが、竹中先生は同様の改革を進めながらも、研究成果をしっかり挙げているドイツに注目します。国立大教職員はもちろん、私大関係者、学生や保護者まで、大いに参考になるドイツの事情を伺いました。
――先生は中公新書から『ヴィルヘルム2世』を刊行されるなどドイツ史のご専門でしたが、大学論にテーマを移しました。ドイツ史研究の蓄積は現在の研究にどのように役立っていますか?
竹中:ドイツの近現代史を勉強したことで、高等教育のあり方を歴史的な奥行きをもって把握できたという利点はありそうです。しかし、研究の内容というより、研究を通じてドイツの大学や学界の事情に触れられたこと、知人友人を得られたことのほうが大きいように思います。日本の大学制度はもともと、ドイツを手本にして作られたわけですが、教育・研究の実際面ではいろいろな違いがあります。それに戸惑ったり、あるいは好奇心をかきたてられたりしたのが、今ドイツの高等教育事情を調査研究する出発点になっていると思います。
わが国の高等教育論議では、外国の事情といえばアメリカの話ばかりですので、ドイツの事例を紹介することには少なからず意味があろうと思っています。
――『大学改革』では日独の国立大学を比較検証していますが、あらためて日本の国立大学の課題を教えてください。
竹中:ポイントになるのはやはり、経営的な思考だと思います。このところ、国立大学の予算をめぐって各地の学長などからの発言が相次いでいますね。それを見ていると、ほぼ「このままでは今の教育・研究を維持できないから、運営費交付金を増額すべきだ」という意見に尽きます。
こうした意見には、私としては違和感を禁じえません。わが国の財政状況からすると、運営費交付金がこの先永続的に、しかも相当額増えるというのは、どうにもありそうにない話です。そうすると、国からカネが来ないから何もできない、何もしないでよいということになりかねません。
加えて、この先18歳人口が減少するのが明白なのに、現行の業務体制を前提にしていていいのでしょうか。体制見直しとなると学内の抵抗が大きいでしょうが、パイ全体が小さくなるなか、いずれは避けられません。そうであれば、他大学に先駆けてダウンサイジングを敢行し、学費値上げどころか逆に引き下げて学生を確保する、などという発想があってもよいと思うのですが。
ちなみにドイツでも、学長は部局への予算カットなどで、学内からの突き上げを喰う場面が少なくありません。それでも、学内体制の再編などはそれなりに進んでいるようです。といって、ドイツの学長に学内を従わせる魔法の杖があるわけではありません。たしかに大学改革で学長権限が強化されました。ですが、ある有力大学の学長経験者いわく、統率の手段は強権ではなく、「説得、妥協、気遣い」なのだそうです。
――国立大学法人化から20年という節目の昨年(2024年)は、『限界の国立大学』(朝日新聞「国立大の悲鳴」取材班)のような検証の動きがありました。それらと比べたとき、先生の持論の特徴を教えてください。
竹中:最大の特徴は、ドイツなど国際的な動きを視野に入れている点です。国立大学の窮状を否定はしません。ただ注意したいのは、これは他の主要国にも多少とも共通する問題で、しかもそのなかにはドイツのように日本よりも教育・研究の活性化に成功している国があるということです。とすれば、カネがないと窮状をかこつだけでなく、何か工夫する余地があるのではないか――それが私のメッセージです。
また、たしかに一方で、電気代にも事欠く研究室もありますが、他方ではずいぶん大らかなカネの使い方をする部署もあるのです。大学は多数の専門分野からなる複合的な組織で、しかも内部の統制がゆるやかです。こうした大学全体の状況を総合的に捉えるには、インサイダーとしての経験が不可欠でしょう。私は2005年から大学本部で国際化の業務に参画した際(拙著で紹介したドイツの「学術マネージャー」のような職務)、大学改革という大きな流れを意識するようになりました。
――大学の先生方からしばしば耳にするのは、役職や事務的な仕事に追われて忙しいというため息です。そんな現役の教職員に向けて、メッセージをお願いします。
竹中:大学では今後、教員については大学間のモビリティを高め、事務職員については高度専門職化を進めるのが望ましいと考えています。その場合、教員の職務は教育・研究を軸に標準化が強まりますから、事務職員が大学経営の主役になります。ですから、事務職員が経営的力量を身につけ、それを主体的に発揮していくことがいよいよ大事になります。
大学職員の高度専門職化というと、わが国ではともすればURA(University Research Administrator)に関心が集中する傾向があります。しかし、大学が必要とする専門職は、URAのような研究マネジメントに限りません。デジタル化、質保証、広報・マーケティングなどもっと幅広く捉えるべきです。
この動きを側面から支援する意味で、リカレント教育や研修など、高等教育に関する人材開発のインフラを整えていくことが大事です。
――私立大学関係者からの反響もあったようですが、国私間の違いを感じ取りましたか?
竹中:私立大学の方からの反応で目立ったのは、やはり18歳人口減少への危機感です。ですから、ドイツの大学が学生数の減少にどう対処しているのかという御質問がずいぶんありました。ところが、ドイツはまだ学生数増加の局面にありますので、せっかくの御質問にも十分答えることはできませんでした。
私立大学の方にも参考になるとすれば、たとえば学内ガバナンスの問題でしょうか。日本の大学は国公私を問わず規制色が強いのか、ともすれば「全学一丸となって」と、トップによる引き締めに傾く傾向があります。大学という組織には集権的な意思決定構造はなじまないというのが私の持論です。ドイツではその点、現場の活力をすくい上げられるような分権的な仕組みをとっているように思われるので、1つのモデルになるかなと考えています。
――本書の刊行後、高校授業料の無償化が国会で議論されました。「次は高等教育の無償化」という声も聞こえてきますが、ドイツの事情は何か参考になりますか?
竹中:日本は主要国のなかで家計にかかる教育費負担が高いのは確たる事実です。物価高など昨今の経済情勢からしても、とくに低所得世帯への負担軽減は必要です。親の収入の多寡で子どもの教育機会が左右されるのはあってならなりません。私自身、それを痛感しています。私は父を早くに亡くし、母親一人の手で育てられました。当時、国立大学の学費が今のような額であれば、私には大学進学は無理だったでしょう。
ただ、だからといって無償化すべきだとは思いません。そうなれば、ベンツを乗り回す金持ち家庭の子女も、税金のおかげでただで教育を受けることになります。今の日本の財政に、そんなバラマキをする余地があろうはずがありません。無償化ではなく、奨学金や授業料免除、「後払い」制度を整備するなど、低所得者に向けて十分な負担軽減を実現すべきではないでしょうか。
わが国の論議では、大学の授業料がない国としてドイツがよく引き合いに出されます。しかし別段、高等教育は無償たるべしという原則や理念があるわけではありません。現に2000年代半ばには、多くの州で授業料を導入したことがあります。また、今日のドイツでは、学生のうち8人に1人は私立大学に通っています。
今の時点で州立大学で再導入に向けた具体的な動きがあるわけではありませんが、大学が予算不足に悩むなか、今後また議論が湧きあがってくるのではと予想しています。
――授業料の値上げや入試改革、あるいはオンライン講義の普及、生成AIの普及など、教育環境が著しく変化しています。インタビューの締めくくりに、このような時代を生きる学生と保護者にアドバイスをお願いいたします。
竹中:イノベーションは日進月歩で、教育にも深く影響を及ぼしています。昔と違って、若いころ勉強した知識で一生食っていけるという時代ではありません。結果として、大学教育のポイントは、単なる知識習得から、能力(コンピテンシー)獲得へと移りつつあります。とくに重視されるのが、特定の専門分野に関わらない、21世紀社会での幅広い知的活動を支える能力です。これは、フューチャー・スキルなどともよばれますが、その中核となるのがデジタル・コンピテンシーです。
ドイツも例外ではありません。AIの活用能力やデジタル倫理についての教育を提供する大学が相ついでいます。多くは短期的なコースですが、なかには「フューチャー・スキルとイノベーション」という学科を設けたところもあります。
これからの時代は、どの大学を出たか、どの学部で学んだかというだけでは十分ではありません。どのようなコンピテンシーの習得を目ざすのか。それを意識して大学時代を過ごすことが大事になっていくでしょう。
――ありがとうございました。