- 2025 03/28
- まえがき公開
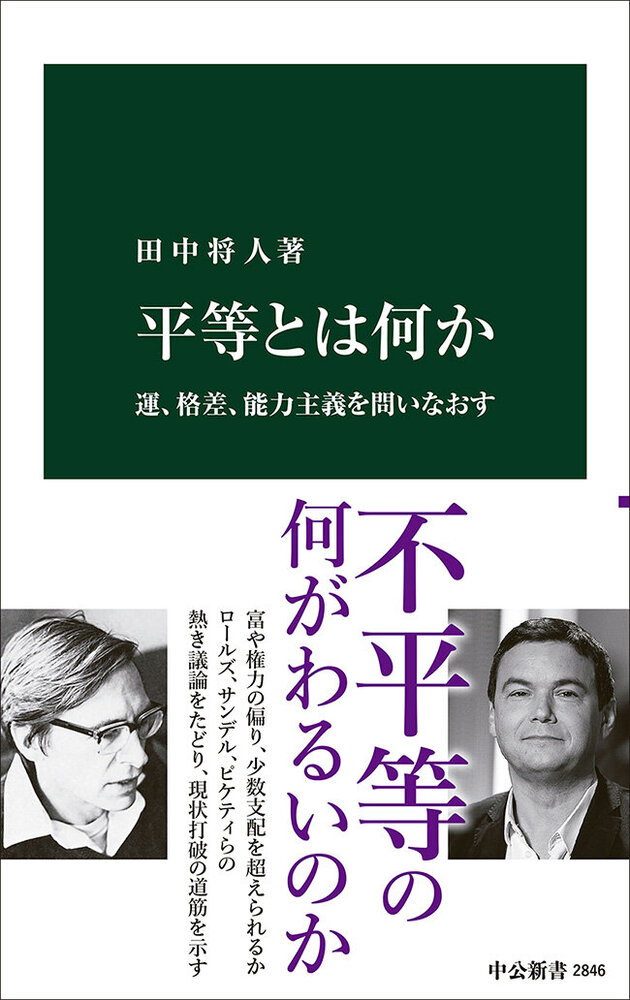
一億総中流といわれてきた日本。いまや格差が広がり、社会の分断も進んでいる。人生が親ガチャ・運しだいでよいのか。能力主義は正しいか。そもそも不平等の何がわるいのか。日本の「失われた30年」を振り返り、政治哲学と思想史の知見から世界を覆う不平等に切り込み、経済・政治・評価の平等を問いなおす。支配・抑圧のない、自尊を下支えする社会へ。財産が公平にいきわたるデモクラシーの構想を示す。 『平等とは何か 運、格差、能力主義を問いなおす』の 「はじめに」を公開します。
かつて「一億総中流」といわれた時代があった。1958年度から実施されている「国民生活に関する世論調査」に由来するもので、関連する設問は以下のとおりである。
あなたのご家庭の生活の程度は、世間一般からみて、どうですか。このなかから一つお答えください。(上・中の上・中の中・中の下・下)
1958年の調査結果は、中の上=3.4%、中の中=37.0%、中の下=32.0%だった。つまりこの時点で7割が中流意識をもっていたが、高度経済成長が一段落した70年代の初頭以降、9割以上が生活の程度を「中」だと安定して回答するようになった。日本経済のパフォーマンスやプレゼンスが高かった、1970年代から80年代にかけての昭和後期を、一般に「一億総中流」時代とよぶ。
筆者の個人史に照らしても、このことには実感がある。1982年生まれの私が小学生になったのは89年(平成元年)だが、その頃はたしかに社会に余裕があったようにも思う。私が生まれ育ったのは山あいの小さな村で、保育所から中学卒業までをクラス替えなしですごした。同級生の保護者の大半は地域の中小企業で働き、休日は農作業にいそしんでいたが、そうした田舎でもパック旅行でハワイやグアムに行くような友達もいた。車で30分の最寄りのデパートはいつも賑わいをみせていた。
小学校の卒業式当日に地下鉄サリン事件が起こった。この1995年あたりを画期として世相が変わったのは子どもながらにわかった。どこそこの父親が職を失ったらしいとの話も一度ならず耳にした。2001年、大学進学のため上京すると、地方と都会の格差をまざまざと見せつけられた。帰省するたびに商店街が急速にさびれていくのも印象的だった。少子化も急激にすすみ、ほどなくして通った小中学校は廃校になった。
かけだしの研究者であった2011年には東日本大震災と原発事故が起こり、日本社会のさまざまな経年劣化を目のあたりにした。三〇代の多くを非正規雇用ですごし、収入の大半は生活費で相殺された。似たようなライフスタイルを送っているだろう人を夜更けのスーパーなどでよく見かけた。一応は生活できていたとはいえ、将来の不安にさいなまれる日もあった。
この30年あまり、経済は停滞し、格差も広がった。このことには各種データの裏づけもある。おそらく読者の方々も、ごく若い人は別として、それぞれの来し方に結ぶ記憶をもっているだろう。かつての日本社会を懐かしく想う人もいるかもしれない。
だが実をいえば、いまなお「一億総中流」は存在することになっている。2022年(令和4年)の調査結果は、中の上=13.9%、中の中=48.9%、中の下=26.2%であり、あわせて89.0%が生活程度を「中」だとしている。9割をわずかに切るとはいえ、数字だけをみればまぎれもなく総中流社会である。だがこのことに、どれほどのリアリティがあるだろうか。
ここにはシンプルな謎がある。調査によれば「一億総中流」なのだが、それはどこか白々しく響く。あわせて訊かれている「あなたのご家庭の生活は、これから先、どうなっていくと思いますか」との設問に対しては、実際、この30年で「良くなっていく」が減少し「悪くなっていく」が増加している。
相対的貧困も深刻なものとなってきている。これは、生存が危機に晒されている絶対的貧困ほどひどくはないが、普通ならできることが貧しさのために困難になっている状態を指す。大まかにいえば、可処分所得の中央値の半分以下で暮らす人びとが該当し、年収で一人世帯だと約130万以下、四人世帯だと約250万以下がラインとされる(2023年)。いまの日本の相対的貧困率は15.7%――一人親家庭に限定すると約50%――である。つまり、6人に1人は貧困であり、人によってはそれでも中流意識を抱いていることになる。
不平等は経済的なものにとどまらない。たとえば国会議員になる人の属性は偏っている。世襲の男性政治家の割合がきわめて多く、貧しい生まれや女性の政治家は少ない(国政での女性議員の割合は1~2割ほどでしかない)。総理大臣などの要職に限定するとこの傾向はさらに強まる。日本経済団体連合会(経団連)のような有力な利益団体についても同様のことがいえる。もちろん政治家はみな選挙で選ばれているとはいえ、何かしらの不平等があることは疑いない。
少なからぬ人びとは自分の生活が、あるいは社会がよくないものになってきていると感じている。自由国民社が毎年12月に発表する「新語・流行語大賞」の2021年トップテンには「親ガチャ」が選ばれている。ガチャとはクジのことであり、子どもが親を選べないことを皮肉をこめて表したスラングである。虐待をする親や貧困家庭のもとに生まれた場合、「親ガチャに外れた」などといわれる。
ただしこのとき、同時に「ジェンダー平等」も選ばれている。性別・性的指向での差別はあってはならないし、不平等は望ましくない。残念ながらそれらはまだ認められるし、ゆえにこの用語が選ばれたのだが、ジェンダーの平等という目標が広まることはわるくはない。
「親ガチャ」には冷笑とも諦めともつかぬニュアンスがあるが、少なくともこちらには前向きな姿勢が認められる。
あたかも私たちはダブルバインド、すなわち二つの矛盾したメッセージに直面して混乱した状態に陥っているかのようだ。一方では平等が崩れてきている実感がありながら、他方ではなお中流意識をもちつづけている。あるいは、不平等の進展をシニカルに傍観しているようでいて、でもどこかでそうした流れを変えなければと思っている……
なぜだろうか。おそらくそれは「平等」と「不平等」について、基準となる考えをもちあわせていないからではないか。もちろん誰もが平等について何がしかを知っている。日々のニュースは不平等を話題にする。しかし、平等・不平等とはそもそも何か、なぜそれが望ましいのか・望ましくないのか、あるいはどうあるべきかについて考えをめぐらせることは、あまりないように思われる。
たとえば「機会の平等」と「結果の平等」というペアはよく知られている。そして大抵は「機会の平等は必要だが、結果の平等はそうではない」といわれる。本人に責めのない事情(家庭が貧しいなど)で深刻な格差が生じるのは問題だが、努力して業績をあげた人とそうでない人を同列に扱うのも問題だ、というわけである。これに対して、本書では、機会の平等は万能ではないし、そもそも結果の平等と対比して捉えるのはミスリードだと主張する。
知っていると思っていたはずの物事ほど、考え直してみると実はよくわかっていなかったことが判明する。そうした試みを自覚的に始めたのが、古代ギリシアの哲学者ソクラテスであった。そのひそみに倣っていえば、本書は「平等とは何か」について政治哲学的に考察しようとするものである。前半であるべき平等の理念を考察したあと、後半ではそれを実現するための「財産所有のデモクラシー」の構想を検討したい。
平等という考えがいくらかでも明瞭なものとなり、読者の方々に何らかの刺激と着想を与え、社会を少しでもよいものに変えてゆくための一助となるとすれば、本書の目的は充分に果たされたことになる。
(まえがき、著者略歴は『平等とは何か』初版刊行時のものです。本文の一部は書籍掲載のものとは異なります)
