- 2025 02/21
- まえがき公開
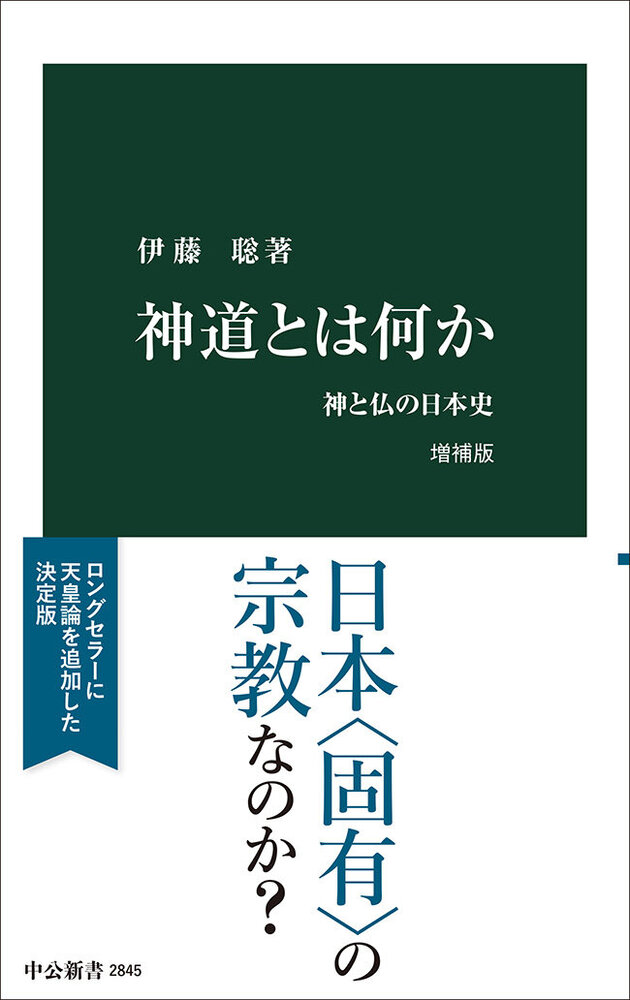
日本〈固有〉の民族宗教といわれる神道はどのように生まれ、その思想はいかに形成されたか。明治維新による神仏分離・廃仏毀釈以前、日本は千年以上にわたる神仏習合の時代だった。本書は両部・伊勢神道を生みだした中世を中心に、古代から近世にいたる過程を丹念にたどる。近代の再編以前の神をめぐる信仰と、仏教などとの交流から浮かび上がる新しい神道の姿とは。補論「神道と天皇」を収録し、新たに補注を加えた増補版。
『神道とは何か 増補版 神と仏の日本史』の 「あとがき」を公開します。
拙著『神道とは何か――神と仏の日本史』が刊行されてから既に12年になる。その間、1年か2年の間隔で版を重ねて、既に第9版にまで来ている。増刷の機会ごとに、気がついた誤記・誤植、事実関係の誤り等を修正してきた。
しかしながら、10年も経つと、単なる字句の直し以上の加筆・修正を必要とする箇所もいくつか目についてきた。その中には、刊行後の早い段階から書き足したく思っていたものや、後になって書き漏らしていたことに気づいたところもある。また、新しい研究が出て、それまでの説明を改めなくてはならないところも出て来た。このように気になるところが増えてきたが、増補改訂を行う機会もなかった。
そうして今年、10刷をという話があった折に、新しい研究の進展を盛り込んだ加筆・修正をしたい旨を申し出たところ、可能であるとの返答を頂いた。ただ、本文自体を大幅に改稿するのは難しいということなので、補注を付して本文内容の修正や追加を行い、併せて補論を付けることにした。
こうして、三十余の補注と補論「神道と天皇」を加えることができた。補注は本文で説明が簡略にすぎた箇所の補足もあるが、多くは初版刊行後の10年余の間に見いだした知見をもとに書き加えたものである。また旧版が、天皇と神道の関係という、多くの人が関心を持つ問題について、正面から取り扱っていないことに気づき補論を立てた。ただし、国学や水戸学さらに近代以後といった、神道がまさに〈天皇教〉になった時期ではなく、その前史ともいうべき中世~江戸前期について専ら解説した。これは、神道と天皇とが多くの点で結びついていなかった中世の状況について述べることで、神道が歴史を通じて天皇と不即不離の関係にあったという通説的理解に修正を求めようとする意図に基く。
さて、筆者は、本書の旧版刊行から今日までの間、専門書1冊(『神道の形成と中世神話』吉川弘文館)、選書2冊(『神道の中世――伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀』中央公論新社、『日本像の起源――つくられる〈日本的なるもの〉』KADOKAWA)を上梓し、その他4冊の資料集(『真福寺善本叢刊〈第三期〉神道篇』2・3・別巻1、臨川書店、『寺院文献資料学の新展開第十巻 神道資料の調査と研究Ⅰ 神道灌頂玉水流と西福寺』臨川書店)を編集した。また、吉川弘文館から出した『日本宗教史』全6冊の編者のひとりとなったほか、監修・編著者として『中世神道入門』(勉誠出版)を仲間たちと刊行した。さらに、本来専門とする中世の枠を超えて、斎藤英喜さんと一緒に『神道の近代』(勉誠出版)を編集した(その斎藤さんは去年、突然として逝ってしまわれた)。その他『日本思想史事典』(丸善出版)の編集幹事として、項目選定や執筆にも当たった。これらの作業を通じて、些かなりとも知見が拡まっていることと思う。
筆者の研究・著書以外でも、ここ10年の間に神道、特に中世神道に関する重要な研究書が陸続として刊行されている。主だったものを挙げれば、原克昭『中世日本紀論考――註釈の思想史』(法藏館)、鈴木英之『中世学僧と神道――了誉聖冏の学問と思想』(勉誠出版)、舩田淳一『神仏と儀礼の中世』(法藏館)、小川豊生『中世日本の神話・文字・身体』(森話社)、Anna Andreeva, Assembling Shinto: Buddhist Approaches to Kami Worship in Medieval Japan(Harvard University Asia Center)、多田實道『伊勢神宮と仏教――習合と隔離の八百年史』(弘文堂)、星優也『中世神祇講式の文化史』(法藏館)等がある。また、本書でも多くを負っている、阿部泰郎・伊藤正義・岡田莊司・吉田一彦氏の諸論考も、一書にまとめられて、近年刊行されている。
これらによって見いだされた新たな視点・論点を、今回の補注では反映させようと努めた。もちろん、必ずしも十分とは言えないのではあるが、神道研究(なかんずく中世)が、今現在も生産的・精力的な研究分野として活動している現況を知ってもらいたいのである。
神道に関する一般読者を視野に入れた概論書・解説書は、拙著刊行後も次々と出版されているが、専門研究の成果を踏まえて執筆されているのは、岡田莊司・小林宣彦編『日本神道史〔増補新版〕』(吉川弘文館)、島薗進『教養としての神道――生きのびる神々』(東洋経済新報社)、佐藤弘夫『日本人と神』(講談社)、斎藤英喜『神道・天皇・大嘗祭』(人文書院)くらいである。他の多くは、昔ながらの神道像の再生産や、主観的な神道論に基づくものであって、そこには最新の研究動向はあまり反映されていない。このような現状において、まだまだ本書の役割は残されていると考え、今回増補改訂を加えた新版を刊行するに至った。
本書の刊行に当たっては、旧版の執筆のきっかけを作ってくださった高橋真理子さんをはじめ、太田和徳さん、黒田剛史さん、そして増補版の編集者の吉田亮子さんには本当にお世話になった。ここに心より御礼申し上げます。
(あとがき、著者略歴は『神道とは何か 増補版』初版刊行時のものです)
