- 2024 10/22
- まえがき公開
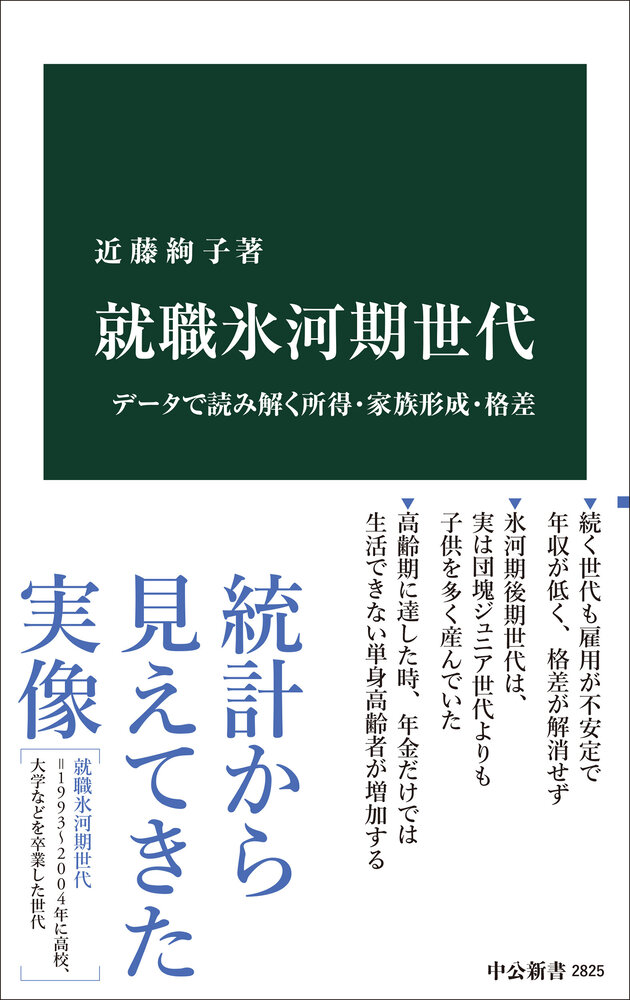
バブル崩壊後、未曾有の就職難が社会問題となった。本書は1993~2004年に高校、大学などを卒業した人々を「就職氷河期世代」と定義し、雇用形態や所得などをデータから明らかにする。不況がこの世代の人生に与えた衝撃は大きい。結婚・出産など家族形成への影響や、男女差、世代内の格差、地域間の移動、高齢化に伴う困窮について検討し、セーフティネットの拡充を提言する。統計から見えるこの世代の実態とは。 『就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差』の 「まえがき」を公開します。
1990年代半ばから2000年代前半の、バブル景気崩壊後の経済低迷期に就職した「就職氷河期世代」は、若年期に良好な雇用機会に恵まれなかった結果、中年期に至る今も様々な問題を抱えている。
この世代は現在でも上の世代に比べて、不本意ながら不安定な雇用形態にある人が多く、賃金が低い。ここまでは、政府の公表している統計データを見ればすぐに確認できる事実だ。しかし、家族形成との関連性や人口動態に及ぼす影響などは、データに基づく客観的な把握がなされているとは言いがたい。
そこで本書は、世代全体をカバーする大規模な統計データを用いて就職氷河期世代の動向を客観的にとらえる。経済的に不安定なので家庭が築けない、正社員でないと子供が持てないから少子化が進む、就職氷河期世代は挫折を重ねてひきこもりになりやすい。なんとなく個人の経験に基づいて語られがちな通説を、客観的に検証する。加えて、女性の働き方の変化や、地域間移動など、これまであまり注目されてこなかった側面にも切り込んでいく。
また、「就職氷河期世代」とひとくくりに言っても、バブル景気崩壊直後の1990年代半ばに卒業した世代と、失業率が戦後最悪の水準だった2000年代初頭に卒業した世代では、新卒市場の状況には大きな差がある。「就職氷河期」という言葉が流行したのは1992〜94年ごろだが、失業率や新卒者の就職率などの指標で見ると、実は2000年代半ば過ぎの景気回復期とそう変わらない。山一證券や北海道拓殖銀行の破綻を契機とする金融危機の影響を受けた1999年卒から数値は一気に悪化し、2000年代初頭にかけて低迷が続く。そのため本書では、1993〜98年卒を「氷河期前期世代」、1999〜2004年卒を「氷河期後期世代」と定義して、区別する。新卒時点での就職状況がより深刻だったのは氷河期後期世代だが、前期世代はキャリアの最初の10年あまりがずっと不景気だったという特異な世代であり、長期的に見てどちらがより問題を抱えやすいかは自明ではない。
就職氷河期世代の苦しい状況をつづった書籍はすでにたくさんあるが、多くは個別の事例を取材したルポルタージュであり、世代の全体像をとらえたものは意外と少ない。ルポルタージュでは、どうしても特に厳しい状況にある事例にスポットが当たりやすく、安易な一般化は世代全体の状況を実態以上に悪く印象付けかねない。一方で、メディアによる報道は、都市部在住の大卒者の視点に偏りがちでもある。本書では意識的に、学歴や地域の間の差異にも目を向けていきたい。
本書の構成は以下のとおりである。
まず序章では、「就職氷河期世代」が学校を卒業した当時の状況を振り返り、就職氷河期世代という言葉の意味を確認する。本書では、「就職氷河期世代支援プログラム」関連の公文書の定義に倣い、1993〜2004年に学校を卒業した世代を就職氷河期世代として扱うが、一般的には定義に若干の幅があること、前述のように1999年前後で状況が変化することなどを説明する。
続く第1章では、中年期に差し掛かった就職氷河期世代の現状を、就業率、給与、雇用形態など、労働市場の指標を用いて確認していく。上の世代に比べてどのくらい収入や雇用形態に差があるのか、そのうちどの程度が新卒時点の景気状況で説明できるのかを、詳しく見ていく。また、これまであまり注目されてこなかった下の世代との比較を行い、2000年代半ばの景気回復期に若年の雇用状況はさほど回復していなかったことも明らかにする。
第2章では、就職氷河期世代の結婚や出産行動について検証する。少子化や未婚化の一因として、不安定雇用の増加がしばしば指摘されてきたが、実はマクロレベルでの因果関係はそれほど自明ではない。特に女性は、経済理論上は、市場で働く代わりに家庭に入ることで、結婚や出産が増える可能性もある。政府による子育て支援政策の拡充の恩恵もあってか、氷河期後期世代の女性はむしろその前の世代よりも、多くの子供を産んできたことをデータで示す。
また、就職氷河期の影響自体も、男女で異なる可能性がある。新卒市場における男女格差の推移や、結婚や出産による退職行動の変化、中年に差し掛かった現在の状況などを、第3章で詳しく見ていく。
第4章では、世代内の格差の広がりや、生活困窮者やその予備軍の動向を見る。就職氷河期世代は、それ以前の世代に比べて、無業者や所得の低い非正規雇用者の割合が増えたことで、所得分布が下側に広がる形で格差が拡大した。また、親に経済的に依存する無業者や不安定雇用者が増え、親が高齢となった後の生活困窮が懸念されることを示す。また、氷河期世代よりも若い世代でも格差は縮小しておらず、将来の生活に懸念がある無業者は増え続けていることも示す。
第5章では、これまであまり注目されてこなかった、都市と地方の違いや地域間移動に焦点を当てる。就職氷河期の影響には地域差があったのか。だとすれば、比較的景気のいい地域へ人口が移動していたのか。また、18歳時点ですでに景気が悪化していた世代では、経済的な制約から東京の大学に進学しにくくなって地域間移動が抑制されていた可能性などについても検証する。
ここまでの現状把握を踏まえて、終章では、いわゆる8050 問題や無年金高齢者の増加など、今後顕在化が予想される問題にも触れつつ、今から何ができるのかを考えていきたい。
(まえがき、著者略歴は『就職氷河期世代』初版刊行時のものです)
