- 2024 10/26
- まえがき公開
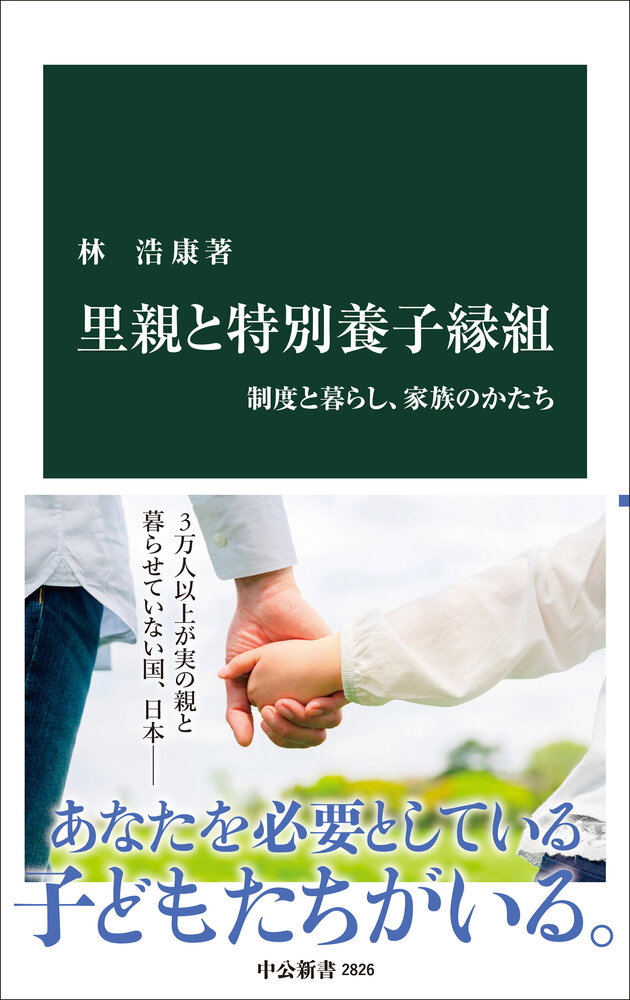
実の親と暮らせない子どもたちはこの国で3万人を超える。彼らの成長を家庭内で支えていくのが、里親や特別養子縁組だ。前者は一時的に育てる公的養育で、後者は生涯にわたり親子関係が持続する。それぞれの家庭で、親と子はどう暮らし、どんな思いを抱いているのか。血縁なく中途から養育する制度の意義や課題は何か。子どもの支援のあり方に長年取り組む著者が、当事者へのインタビューなど多くの事例をもとに解説する。
『里親と特別養子縁組 制度と暮らし、家族のかたち』の 「まえがき」を公開します。
里親や特別養子縁組は、生みの親と暮らせない子どもたちを自身の家に迎え入れて養育する制度である。妊娠・出産を経ることなく、中途から子どもを養育する。そのような特殊性をもつ制度のもとで、どういった子どもたちが、そこでどのように暮らしているのか、これらの制度の意義や課題は何か、社会はそれをどのように支えるべきか、そうしたことについて本書を通して考えてみたい。
里親は、児童福祉制度に基づき、子どもが生みの親のもとに戻るまで、あるいは社会に巣立つまで一時的に養育する公的養育者であり、里親と子どもは法律上の親子関係にはない。一方、特別養子縁組は養親と子どもが法的親子関係を結び、生涯にわたって関係を維持する。その際、生みの親との法的関係は解消される。
ここである家族を紹介しよう。
両親と4人兄弟の6人家族、しかし子どもたち全員が異なる親から生まれたという石井さん家族に出会った。20代の長男(特別養子)、次男(実子)、10代の三男(特別養子)、そして里親として養育する4人目の中学生の男児である。長男と三男は生みの親が育てることができず乳児院で生活した後、この夫妻が里親として我が家に二人を迎え入れ、のちに特別養子縁組をした。小さい頃からそうした生い立ちを子どもたちに告知し、継続的に伝えてこられた。以前、長男と三男の二人にインタビューした際、「日々の生活はどうですか?」という質問に、以下のように答えてくれた。
長男 今そのとき、そのときが一番幸せです。大好きだった祖父の会社が倒産して認知症がんになったり、父が癌になったり、家族の中でいろんな大変なことがありましたが、みんなで助け合って乗り越えてきたので、自分もきっとやっていけるっていう自信はあります。
三男 朝起こしに来るとき、よく「大好きな〇〇ちゃん、早く起きて」と母は言ってくれうれます。そうした何気ないことを嬉しく思うことがあります。
長男 冗談交じりでも「大好きな△△ちゃん」と言ってくれたりします。大好きだよ、愛してるよ、うちに来てくれてありがとうとか、出会えて良かったよっていうのを面と向かって言うんじゃなくて、何気ない会話の中で言ってくれます。だから自然に自分は愛されていると感じるようになってきたと思います。
開口一番「今そのとき、そのときが一番幸せです」と言えることや、日々の生活の中でのことばがけに感銘を受けた。血縁のない中途からの養育だからこそ、意識してそうしたことばがけをしたのかもしれない。里親や養親の重要な役割の一つは、大切にされる体験を子どもに提供し、子ども自身が生きる土台としての自尊心を育むことといえる。
一方で、縁組されたすべての子どもたちがこのように幸せに暮らしているわけではない。2歳のときに乳児院から里親委託された後、特別養子縁組された晃さん(仮名、23歳)は、自身について以下のように語った。
高校2年の冬に父が怒りに任せて突然自分が養子であることを告げました。他の人よりも明らかに時間をかけて勉強しているのにできないので、父が怒って手を上げて、その流れで告げたと思います。そのとき、養子だから、父はこんなに自分に当たりが強かったのかと思いました。ショックはなかったです。「なるほど」というのが一番の感想でした。
僕が大学4年の夏に帰省した際、ゆっくり時間を取って話せるのはこの夏だけと思い、自分の思いを全部話しました。あの人たちが変わってくれるんだったら、ただ悪く言うだけでは、筋が通らないと思いました。この家族に対して安心できないと伝えました。大学2年生のときにメンタルヘルスクリニックに通ってたことも話しました。そのときに「あなたたちに助けを求めたいとは思えなかった」と言いました。でも、父は対応は間違っていないと言い張りました。母は流産したことがあるのですが、そのときに産んだ子って自分のことを思い込んでいて、養子っていうことばを出すだけでヒステリーを起こし、それ以上聞けなかったです。
里親や養親となる者の多くは不妊や流産など何らかの大きな喪失感を抱えている傾向にある。それが子どもに対する過度な所有感や期待を強化することもある。成長とともに親の期待に応えることができず、子どもは自己否定感を抱え、家庭以外の逃げ場や安心できる場がなければ養親子関係の悪化要因となる。養子縁組後は一般家庭同様にみなされ、養親や子どもが求めない限りは、社会的に関与することが困難である。家庭は社会から閉ざされた空間であり、晃さんのように生きづらさを抱える場合もある。17歳という多感な時期に突然養子であることを告知され、家庭内で自身の生い立ちについて聞きたくても、それを口にできない状況は辛く、自身の生きる土台を揺るがす。子ども自身が大切にされていると感じられる養育者に託す責任が社会にはあるが、必ずしもそのような家庭に託されているとはいえない現実もある。家庭養育は養育者が一貫していることが強みだが、一方でそれがリスク要因となることもある。そのことを十分に踏まえて、子どもを託す責任が委託機関にはある。
それでは日本において、里親や特別養子縁組はどのような状況にあるのだろうか。生みの親のもとで育つことができない子どもたち(児童養護施設、乳児院、里親家庭等で暮らす子どもたちの数。特別養子縁組した子どもは除く)は3万3157人(2023年10月現在)、そのうちの約25%の子どもたちが里親家庭で暮らしている。残りの75%強は乳児院や児童養護施設で暮らしている。里親家庭で暮らす割合は、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどに比較して極端に少ない。それらの国々では、親元で暮らせない子どもたちの少なくとも半数は里親家庭で暮らしている。オーストラリアでは90%以上が里親家庭である。施設での養育は極めて限られた子どもたちにしか提供されない。日本はそうした国とは正反対の状況であり、施設養育が主流を占めている。
日本での特別養子縁組の成立件数は、近年500~700件台で推移し、漸減傾向にある。特別養子縁組は里親に比較して、子どもの家庭への帰属意識を促し、永続的な親子関係を確保できるということから、アメリカやイギリスでは、生みの親が存在しない、親族での養育が困難である、あるいは生みの親の家庭に復帰することが困難な子どもたちに対して、積極的に活用されている。
本書は、里親や特別養子縁組の家庭における養育に焦点を絞り、生みの親ではない養育者が子どもを家に迎えて中途から養育する制度の意義や課題について考えることを目的としている。
まず第1章では、親子が別れて暮らさざるを得ない子どもの状況および親や子どもへの社会的支援のあり方について述べ、第2章では、子どもを託す親の事情や現代社会における養育の困難、成育環境が子どもに与える影響、里親・特別養子縁組制度の概要について述べる。第3章では、里親や養親になるための要件や子どもを受託するまでの過程、里親や特別養子縁組に求められている家族像、不妊治療の現実と里親や養子縁組制度との関係等について論じ、第4章では、里親や養子縁組家庭で生活した当事者へのインタビューに基づき、多様な生活体験を明らかにし、その実態や課題について述べる。第5章では血縁のない親子が中途から一緒に暮らし関係形成を図ることの難しさに触れ、親子関係が中途で解消される里親養育不調について論じ、第6章では、子どもの出自を知る権利の意義やその内容、さらにはその権利保障に向けた社会的支援体制のあり方について述べる。そして終章では全章の内容を踏まえ、里親や養子縁組を推進する上での課題について論じる。
本書を通して、里親や特別養子縁組という生き方や制度への理解が深まり、それらがより当たり前の社会となることを願っている。
(まえがき、著者略歴は『里親と特別養子縁組』初版刊行時のものです)
