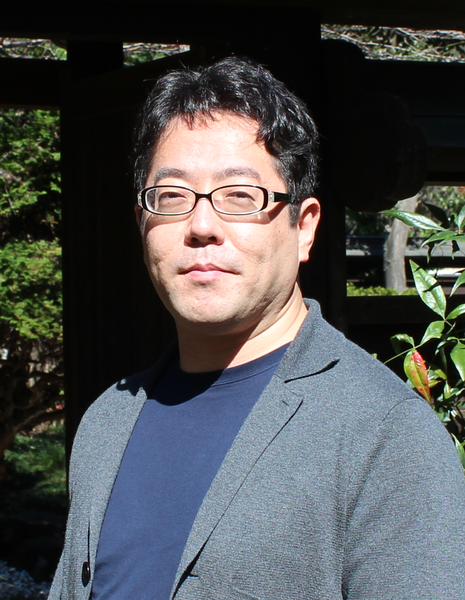- 2020 11/16
- 著者に聞く

Covid-19による緊急事態宣言下、2020年4月に発売された『五・一五事件』。1932年5月15日に起こった首相暗殺事件について、その起点から実行犯たちのその後までを追った作品である。「昭和戦前の分岐点」とも言える五・一五事件だが、今まで精緻に全貌を追った作品はなかった。
刊行後、朝日(保阪正康)、毎日(加藤陽子)、読売(加藤聖文)などの各紙で書評が掲載された。そこでは当時の政局・世論とのかかわりが、現代の政党・政治不信への警鐘とも理解され、高く評価されている。ドキュメンタリータッチの読みやすさも評価され、版も重ね、今秋、サントリー学芸賞(歴史・思想部門)を受賞した。
著者・小山俊樹さんに、ご本について、またこれまで歩んできた道についてうかがった。
――刊行後の反響はいかがでしょうか。
小山:本書の発売直前には、都内などの大型書店が軒並み閉店となりました。一般書では発売前後の店頭での売れ行きが大切と聞いていましたが、これはもう手に取ってもらう以前の問題で。ネット書店でも在庫がなかなか補充されず、たいへんな状態でした。
それでも5~6月に入って、新聞紙上での書評などで好意的に取り上げていただくと、強い反応が寄せられるようになりました。
複雑な事件の経緯やその後について初めて知ったという声や、事件の背景にある経済失策や、軍縮、農村の状況などについて、関心を持たれた方が多かったように感じられます。しっかりと読んで下さっている読者の方が多く、本当にありがたい気持ちです。
――今年度のサントリー学芸賞受賞の一報を聞いて、どのように思いましたか。
小山:これは本当に驚きました。まったく予想外のことで……。なにしろ賞と名のつくものには縁がなく、今後もないだろうと思っていました。これまで頂いた賞といえば、小学校の作文とか、中学校の球技大会とか、そういうのだけで(笑)。とにかくびっくりして、本当に栄誉ある賞ですし、また若手を対象にした激励の意味をもつと聞いて、身の引き締まる思いです。
――なぜ『五・一五事件』をテーマに選んだのでしょうか。
小山:最も意識したのは、断片的な知識から時代の理解へ、という課題です。五・一五事件の名称は、高等学校で日本史を選ぶ受験生なら、知識として持っていますよね。犬養毅首相の名も、政党政治が終わったことも知っているでしょう。ですが、そこで止まれば、事件名は単なる記号にすぎません。
なぜ事件が起きたのか。なぜ政党政治が終わったのか。あえて「なぜ」という正解のない問いを重ねていくと、より細かな史実を見なければわからない。すると必然的に、過ぎ去った時代の光景や、当時の社会の常識と矛盾、さらには事件に関わる人々の心理状態や息遣いまでを、うかがい知るきっかけにつながります。単なる知識が、現在とは価値観の異なる、過ぎ去った時代の人や社会を覗くための導入になるのです。
それは驚きもあり、ある種の思想的な危険さえもともなう、スリリングな歴史の探究です。そうした体験を読者にしてもらうことができれば、歴史を無味乾燥な暗記ととらえがちな発想に、刺激を与えられるかもしれない。それが可能なテーマを私にできる範囲で選ぶとすれば、まずは五・一五事件だろう、と考えたのです。
――『五・一五事件』で最も伝えたかったことは何でしょうか。特にどこに注目して欲しかったですか。
小山:本書はやや欲張りな構成で、大きく3つの問いを設定しています。そのどれか一つにでも注目してもらえれば、興味深く読んで頂けるものと考えました。
第一に、私自身の研究と直接関わるのですが、事件後の政局についての新解釈です。これは、従来から自著で触れてきた内容ではありますが、政党・軍部・宮中や元老の動向をくわしく見れば、政局の帰趨についての天皇の役割がもっと注目されるべきだと考えています。
第二に、これまで不可解とされてきた青年将校側の心理や行動を、理解しやすく説明しようと試みたことです。この点については「テロリストを擁護している」「犯人に同情してしまう」などのご批判も、読者から頂きました。これは全く真っ当なご批判だと思いますし、それだけ本書の叙述が心を揺さぶったのであれば、著者としては望外のことです。
ただ青年将校の心理をわからないものと決めつけてしまうのではなく、いったん理解したうえで、ではあらためてどう向き合うのかを考えることが、五・一五事件に関しては重要だと思っています。
第三に、第二の点と関係しますが国民が犯人に同情し、減刑嘆願に動いた心理についてです。本書では嘆願運動の背後にある、右派団体や在郷軍人系の活動、および海軍部内での対立に注目していますが、それらの動向の大前提として、国民的な同情心の高まりがあります。ここを理解することが、1930年代日本の「空気」を知る上でとても大切です。
もちろん本書は犯行におよんだ海軍将校側の目線を中心に解明しながらも、それだけではない多角的な読み方ができるように描いたつもりではあります。いずれにせよ、多くの読者の方々に考えてもらうきっかけになったものと満足しています。
――執筆するうえで、苦労されたのはどういったところですか。
小山:あまりに著名な事件である割に、海軍将校らが事件に至るまでの経緯、および裁判の経過やその後の経緯などをふくむ、事件の全体像を丁度よいボリュームで描いた文献が乏しく、数あるエピソードの出典も検証が困難でした。
保阪正康『五・一五事件』(1974年)はとてもよい本でした。ただ中心となる愛郷塾長・橘孝三郎は当時の農村を考えるうえで重要な人物ですが、事件そのものを問うときには、海軍将校たちの動向が主体となります。あらゆる文献を検討した結果、結局自分なりに検証をし直すことになり、勉強になりましたがたいへんな時間と労苦がかかりました。
――ノンフィクションのような記述ですが、どういった苦労がありました。また、何か参考にしたり、意識した作品がありましたか。
小山:先ほどの「検証」とかかわりますが、事件を題材としたノンフィクション的作品は多々あります。なかでも読みやすかったのは、中野雅夫『五・一五事件――消された真実』(1974年)でしょうか。同書は存命中だった多数の元将校を含む事件関係者に、念入りな聴き取りをした成果をもとにしており、臨場感のある叙述をしています。
ただし『検察秘録五・一五事件』などの根幹史料が刊行される前の著作であるため、誤りも多く、創作なのかそうでないのか、非常にわかりづらい。やはり著名な事件であることで、ある種の読み物としての脚色が許されてきたのでしょうね。
そこで本書の執筆にあたっては、裁判資料など一定程度の信頼性がおける史料を重視するのはもちろん、臨場感を損なわないようにセリフを積極的に使うことにしました。そのうえで史実性をふまえるために、とくに人物のセリフについては、その現場にいた当事者が語ったり、書き残したものだけを選びました。もちろん、それでも完全な史実とは断定できないのですが……。
事件当日についての説明をノンフィクション的に描いて、冒頭第1章に置くことにしたのは、執筆途中からのアイディアでした。ただこれは本書だけの工夫ではなく、実は本事件を扱った他の作品も大体そうなっています(笑) やはり誰もが聞いたことがあって、でも詳しくは知らない事件現場の再現が、話の導入として効果的だろうと考えました。そして、セリフは決まっているから、それにあわせて説明をできるだけ短く、テンポよく読めるようにすると、あのようになったのですね。
――そもそもなぜ日本近代史に関心を持ったのですか。
小山:どうしてでしょう……もともとは、古代史などに憧れていたのですよ。大学に進んだときも、歴史を学びたいとは思っていましたが、中国に関心が強かったので、東洋史や古代の日中関係史などをやりたいと漠然と考えているだけでした。
ただ、現実に古代史は難しいですよね(笑) 史料もほとんど更新されず、新しい発見など自分にはとても……と悩んでいたところで、近代史であれば史料も豊富で、なんとかなるのではないかと。でも今思えば、受験生のころは近代史が大の苦手で、実のところ五・一五事件と二・二六事件のどちらが先に起きたのか、よくわかってない位の知識量でした。実に浅はかな選択だったと思います(笑)
――なかでもなぜ政党政治に関心を持ったのですか。
小山:これには、大学に入学(1995年)した前後の政治状況も影響しています。1993年に細川護熙(非自民連立)内閣が成立し、これからは政権交代可能な二大政党制が必要で、そうなれば政治はよくなると叫ばれていた時期です。高校生だった私自身はそんなものかな、と思って見ていただけですが、そんなにうまくいくものかな、との懐疑的な想いもなくはなくて。
あまり詳しくなかった近代史のなかで、約8年の政党政治時代があり、その後半期が二大政党の政権交代期であったことに、あらためて興味を持ったのもそのころです。
当時まだ戦前政党政治の研究は、原敬日記などを用いた叙述が中心でした。原没後の二大政党期については、升味準之助さんや伊藤之雄さんなどが言及をしていましたが、史料が乏しいこともあって研究状況は低調でした。
ですがこの時代の政治をみれば、党内派閥の形成が進み、選挙制度が大きく変わり、政治とカネの問題が注目されるなど、現代日本政治の原型ともいえる現象が多々確認できます。それを調べていくなかで、二大政党化にともなう政党間闘争激化の歴史を考えたときに、仮に今後二大政党制になったとしても、それだけでバラ色の未来とは単純に言えないだろう、との思いが強まっていきました。そこで感じたことが、最終的には博士論文(『憲政常道と政党政治』)へとつながっていきます。
歴史とは現在と過去との尽きることのない対話、とよく言いますが、研究をはじめた頃の私の関心は、たしかにそのときの「現在」からみた過去との対話にあったと思います。2020年の今であれば、当時と同じ形での関心は持たなかったかもしれません。やはり作品と時代性は、切り離せないのでしょうね。
――影響を受けた研究者や作家、映画や書籍があればお聞かせ下さい。
小山:実はあまり本を読まないし、映画も観ないので……。大ヒットと言われても、見逃がすことが多くて。人生損してるかもしれません(笑)。どちらかというと、時代を超えるような古典や名作を味わいたいほうです。
それこそ中学生や高校生のころは『三国志』が好きでした。「中公文庫」から出ていた宮崎市定さんの本なども、ほとんど全部読みましたよ。宮崎市定さんは学術的な議論をふまえつつも、大胆な説の提起があって、すっかり魅了されました。なにより、とにかく読みやすい(笑)。適度なユーモアを交えながら、丁寧な解説を易しい文体で施してくれる。
当時、中央公論社にいてのちに作家となる宮脇俊三さんは、学者の書いた文章も遠慮なく直すことで有名な編集者でしたが、宮崎さんの文はわかりやすくて、ほとんど修正しなかったそうですね。当時のことを思うと、本当にすごい。平易な文体は、研究者としても意識してよいことだろうと思います。
――次回作はどういった作品ですか。
小山:いろいろと「筆債」がたまっていまして……。次は長年の課題であった、戦前の政治とおカネの問題を書く予定でいます。めったに史料に残らないところですから、研究も断片的でほとんどない。まだ戦争より前であれば、少しは史料も出てくるのですが。私自身もまだ断片でしか描けていないので、一度まとめなければと考えています。なによりこれは細々とですが、おカネを頂いて取り組んでいる研究テーマなので、ちゃんと還元しなければいけない。オモテのおカネを使って、ウラのおカネの話を書くわけです(笑)
でも政治には付きものの話題ですし、たいへん難しい問題ですよね。国民の政治不信を招く要因にもなりますが、政治をやるのに必要なことも少し考えればわかる。そして戦前くらいの昔の事例であれば、やや冷静で客観的な議論もできるのではないでしょうか。一方的に批判をするだけでなく、どういう在り方が望ましいのか、という問題意識をもって描きたいと考えています。
――これから追っていきたいテーマについて聞かせて下さい。
小山:大きな目標としては、五・一五事件の後にあたる、1930年代の政治史を自分なりに再検証したいと思っています。政党政治崩壊後の戦前政治史については、近年めざましい研究の進展があります。そこに自分なりの視点をもちこんで、新しい方向性が見出せないか模索してみたいですね。
いま意識している視角は、「自由」の問題です。1930年代は、日本における「自由主義」排撃の時代でした。ただそこで言われる「自由」とは、いったい何であったのか。もっと言えば、明治以来の系譜をもつ日本の「自由主義」は、1930年代にはどういう意味での「自由」を守ろうとしていたのか。
戦前オールド・リベラリストの政治家として知られる、斎藤隆夫の書いた遺稿の一節に、次のような文があります。
政党内閣も自由主義の産物であるから悪いと言う。なぜに政党内閣が悪いのか。……五・一五事件を動機として政党内閣が中断せられたのは当然である。しかしこれも我が国の政党内閣が悪いのであって、これをもって政党内閣は自由主義の産物であるから悪いと言う理由にはならぬ。(斎藤隆夫「自由主義に対する妄評」1941年)
斎藤は五・一五事件で「政党内閣が中断」したのは当然だ、カネや情実で人を集めた日本の政党に国政の運営などできない、と言い切ります。それでも、斎藤は政党内閣や「自由」を否定すべきでなく、むしろ「堂々と自由の大旗を立てて邁進すべき」だと主張している。一筋縄ではいきませんね。むしろどうしてそのように主張できるのか、知りたくなってきます。
当たり前に「自由」のある時代には、かえってその中身は見えにくいものですが、否定され抑圧されて、初めて現れるものがあります。この時代の「自由」を深掘りすることで、分かることがたくさんありますし、きっとその知見は、現在の私たちの「自由」の理解を深めてくれるのではないか。新たなテーマには、そんな希望をこめて取り組んでいます。