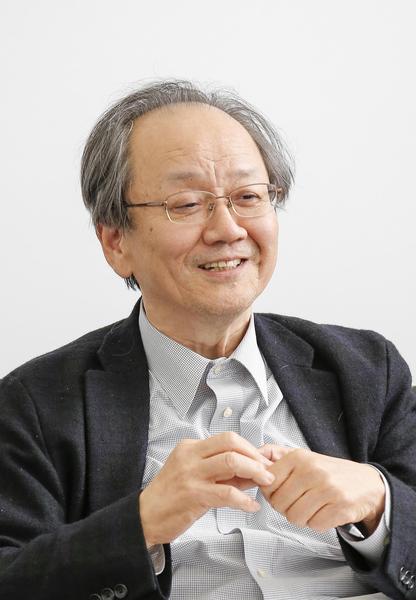- 2019 09/10
- 経済社会の学び方

本連載は加筆・修正の上、中公新書として刊行予定です。連載第4回以降の記事は書籍でお楽しみください。
■概念(concept)について
統計数字の問題に入る前に、社会研究で用いられる「概念(concept)」について触れておきたい。哲学の認識論の問題には深入りできないが、われわれが観察の対象を認識する場合、実は目で見ているというよりも、概念で見ていると表現したほうが適切なことが多い。「概念で見る」ということをもう少し分解すると、概念によって「のっぺりとした現実」を切り分けるということになる。したがって、われわれは概念なしには見ることも考えることも、仮説を検討することもできない。例えば自転車とはこういう形をして、これこれの機能を備えた運搬用具であるという「概念」でもって、見たものを瞬時に(仮説を検定するように)「自転車だ」と認識しているのである。
ここで、「社会」とは何か、「経済」とは何か、「経済社会」とは何を意味するのか、という問いが生まれることはきわめて自然だ。こうした基本的な問いは、それぞれの学問分野で一大テーマとなりうる性質のものであるが、ここで立ち止まってしまうと、これから具体的に取り組もうとしている探求が前に進まない。「社会」は実在するのか、経済の動きは「個と全体」についてはどのような関係にあるのか、などの問いは社会研究の中心的なテーマとして論じられてきた。しかしこうした問題は、研究のはじめから分かるようなものではなく、研究を進めながら次第にその内実が明らかになるものなのだ。つまり概念規定は、研究の到達点であって、出発点ではない。研究の最初に用いる概念は仮説にすぎないとも言えよう。
「経済社会」という概念について言えば、K. ポランニーが言う「社会が経済システムの中に埋没する」(ポランニー『大転換』)状況の社会、という程度の理解で現段階では十分だろう。
■概念を指標に変換する
こうした概念を用いて、一つの経済なり社会を他の経済や社会と比較する場合、あるいは同じ社会の過去と現在を比較する場合、比較を可能にする指標(indicator)が必要になる。この指標を開発する作業が社会研究では重要な位置を占める。
例えば、労働経済学の分野での具体例として、「技能とは何か」、「個人の、あるいは集団の生産性とは何か」という根本的な問題がある。この場合、技能という概念(concept)の内実を知り、その高低を測るにはどのような指標を用いればよいのかを考えねばならない。そこで、技能の内実を二つの角度から把握してその指標を作成する。一つは、どれだけ多くの仕事がこなせるのかという「技能の広さ」、もう一つは、「どれだけ変化や異常に対処できるのか」という「技能の深さ」である。筆者自身、技能という概念を、この二つの指標で測るという方向で研究を進めたことがあった。技能を、「広さ」「深さ」という二つの測定可能な軸で把握することによって、製造業や銀行業の職場での生産性を国際比較することができた(小池和男・猪木武徳編著『人材形成の国際比較』)。
このように、概念を操作可能な数値である「指標」へと変換する作業は、経済学を進歩させるうえで決定的に大きな役割を果たしてきた。マクロ経済学の重要指標である国民所得、国内総生産(GDP)はその代表例である。国民経済計算システム(SNA-System of National Accounts)によって、生産と所得の分配状況や、所得をどこから受け取りどこに支出したか等を知ることができる。経済成長率の指標としてよく使われるGDPはこのシステムの項目の一つである。
GDPという概念は、ある国の国内で、一定の期間内(1年、四半期など)に、新たに生み出された経済価値を測定することで、その国の豊かさを測るために考え出された数字だ。GDPは、その「豊かさ」という概念を、さまざまな仮定を置いて計算している。経済社会全体の「国力」や「豊かさ」を、GDPという測定可能な指標で表現するのだ。この国民経済計算システムが、改良を重ねて精緻化されるのと軌を一にしつつ、マクロ経済学は大きく進歩してきたのである。
■GDPが抱える問題
実際の測定の段階で、GDP概念には正確さに関してさまざまな問題が存在することは、多くの論者が指摘してきた。測定の対象は、市場取引、ないしはそれに擬制された取引である(注1)。 例えば、家庭内の労働で生み出された経済価値が含まれない。同じ家事労働でも、それを主婦(夫)がしていれば、市場取引を経ていないため、GDPには含まれないが、お手伝いさんがその家事労働を行えば、所得を生み出す活動であるため、GDPに含まれる。さらに、生産活動が生み出すものはすべて正の価値を持つと想定されているが、ときには負の財(大気汚染や水質の劣化など)の生産を伴うことがある。その点が考慮されていない、などとの指摘があり、改良への努力がなされてきた。
(注1:擬制された市場取引として、いわゆる帰属家賃(imputed rent)の支払いがある。例えば自己所有の住宅には家賃支払いはないが、市場での相場を用いて自分が自分に家賃を支払っているとみなして家賃収入を計算して計上するのだ。)
もう一つ、このGDPを考えるときに無視しえない(しかし忘れられがちな)問題点を指摘しておきたい。GDPの計算では、多種多様な財とサービスの生産が生み出した付加価値を集計する段階で、生産された物量(Q)に価格(P)をかけたものを貨幣価値額に換算して合計する。例えば、最終生産物の1.8リットルの牛乳と3本の鉛筆をそのまま物量で足し合わせることはできない。それぞれに価格をかけることによって、はじめて円という共通の「元(dimension)」での集計が可能になる。
では単に足し合わせるために「元」をそろえるだけであれば、なぜ「価格」ではなく、「重量」ではダメなのか。簡単に答えれば、市場価格は、その国の市場に参加する人々の満足度を反映しているから、それに物量をかけて合計することが意味を持つのだ。経済学では、市場経済で成立する価格は、あらゆる財やサービスの限界的な満足度との比が一定になるようなところで均衡状態が生まれると想定する。だから(例えば、「重量」ではなく)価格をかけることがその経済に参加する国民の満足度の総和と考えることができるのだ。市場価格が成立していない統制された経済(例えば旧社会主義国の計画経済における価格の決め方など)では、GDPの集計はこうした前提を満たしてはいない。
■栄養士の比喩
出来上がったこのGDPという指標と、経済生活の豊かさ、あるいは人間の抱く幸福感との関係についての反省も必要だろう。GDPの前は、GNPという指標が用いられていた。後者は、日本人が生み出した経済価値に注目する概念であったが、海外での直接投資活動が活発になってくると、GNPはもはや国内の(domestic)経済状況の有効な指標とはなりえない。日本の経済的豊かさを考える場合には、日本国内で生み出された経済価値に注目するGDP概念が適切だと考えられるようになったのだ。
GNPにしろ、GDPにしろ、こうした豊かさの測定のために案出された集計概念の持つ問題点を指摘する次の比喩は興味深い。
GNPをベースにした経済政策は、「乗員・乗客の乗車前と降車前の機関車の重量を測定して、その差を計算し、全員に一つの同じ食餌メニューのベースを作成する栄養士」のようなものだというのだ。(Roger Garrison)
■虚無主義に陥らず、改善を進める
おそらく問題は、豊かさ(あるいは経済的厚生)の代理指標として、GNPないしGDP測定の不確かさと、国民が「自分の生活にどの程度満足しているのか」と自己申告したデータ(self-reported satisfaction)の曖昧さと、どちらが 国の豊かさの指標として「傷が浅いか」ということになろう。大事なことは、「だからGDPなんて意味がない」といった虚無的な姿勢(nihilistic position)に陥ってはならないということだ。
筆者が大学院生であったころ、経済成長論で優れた仕事をしたロバート・ソロー教授が次のような面白い譬えを用いて、こうした虚無主義を厳しく戒めたことを思い出す。
ある町の賭博場に置かれたたった一つのルーレット盤には、誰にでも分かる明らかな歪みがあった。人は「あんな歪んだルーレット盤で賭けなんかできない」という。しかし「この町にはこのルーレット盤しかないんだ!」と叫ぶより他はない。むしろその盤の癖や「歪み」の性質について究明することこそ重要なのだ」と。
GDPという指標の「歪み」の性質を究明するとともに、それを補完する指標を模索すべきであろう。戦後世界の先進工業国でGDPが飛躍的に増大したにもかかわらず、「自己申告された幸福」の程度は少ししか上昇していない(Oswald 1997)。そこで厚生を左右する要素として「所得」以外のファクター、健康、家庭、仕事、社会的信頼の風土などをもっと分析の対象にすべきだという主張が現れた。そして国際比較、過去現在の比較のために大規模なサーベイを行い、観察するのが難しい不平等、環境劣化、インフレや失業への感じ方を直接聴き取るという作業が行われている。
いずれにせよ、アマルティア・セン が指摘するように、貧者は意思能力はあっても経済的な条件ゆえに行為能力(capability)が発揮できないことがある。その場合、「自由な選択」あるいは「自由な行動」を取れない状況にあることになり、個々人の「選択」は、経済的な豊かさを計測するための限られた情報しか与えていない。それゆえ市場で表明された選好(expressed preference)で構成された「市場価格」を用いて集計された「経済的な豊かさ」は再考する必要が出てくる。つまり、自分にとって最善だと思う選択ができない状況で取られた行動の生み出したGDPのような集計量に、どれほどの経済福祉的な意味があるのかという問いが生まれる。
■「無茶な議論」をしないために
社会研究で用いられる数字には次の3種類がある。1)人口、労働力、財政支出、国債残高など概念そのものが数字で直接表現できるもの、2)先に挙げたGDP、あるいは利子率、物価のように、概念を一意的な数字で直接表現はできないが、代理の指数を作成して数字で表現できるもの、3)そもそも概念そのものに量的な要素が含まれないもの、の三種である。
1)については、もともと概念自体が量的なものであるから、特に説明を必要とはしない。数字の中で、概念と指標が一番密接に重なっているのは、人口であろう。人口は自然数で数えられる。もちろん、その社会に人の移動(出入り)があれば、どの時点で(スナップショットのように)人口を数え上げるのか、出生、死亡、転出(移出)、転入(移入)などの人口の動態を知ることも重要になる。人口はどれほどなのか、その中のいかなる割合が労働力として経済的な活動に従事している(economically active)のか、という問いは、まずもって国や社会を研究するときに知っておくべき数字であろう。
2)はすでにGDPを例として説明した通りである。3)のタイプとしては、大学の格付け、「学力」や能力の測定、医療制度の格付けなど、近年 多くの分野で見られる「測定競争」がある。この数字を観ることには慎重でなければならない。
自分が研究の対象とした社会を分析するには、数えられるもの、測定できるものにすぐ関心を向けるのではなく、まずいかなる概念を用いて自らの問いを立てるのか、その後にその概念をいかに数値化するかという方向が正攻法なのである。重要な概念が常に図れるとは限らないし、測れるものが常に価値あるものとは限らない(ジェリー・Z・ミュラー『測りすぎ』)。
一般に、数字で表現するということは、二つの点で重要な意味を持つ。数字を正確に把握していないと、半可通の人が良くやる「無茶な議論」、「勇ましい議論」をしてしまいがちだ。「無茶な議論」とは、数字の裏付けのない、単なる主張(assertion)にすぎないような論である。学問的な議論には常に論証(demonstration)が必要だ。もちろん、「こうありたい」という信条や希望を持つことは大切だが、社会問題に関しては特に、主張と論証をしっかり区別する冷静さが常に求められる。
イギリスの優れた経済政策学者 アレック・ケアンクロス(Alec Cairncross 1911~1998) の言葉、 「主張することは簡単だ。難しいのは論証するということだ(Assertion is easy, demonstration difficult.)」は社会研究の重要な姿勢を述べたものだと言える。
「無茶な議論」や「勇ましい議論」をしないために、細かな数字や事実を正確に知ることは必要だ。根拠のない空想や希望的な思考(wishful thinking)がとんでもない主張を生み出さないよう、足を地につけて考えるために、数字を抑えておくことがまず必要とされる。そのためにも、「ポケット統計」のようなものを持ち、基本的な統計数字をいつでも見られるようにしたいものだ。
■歴史を学ぶ時との共通点
実は、この「細かな数字や事実」の大切さは、歴史の学習や研究についても当てはまる。高校で学ぶ歴史は年代や人名ばかり覚えさせられて、大きく歴史を論ずる力、歴史的に考える力を弱め、歴史は「暗記科目だ」という誤った先入観を植え付けていることは事実だ。私の経験では、欧米の学生の中には、「なぜイギリスで最初に産業革命は起こったか」、「第一次世界大戦はなぜ起こったか」など、唯一の正解が必ずしもない問いについて堂々と論じる者がいる。一方、日本の学生は、歴史というと、薄い教科書にびっしり記された年代や事件名、人名を覚えることばかりに専心しすぎて、歴史学への興味を失ってしまう者がいることは否定できない。
しかしこの「細かな事実の暗記」に全く意味がないわけではない。細かな年代、人名、事件の経緯などについて正確な知識をまず持っていないと、議論が浮ついたものになり、やがて事実をすっかり置き去りにして、「論より証拠」ではなく「証拠より論」に熱中し、自分に都合の良い解釈を主張してしまうことがある。
■「知的誠実さ」と「倫理的誠実さ」
この点に関連して、人間あるいは人間が織り成す社会について「知る」という姿勢には、二つの誠実さが求められることに留意しておきたい。「知的誠実さ」と「倫理的誠実さ」、この二種類の誠実さを区別せず、混同してしまう誘惑が常に存在する。しかもこの二つはときに両立させることが難しい。
知的誠実さというのは要するに、見つかった事実を真理として認め、それをまずは受け入れるということだ。しかし、その真理を、例えばそのまま政策に使うとか、あるいは吹聴するとか、それに特定の価値を与えて無反省に主張をし続けるということは、倫理的な誠実さと一致しないことがある。反対に、倫理観やイデオロギーに染まりやすい人の場合、道徳的な判断を重んずるあまり、真理に目を背けてしまう可能性がある。
こうした状況は自然科学でも発生する。最近の自然科学、特に人間の生命や遺伝に関わる分野では、この実験や作業に人間が踏み込んでもいいものだろうかと思われるような研究もある。倫理的誠実さが重要だという判断に立てば、その知的営為によって得られた真理に蓋をすべきだという考えもありうる。
生命科学の分野において、どこまで学問的に明らかにすべきなのか。どこまで生命自体を科学的な操作の対象にしてもよいのか。こうした問いへの答えは、それぞれの人々が抱く生命に対する信条や立場によって異なってくる。社会研究の分野でも、例えば税や補助金、財政支出や金融政策について、その効果は多岐にわたる。その場合、どの社会グループに対する効果を念頭に政策を打つべきなのか意見が分かれるケースは多い。こうした点について完全な社会的合意に到達することは難しい。おそらくルールを作成しても、抽象的な(理念的な)ものに終始して、具体例に対する実効性は生まれないだろう。とは言え、倫理的誠実さを闇雲に優先させて、知的誠実さを無視することにも問題が残る。
■自然科学的な体裁を目指すマイナス面
もう一つの誘惑として、あらゆる学問はその方法が自然科学的な体裁をとれば、その研究内容の学術的レベルが高いと思い込むことがある。自然科学に似せようとする努力には、厳密さ、正確さを求めるという点で、プラスの面はある。他方、自然科学的な分析のフレームワークに収まる問題だけしか取り上げなくなるといったマイナス面も出てくる。
よく紹介される話として次のような譬えがある。公園の電灯の下で、探しものをしている男がいる。何を探しているのだと聞くと、重要な物を落としたと言う。どこで落としたのか尋ねると、暗闇のほうを指して、「あっちで落とした」と言う。つまり、電灯が照らすことができるところの問題だけに集中して、向こうに重要なことがあることを知りながら、それに目を向けようとしないような態度が生まれる。
また、すぐに役に立つことだけを研究するということは、言葉を換えると、すぐ役に立たなくなることのためにだけエネルギーを使うことになるかもしれない。実利性というのはもちろん重要だが、実利だけを求める学問の世界(アカデミア)が長期的に見てどうなるのか。おそらく根本的な問題に向きあう余裕がなくなり、弥縫策の研究だけに専念するという事態を招くだろう。
■「真理」を求めるか、「真らしい」ものを求めるか
このような留意点を知らされると、経済学はなんと不確かで、厳密性のない学問分野なのだろうか、と感じる読者が多いかもしれない。しかしそうした印象は、学問的な真理に対するバイアスのある反応であって、理性をベースにした論理による推論、あるいは正確さと厳密さを第一に考える近代科学の「外形」「形式」のみに目を奪われていると言わざるを得ない。もちろんこの姿勢は分野によっては不可欠であろう。しかしこの考えは、R.デカルト(1596~1650)以来の、数学を学問の女王とする自然科学の方法のみに限定する狭い考えに陥る危険性がある。
われわれが探求する問いには、数理的な論理だけでは答えられない問題が山のように存在する。したがって論理的に証明可能な「真理」と、論証することのできない「真らしい」物事がある、ということを認めることが大切だ。厳密に論証できるような性質の問題と、正確に論証はできないけれども、これは「真らしい」というような事柄の区別である。
つまり大きく分けると、論証を目的とする学問と、探究し続けるようなタイプの学問があると認識することだ。この点を強調したのはG.ヴィーコ(1668~1744)であるが、この違いを認識しないと、すべてが数量的な論証の学問だと考え、論理的に正しいということだけに目を奪われてしまう。自然科学的な厳密さなり正確さというものを尊重するあまり、問題がそのフレームワークに当てはまる性質のものなのかどうかを十分検討しなくなる可能性がある。
論証の学問は、「真」か「偽」かを明らかに示すことができる。したがって、問題の選び方、問い方には好みや政治的な意識が入り込む可能性はあるものの、いったん立てられた問いに対する推論と結論は、価値中立的な場合がほとんどであろう。しかし、数理的な論証になじまない「問い」や「命題」は、その結論は言うに及ばず、その推論自体にも主観的な判断が入る可能性がある。特に社会研究は「問題」の重要性の判断自体が政治的な主張につながることが多い。政治的な力、世間の評判、承認欲求(善い人だと思われたい、優れていると評価されたい)など、先に述べた「誠実さ」の問題と表裏一体の関係にあることがしばしばあり、政治的な判断と結びやすくなる。
■政治の力から自由な学問はあるか
世間の評価とか政治的な圧力から全く自由な学問というのがあるかどうかという問題をアダム・スミスが論じている。彼は『道徳感情論』の中で、自分の知っている研究者で、グラスゴー大学とエディンバラ大学の数学者の誰それは、自分の仕事が世間から評価されているかどうかということに全く無関心で、気にかけていない。ニュートンも、自分の著作が数年間人々の話題に上らなかったことに対してほとんど関心がなかっただろう。それに比べて、他の学問は必ず学派を形成し、自分の評価と異なる感覚を持った仕事に対して、嫉妬し批判を重ねるというのだ。
アダム・スミスの時代には、自由な学問というのは高等数学と「自然哲学」くらいだと考えられていた。ここで言う「自然哲学」とは、自然の事物や自然現象を総合的・統一的に理解しようとする(ルネッサンス期以後18世紀末までの)形而上学を意味している。現代のように学問が細分化されると、どの学問が「真」を目指し、どの学問が「真らしい」を意識しているのかの分類は複雑になる。
それでも自然科学に莫大な研究費が必要となった時代には、その学問が世間や政治の力から自由であるとは言えないだろう。研究テーマの設定だけでなく、その研究を実行するためにも、研究者の政治力が問われるようになる。実験装置を買う予算をどう獲得するのか、どのような研究者達を組織するのか、など予算獲得のために世間の評価や政治的な力が求められても不思議ではない。世間の評価に全く無関心であることは難しい。
ちなみに、筆者が、「社会科学」という言葉をあまり使わず、むしろ「社会研究」という言葉を使う理由もこの点と関係している。「社会科学」と言ってしまうと、人間も社会も科学的に分析が可能で、分析によってすべての「真」が白日の下に明らかになるという楽観的な見方を生み出しやすい。人間と社会は「科学的手法」で分析できる側面もあることは確かだが、それですべてを理解できるわけではない。こうした意識も重要と考え、「社会研究」とよぶことにしている。筆者の言う「社会研究」と密接に関係する歴史学や思想研究が科学的方法だけでは探求できないことが示すように、「真らしい」ことを探求する学問には、自然科学を念頭に置いた科学という言葉はなじまないと考えている。
(以下、次回。参考文献は、新書刊行時にまとめて表示いたします)