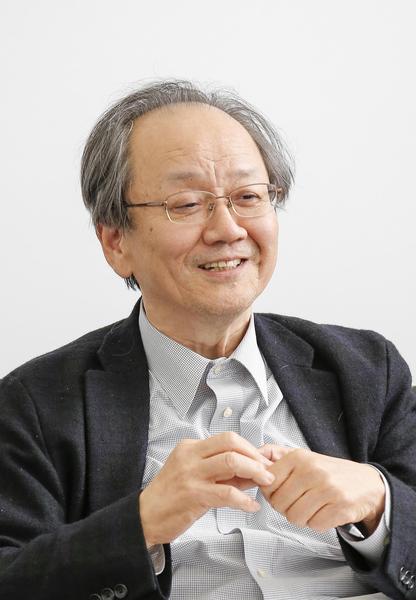- 2019 07/31
- 経済社会の学び方

本連載は加筆・修正の上、中公新書として刊行予定です。連載第4回以降の記事は書籍でお楽しみください。
■連載開始にあたって――「燻製ニシン」にまぎらわされず
この連載の目的は、社会の経済構造やその動き方、そこから生まれるさまざまな問題の改善や解決を考える者は、何を知っておかねばならないかを示すことにある。研究や調査分析と言われる活動に近道はない。すぐに「解」がポケットから差し出せるような問題は少ない。ほとんどは、その前提となる社会の「文法」を先人の知識から学び、分析に必要な技術や技能を少しずつ積み重ねていくことが要求される。
それは楽器演奏にも似たところがある。美しいバイオリン演奏に魅せられた人が、バイオリンを手に入れてすぐに同じように演奏できることはない。良い演奏家になるためには、その前提となる技術的訓練に時間をかけて積み重ねなければならない。技術を身に着けるだけではない。良い演奏を聴いて、美しい演奏とはどのようなものかを、比較しながら考え、そして自分が何を表現したいのか、理念の自己確認が必要になる。
そうした理念の自覚は必要だが、「行き過ぎ」は避けねばならない。美しい音楽、よい音楽とはなにかを知的に自覚することは重要だが、「美」とはなにかという問いだけに拘泥していると、いい音楽家にはなれない。根本的な問いは無視してはならないが、その問いだけに集中することはあまり生産的ではない。
これから論ずる経済社会の問題を考える場合も、経済、社会、資本などの言葉が定義なしに出てくることがあるが、はじめの段階では、その意味を厳密に理解し定義しようとすることにこだわらない方がよい。「経済社会」という言葉は、その中に経済的関係が深く染み込んだ社会という程度に理解しておけば十分であろう。さらに具体的、かつ正確な意味は、研究や調査の経験を積み重ねることによって次第にその意味が少しずつ現れてくるはずだ。「自然科学」とは違って、「社会科学」の分野では、こうした基礎的・根本概念を学びの初めの段階から定義することは概して難しい。定義できたとしても、抽象的過ぎてイメージが伴わない空虚な理解に終わる場合がある。
定義と本質を云々することは、いわゆるred herring(燻製ニシン)となりかねない。狐の通った跡を燻製ニシンを引いて横切ると、狐のにおいが消えて猟犬が迷う。概して「本質論」はred herringになることが多い。経済社会などの問題には、概念を定義して定理を命題として打ち立て、それを証明するというような数学的な論の進め方は適さない。
したがって余計な「学問的」な鎧を取り払い、しかし言葉の意味を常に問いつつ、読み進んでいただくことをお願いしたい。
■方法論に潜む矛盾
これから社会研究をしようとする人々に、いきなり「方法論」を説くことにはある種のためらいがある。方法論を体得するということには一つの矛盾が含まれているからだ。この重要な点を、すでに2400年前にアリストテレスがいみじくも次のように表現している。
「あることをおこなうためにはそれを前もって学んでいなければならないが、それが学ばれるのは実際におこなわれることによってである。ひとは建築することによって大工となり、琴を弾ずることによって琴弾きとなる」(アリストテレス『ニコマコス倫理学』1103a32-33)
確かに、医学を勉強したから、すぐ医者になるというわけではない。多くの患者を診察し、たくさんの症例を知ることによって一人前の医者になる。方法論を知ったからと言って、すぐよい研究ができるわけではない。研究をすることによって、徐々に研究の仕方が分かるというものだろう。経済学や政治学を学んだからといって、現実の政治や経済が分かり、適切な対策をすぐ打ち出せるものではない、ということもこの点に関係している。
また、自分が答えを探したいと思う問いを一つの命題として「定式化(formulate)」し、そのために必要なデータを集め、データの質を吟味し、推論の手段(統計的手法か、文書資料か、フィールドワークか等々)を選んで実行していけば結論が得られ、研究は完了するというわけではない。先行研究に、何を、どれだけ付け加えることができたのかを示す必要がある。さらに、得られた結論は常に暫定的な性格を持つから、後続の研究者達によって修正が加えられ、より一般的な結論へと発展することを前提としなければならない。したがって、分かったことと分からないことをしっかり区別しなければならない。さまざまな試行錯誤(trial and error)と改善のサイクルによって、次第に真実が明らかにされていくのが常である。
このように考えると、初めから具体的な素材のない「方法論」を説くことは、外側だけが強そうな鎧を着た「張り子のトラ」を作るようなことになりかねない。したがって本章で述べることは、あくまで、社会研究を進めるうえでの「一般的な留意点」であることを念頭に置いていただきたい。
■「問うこと」の重要性
国や社会について少しでも理解を深めようとするとき、ひとはまず何に注目するであろうか。全体を一挙に見て取ることはできないから、その対象のどこに注目して観察するのかを選ばなければならない。しかしそのためには全体についての大体の知識が必要になる。全体を知るには部分を知らなければならない。しかし部分を知るためには全体についての知識が必要になる。これも一つの矛盾のように見える。したがって何を、どう観察すればよいのか、それを選び出すのは言うほど易しいことではない。
ただ、現実にはほとんどの場合、すでに絞られたテーマや問いを外から(外発的に)与えられるか、あるいは流行に影響されて問題を設定することが多い。内発的な関心として「何を選び出すか」をはじめから迷うことはあまりない。しかし自分がそもそも何を知りたかったのかを「自己確認」することの重要性、上手く問いを設定することの難しさは、強調してもし過ぎることはない。柳田國男が言ったことであるが、日本人は「学問」というと「学ぶ」ことに重きを置き、「問う」ことを重視しない。しかし「何を問うのか」は簡単ではない。
わたしは、大学院生に「論文のテーマを、答えられるような形に絞り込み、問いが一つの命題として定式化(formulate)されれば、仕事の半分は済んだようなものだ」とよく言った。何を知りたいのか、「内発的な」自分の問いは何なのかを確認しておかないと、社会研究を「持続と蓄積」の精神で継続することはできない。どうしても、ひとは流行や他人の関心に引きずられ、いつの間にか自分本来の関心や問題意識を忘れてしまうのだ。
もちろん、流行のテーマを取り上げるのにはそれなりの利点もある。多くの人が重要な問題を取り上げ、競争と協力をバランスさせながら集中してその「解決」に取り組む「共同研究」は、社会研究にも必要だ。ただ、その場合でも、自分の将来の学びの肥やしになるように、もともとの自分の関心を見失わないようにしたい。
■現場の空気を吸うこと
自分が関心を持った社会の一局面を知るためには、その場所へ行ってそこの空気を吸うことが一番であろう。もちろん、すべての分野にこのことが当てはまるとは限らない。知人のドイツ文学者は、生涯ドイツに行かなかったが、ドイツ文学の優れた翻訳と研究で同分野の研究者達から尊敬されていた。人間であること(humanitas)に本質的な違いがないとすれば、人文学の場合にはそのようなケースはありうるだろう。
能因法師も、「都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関」と詠んで、遠くの白河の関のことを都にいながら詠んだのでは説得力がないと考え、秘密裡に自宅の縁側で日に当たって日焼けして、「みちのくにのかたへ修行のついでによみたり」と言ってこの歌を披露したという。真偽のほどはわからないが面白い話だ。
それでも、地域研究(regional studies)など、外国社会を研究する者にとって、その国の空気を吸うのはやはり必須であろう。「百聞は一見に如かず」である。日本を知るには日本をくまなく歩くということが必要だ。昔の人文学や社会を研究する者は、「足で学んだ」と言われる。例えば、菅江真澄、柳田國男、宮本常一など、民俗学で重要な仕事をした人はみな旅をして、その社会を観察しながら、試行錯誤を重ねつつ自分の仮説を打ち立てるという発見的な(heuristic)手法を用いた。現代経済の研究にも現場を観てみるという精神はある程度必要だ。
しかし対象が「日本」のように広くなればなるほど、「そこへ行く」ことの意味や益は希薄になる。また、こうした丁寧な観察手法は、大きな誤りを防ぎ、リスクの少ない研究方法ではあろうが、膨大な時間とお金がかかり、現代ではなかなか実行し難い。さらにその観察が、どれほど一般化できるのかという大きな問題を抱えている。特に巨大で複雑な構造を持つ現代の産業社会の問題を研究対象とする場合、個別企業における「観察」が、どれほど多くのケースに当てはまるのか、その意味が曖昧になるおそれがある。
この点については後に改めて取り上げたい。「ひとつからすべてを学ぶ」(Ab uno disce omnes -ヴェルギリウス『アエネーイス』第2巻)ということの意味を、例えば聴き取り調査やフィールド・ワークの場合を例としつつ考えることにする。ちなみに文学などは「一つの例示がすべてを語りうる」重要な例となり得ることは確かであろう。
■見えないものの観察
自然科学の研究では大量の観察は大前提・不可欠であり、最も重要なステップを構成する。現代の自然科学の多くの分野では、人間が日常生活で観察できるような対象そのものを直接観察するのではなく、超ミクロの世界の対象に関心が移り、実験室内の電子顕微鏡の世界になっていると聞く。分子レベルの研究をしている植物学者に、路傍の雑草の名前を尋ねても、「何ですかね」と言われることがある。それでも実験室の中であれ、目に見えるものを観察するという作業の重要性には変わりがない。
それに対して、人間や社会の研究は心理や人間の関係性を問題とするゆえ、ほとんどの場合目に見えない世界を相手としている。経済で論ずる「物価」も「GDP」も「貿易赤字」も、可視性を持った概念ではない。これらの概念の背後には、諸商品の価格が高騰している市場(いちば)の光景、外国製品が多く出回るデパート、大勢の日本人観光客(サービス貿易の「輸入」)でにぎわう国際空港などを見ることはできる。しかしそれは、物価や貿易赤字そのものを見ているわけではない。そこから抽象される前のいわば「概念化される前の原風景」を見ているにすぎないのだ。
政治や経済社会の研究は、多くの場合、具体的に見えないものを観察しなければならない。関係性自体は目に見えないから、現場に赴く「観察」という経験知の獲得方法は軽視され、忘れ去られることが多くなる。そこでわれわれの問いが、事実から遊離したものにならないようにするためには、聴き取り調査(フィールドワーク)という重要な手法がある。この手法については、後で改めて説明を加えるが、フィールドワークをも「観察」に含めると、「観察」は社会研究でも重要な手法である点では自然科学と変わるところはない。
■文字資料の価値の判断
社会研究のために、しばしば採られる手法として、文書や歴史資料を用いる方法がある。社会と経済を調べる場合、その社会の基本構造を規定している法律を知ること、その社会の歴史的変遷を知ることは大事だから、こうした方法は不可欠と言ってもいい。「書かれた資料」を用いるときには、その資料の信頼性についての「資料批判」がまず必要になる。書かれているからと言って、それをそのまま信用するわけにはいかない。
加えて、概して大事なことは文字として残されてはいないものである。法律やルールで書かれていることと、実際の慣行(practice)が乖離していることは意外に多いのだ。書かれた制度やルールがあるからと言って、その社会がそのルール通りに動いていると信じることはナイーブというものであろう。そうあること(Sein)と、こうあるはずだ(Sollen)を混同してしはならない。
歴史上の文書資料については、日本中世史の泰斗・林屋辰三郎が、「資料の価値というのは、『現地性』と『同時性』という二つの軸で判断できる」と指摘している。「現地性」というのは、対象と同じ場所でその史料は書かれたのかどうか、「同時性」というのは、対象と同じ時に書かれているかどうかということだ。この「現地性」と「同時性」の二つの軸で判定して、その基準に近づけば近づくほど、史料としての価値が強いとして、林屋は次のような古代史の例を挙げている。少し長いが引用しておこう。
「古代史の文献史料といえば、『古事記』や『日本書紀』があるでしょう。これらは、日本という広い意味での「現地性」を強く持っている。しかし、「同時性」という基準からすると、これらの完成されたのは八世紀です。まあ、六世紀ぐらいのところから信頼できるということですが、少なくとも「遠古代」に関しては、これらの「同時性」は非常に弱いといわねばなりません。
ところが、もうひとつの『魏志』倭人伝はどうかというと、これは「同時性」はかなり価値が高いけれど、「現地性」はまったくだめなんです。たとえば、この中に倭国の風俗の記事がいろいろ出てくる。(中略)結局これは、書いた人の頭の中に、海南島と倭とがだいたい同じ緯度だという考えがまずあって、それで話を進めてきただけのことですね。だから、海南島の風俗ではあっても、倭国の風俗ではないわけです。
『魏志』倭人伝とか『後漢書』というと、今は、文献として最高に信用が置かれていて、もっぱら、それだけで議論が進められてゆくという傾向がありますが、こういう、非「現地性」という盲点があって、片や、『古事記』や『日本書紀』には、非「同時性」という弱さがある。その両方をうまく操作して、その操作のしかたに考古学や民俗学の力を借りて、歴史家は「同時性」と同時に「現地性」をも満足するような史料を頭の中で作り出してゆかねばならない。
『魏志』倭人伝の語句をいくら詮索しても、それは『魏志』倭人伝の文献としての研究にはなるでしょうが、そのままそれが、日本の歴史を解明したことにはならない。」 (「神と王の遍歴〈その1〉」『野性時代』1975年2月号)
林屋辰三郎のこうした基準は、文書資料の価値、その信用度を判断する際の重要な目安を与えてくれる。われわれはどうしても、書かれたものを信じやすい。活字として固定化した情報に対して、闇雲にそれが真実だと思い込んでしまう傾向がある。しかしよく考えると、「書かれたもの」が、一体誰が(どのような社会的立場にある人物が)書いたのか、誰を読み手として想定していたのか、そもそもどのような目的で書かれたのか、などについて十分検討しておかないと、ほとんど価値が無いような文書資料を論拠に議論しかねない。中には事実の発見を妨げるような虚偽が含まれている文書もあるのだ。
制度やルールについては理念を述べた文書が少なくない。法律にもその理念や目的が冒頭に掲げられている。しかしそれが実際にその法律が文言通りに運用されているという保証はない。その運用は別問題なのである。社会研究にとって重要なのは、「実際にいかに運用されていたのか」という点であって、書かれた理念や目的を、実証的な分析にそのまま使うことはできない。
(以下、次回。参考文献は、新書刊行時にまとめて表示いたします)