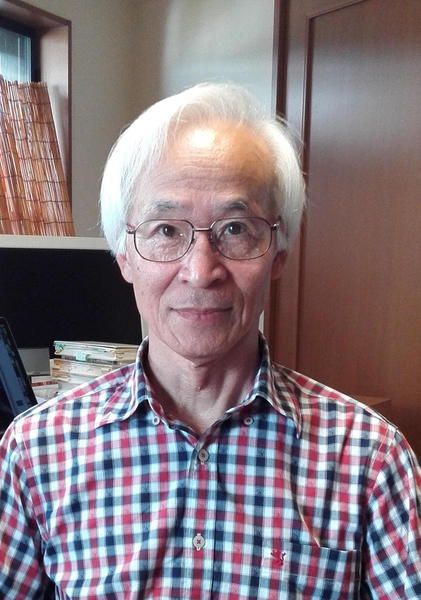- 2017 07/27
- 著者に聞く

私たちは普段、見ることや触れることを特段意識しないのではないでしょうか。細胞たちはうまい具合に連携し、細菌などの外敵からカラダを守ったり、脳が認識をする手助けをしたりしています。人間の全一性を支えているカラダの働き者・細胞が主役の『カラダの知恵』を上梓された医師の三村さん。細胞同士の情報伝達の仕組みから、直感やプラセボ効果など心の働きまで、やさしい語り口で解説する本書の執筆の背景などをうかがいました。
――はじめに、本書の執筆の動機をお教えください。
三村:外科の手術はケガのようなものですが、そうしたケガに対するカラダの反応の不思議さを感じていました。
たとえば虫垂炎、いわゆる「盲腸」のような小さな手術であっても、手術がうまくいかないと、ずっと高熱がつづいて患者さんはぐったりしたままでいます。
反対にどんなに大きな手術、たとえば食道癌の手術でもうまくいくとすんなりと快方にむかいます。
このことは手術の大小にかかわらず、反応の道筋はおなじであり、反応の途中でなにかがちがうと回復のしかたがまるでちがうことを示しています。
そしてその「なにか」とは「細胞たちのコミュニケーション」にヒントが隠されているのだろうと考えました。
また、手術のまえやあとで、人によってこころの動きがちがいます。キモチがカラダにどう影響するのかについてもまとめたいと思っていました。
実際に動物を使って、手術後にカラダのなかでどのような反応がおき、それを軽くするにはどんな方法があるかという研究をしてきました。
そうしていくうちに、カラダの反応は実に整然としていて、都市機能のように合理的であると気づきました。
このことを専門領域以外の人たちにつたえたいと思い、執筆しました。
――執筆中に苦労したことはありますか。病院での診療などと両立するために、どのようにスケジューリングされていたのでしょうか。
三村:病院勤めは、区切りがあってないような毎日で、それは大学を卒業してからずっとそうでした。
日中は診療や院長としての業務があります。会議の準備などもありましたので、原稿に向かうのはいつも早朝でした。
調べものに結構時間がかかり、ひとつ不明のところがあると信頼すべき本を探りあて、それら数冊を1ヶ月以上かけて調べる、ということを繰り返していました。
平日は病院と原稿の執筆に時間を費やしていましたので、土曜日のお昼になると解放感はひとしおでした。これで「きょうの午後とあす一日は自由な時間なんだ」と思い、ひと息ついていました(笑)。日曜日は松本の里山を歩き、気分を変えました。そうでないとつぎの一週間がしんどかったですね。
――お忙しい中、ありがとうございました。
三村:しかし、そういった環境も執筆するうえでプラスに働きました。雑事でがんじがらめになっていたからこそ、本書に紹介した細胞どおしのコミュニケーションやカラダのしくみをかえって強く意識したようです。無意識に人の集団と対比することが癖になっていました。
どの職場でも抱えている問題は似ていると思います。多くは人間関係であったり、リスクマネジメント上のことや経営上のこと、そして個人のレベルでは充足感であったり待遇面でのことなどです。
「なんでうまくいかないのだろう」と悩むとき、カラダのしくみがヒントとなって解決の糸口となることがありました。
どのような職場でも中枢からの指令が末梢につたわり、その反応が中枢へととって返し、それに対して適確な指示がまた出ていきます。
指令の意味を共有し、末梢で困ったことがおきれば自律性をもってその場で解決していく、そんなカラダのしくみが大いに参考になりました。
本書の5章で触れた、相手の顔の表情をこちらの顔が読みとり、直感をはたらかせることなども、それらの裏付けを知っているからこそ役立ちました。
つくづくカラダのしくみは人の集団でこそよく理解できるものだと実感しました。
――執筆中のエピソードなどございましたら。
三村:原稿を書き終えてからでしたが、カラダの情報伝達システムと人社会が似ていると実感したことがありました。
以前から、松本から上田城まで歩いてみたいと思っていたのですが、あるとき松本の老舗のお菓子屋さんで「上田まで○○里」と墨で大きく書かれた大人の背の高さくらいの看板を目にしました。骨董品的に店内に置かれていたのですが、それには「保福寺峠(ほうふくじとうげ)を経て」とも書かれていました。上田までは自動車道路沿いを歩くしかないものと思っていたので、それだったらその峠を歩いてみようと思ったわけです。
松本の北のひなびた村まで別の峠をこえて行き、村落を過ぎてさらに長いのぼり坂を歩きました。行けども行けどもつづら折りの坂が続き、リスに出会う以外にはだれにも出くわすことのない廃れた山道でした。松本から4.5時間かかってようやく保福寺峠に着きました。それまで展望がきかなかったのに、ふり返ると北アルプスが忽然と目の前に見え、茶屋のあとがあったりして、向こう側の上田から来た人はそれまで見たこともない世界を目にしてさぞ驚いただろうと思いました。わたしはその峠を上田の方へ下りていき、知らない村をたどっていきました。結局、上田まで17時間かかりました。
実はその古道は奈良時代にできた「東山道(とうさんどう)」という大きな道路だったのです。畿内(京都)から近江(おうみ、現在の滋賀)、美濃(みの、現在の岐阜県南部)、飛騨(ひだ、現在の岐阜県北部)、信濃(しなの、現在の長野)を通り、東北や江戸へ抜ける、当時、律令国家が国を治めるために整備した全国に七つある駅路のひとつです。
畿内からの発令を東北へつたえ、地方から中央へ情報を吸い上げるための公道でした。それをサポートするように30里(16キロメートル)ごとに駅(うまや)がおかれ、役人が使うための馬が飼われていました。
実際に歩いたのは東山道のごく一部にすぎないのですが、京都から多賀城まで実に最短のコースをたどっています。それは情報伝達を素早くするためにそうなったのでしょう。700年初頭にグーグルの地形図などもちろんなかったのですが、鳥の目で俯瞰したように当時の国と国との境を難所であろうが急所であろうが峠をたどり道程が短くなるようにつくられています。
そして驚くことに、この七道そのものや駅は現在では地中に埋もれたりしているのですが、1960年代から全国の主要な高速道路を建設するようになってから、その工事中にそれらの古道が見つかるようになりました。つまり、律令国家の時代に整備した日本中の情報伝達のための幹線道路の道筋が現代の主要な高速道路のそれらに一致しているのです。人は、社会をつくるとき合理的にするものだ、と感心しました。
もうひとつ合点したのは駅制についてです。まるでカラダ中をめぐるリンパ管のリンパ節であったり、血管の内皮細胞のように感じました。昔の村や宿(しゅく)がカラダの情報網や物流システムに組みこまれているのだと思いました。
――本書のポイントはなんでしょうか。
三村:人のこころを含めたカラダのしくみは、じつに整然とできています。
まるで人がそれぞれに生業をもちそれに打ちこみ、それによって口を糊し、笑い、泣き、善良な人たちの生活そのもののようです。わたしたちがなんともなくカラダを動かし、あたりまえに生活していけるのは、細胞たちが休むことなく、カラダのしくみを支えるシステムを動かしているからです。
異なる点としては、人社会では縦割りのところがありますが、カラダは横にも斜めにもシステムどうしが連携しています。また人社会に比べると壮大で無駄なところもあります。そして、おそらく、未だ人が知り得ない、あるいは人の常識を逆転させるようなシステムが隠されている気がします。
本書で紹介したカラダのしくみの数々について、知識を知ってもらうことより、そんな「カラダの知恵」を感じてもらえたら嬉しいですね。
――最後に、読者へのメッセージをお願いします。
三村:わたしからのメッセージは三つあります。
まず、「カラダのしくみ」を知る旅に出よう!
見たこともない街や風景、聴いたことのない音、接したことのない文化など、「カラダのしくみ」にはそんな新鮮な驚きでいっぱいです。
そして「カラダのしくみ」をお手本にしよう!
みなさんはプライベートでも仕事でも行き詰まってこれはもうダメだ、と思うことがあるでしょう。そんなときわたしはいつも『いま、ここに』と考えます。どんな具合の悪いときでも生物は35億年のあいだピンチを脱してここにたどりついたのですから、自分のカラダのなかにもピンチを乗り切る知恵がきっと隠されていると思っています。
最後に、「直感」を大切にしよう!
自分を信じて、直感を鈍らせないようにしよう。そのためにはいつも感性を磨く。新しいことを知り、やってみる。そうしていくうちに自分の本当の声がはっきりと聞こえてきます。
――ありがとうございました。