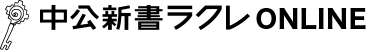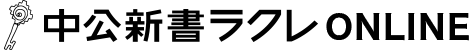今年6月、元農水省事務次官がひきこもりだった44歳の長男を刺殺した事件は、世間に大きな衝撃を与えました。
また、船戸結愛ちゃん、栗原心愛さん、池田詩梨ちゃんら、親の虐待を受けた幼い子どもが志望するという悲しい出来事も続いています。老々介護に疲れ果てた末に心中をはかる、といった事件も後を絶ちません。
読売新聞社会部は、家族内で起きた事件に焦点を当て、その背景に何があるかを探るべく、取材を続けてきました。
周囲に相談できず、自分たちで問題を抱え込んでしまった当事者たちの苦悩、被害者たちの無念に総力取材で迫ったルポルタージュです。本書の「まえがき」を抜粋し、ご紹介します。
―――――――――
〈まえがき〉
事件報道において、家族内で起きた事件は、ともすれば社会の耳目を集める大きな事件の中に埋もれてしまいがちです。
その理由の一つには、多数の死傷者が出た大事件・大災害、国民生活や企業活動に影響を及ぼすような大型経済事件や、読者の関心の高い著名人が当事者となるような事件の取材が優先されてしまうという事情があります。
もっと本音を言えば、新聞紙面で大きく取り上げる事件に比べて、家族内で起きた事件には「事件性」が薄いという思いが報道をする私たちの側に潜んでいるのだろうと思います。
この「事件性」という言葉は、新聞記者が駆け出しの頃に最初に覚える用語です。
例えば、人が列車に轢かれて死亡したという事案について、誰かにホームから突き飛ばされた結果であれば殺人事件ですが、自殺であれば「事件性なし」ということで、そのこと自体を報道することはまずありません。
「事件性」の有無とは、ニュース価値に関わる用語として使われます。そして、家族内の事件についていえば、それがたとえ殺人事件であっても、身内の問題だという意味で「事件性」が薄いと受けとめてしまうのだと思います。
刑法にも親族間の特定の犯罪については罰しないという特例があります。これは「法は家庭に入らず」という理念、国家は家庭内の問題には介入しないという考え方からきています。
しかし、近年、国や公的機関の不介入と対応の遅れが痛ましい家族内事件に結びつくような事例が相次いでいます。
刑法犯罪が毎年減少する中で、家族内の深刻な事件が急増しているのはなぜか。埋もれた事件を掘り起こし、当事者の生の話を聞いて、その疑問に答えていくことには大きな社会的意義があるはずだと私たちは考えました。
そして、取材を通じて分かったのは、家族内で起きた悲劇の一つひとつに、私たち自身、私たちの家族の誰もが直面するかもしれない苦悩が内在しているということでした。

この連載は、社会部を中心に社会保障部、国際部、写真部の計19人の記者が担当しましたが、記者たちは事件当事者、関係者の話に耳を傾け、事件の背景を浮かび上がらせることで、同じ悲劇を繰り返させない手がかりを示したいという思いに突き動かされて、このテーマに取り組みました。
家族内で起きた事件の当事者に話を聞くという取材の難しさは予想をはるかに上回りました。
家族内事件はプライバシーの壁が高く、警察などから得られる情報も多くはありません。当事者も家族親族や周囲への影響を恐れてほとんど取材には応じてくれません。
取材班は、まず当事者を探すために、読売新聞の全国の支局に残る過去の取材資料を集めてリスト化し、取材メンバーが一人ひとりに取材の趣旨を説明し、取材交渉を行いました。
10人に1人会えればいい方で、中には最初に手紙を書いてから3か月間、手紙だけのやりとりを続けてようやく直接面談できた方もいました。
また、取材の趣旨を理解して取材に応じてくれたものの、記事掲載時になって、「取材の意図には賛同するので掲載は構わない。しかし、自分は心の傷をえぐられるようなことを語っている。その記事は読みたくないし、この話題には今後も触れたくない」と話した人もいました。
第1部「介護の果て」では、高齢者介護(老々介護)を巡る悲劇を取り上げました。高齢化社会の進展に介護家族の支援が追いつかない中で極限まで追い込まれた家族の苦悩を報告しています。
第2部「親の苦悩」は、精神障害や病気、ひきこもりなどに悩んで最愛の子どもに手をかけた親たちの話を集めました。一方で、精神障害で荒れていた息子が就職できるほど回復するまで支えてきた母親の体験など希望につながるケースも紹介しました。
第3部「幼い犠牲」では、児童虐待を正面から取り上げました。わが子を虐待死させた加害者、それを防げなかった関係者に直接取材し、父親の性的虐待を受けた被害者の生々しい証言も報じました。この連載の後、東京都目黒区の5歳女児や千葉県野田市の小4女児が犠牲になった虐待事件が起きました。本書では、これらのケースについても加筆しました。
第4部「気づかれぬ死」では、地域社会から孤立し、家族にも親族にも看取られずに亡くなっていく「孤立死」をテーマにしました。孤立死は、刑事事件ではありませんが、家族や親族にとってはショッキングな事件にほかなりません。この連載に合わせた独自調査で、2016年の1年間で孤立死が全国で少なくとも1万7000人を超えていたことも初めて明らかにしました。
第5部「海外の現場から」では、第1部から第4部で取り上げた各テーマに関し、支援先進国といわれるイタリア、英国、米国、フランスにおける取り組みと、そうした国々でも今なお悲劇がなくなっていない状況をリポートしました。
一連の記事からは、戦後70年を経た日本で、少子高齢化と核家族化、都市化などで地域社会の結びつきが希薄化し、孤立した家族が周囲に相談できないまま問題を抱え込み、悲劇を生んでいるという実態がまざまざと伝わってくると思います。
タイトルの「孤絶」という言葉は、「世間とはつながりがなく孤立していること」を意味します。
インターネットが発達し、どんな商品もネットで注文できるような便利な世の中になって、社会の高齢化がさらに進み、隣人との付き合いがなくなって来れば、私たちの誰もが、この連載に取り上げられたような苦悩に直面する可能性は高いと思います。

昨年12月に法務省が公表した「平成30年版 犯罪白書」において、「進む高齢化と犯罪」という特集が組まれました。
日本の刑法犯の認知件数は、2002年をピークに年々減少を続け、2017年も戦後最少を更新する一方、検挙数に占める65歳以上の高齢者の比率は約20年の間に4・2%から21・5%に急増しています。
白書に掲載された高齢者の殺人事件に関する特別調査の結果は衝撃的でした。
高齢者が起こした殺人事件の被害者は、配偶者・親・子といった親族が約7割を占めており、犯行動機のトップは、「問題の抱え込み」(約7割)でした。
「問題の抱え込み」とは、社会的に孤立し、他の解決方法が選択できずに一人で問題を背負い込んだことが犯行の背景となっており、刑事裁判の判決でも「同情の余地がある」などと認められた事案です。
また、高齢者による殺人事件の被害者が自身の子どものケースでは、子どもに「精神の障害」があるとされたのが9割にも上っており、白書は「障害等を抱えた子の対処を、誰にも相談できないままに抱え込んだり、子の暴力・暴言に思い余って犯行に及ぶ状況が推察される」と指摘しています。
一方、被害者が配偶者のケースでは、被害者が精神・身体のいずれか又は双方の障害を抱えているとされたのが5割に上り、約3割は被害者が「要介護・寝たきり」や「認知症」の状況にありました。
この点について白書は、「高齢者特有の将来に対する不安や、自身と同様に高齢である配偶者との生活に行き詰まりを感じながら、これを抱え込んだままでいることが、殺人という悲劇につながった例が少なくない」と分析しています。
この犯罪白書の特別調査の結果は、まさに読売新聞が一年以上かけて報じてきた内容を、数字的に裏付けるものでした。
家族内事件の背景にある介護や心身の障害、ひきこもりといった事情を家族が抱え込まないようにするために、社会全体がそうした家族の物理的・心理的負担を軽減していくための知恵を出していく必要があります。
また、幼い犠牲を出さないために、子どもたちのSOSを見逃さず、社会が適切に対処していく制度を早急に構築していく必要があると思います。
本書がその一助になればと願っています。
読売新聞社会部