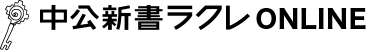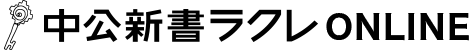アメリカのトランプ大統領は、米朝首脳会談を通じて「恋に落ちた」と金正恩を讃えた。
その北朝鮮の背後にあって「海洋強国」を目指す習近平国家主席率いる中国。
朝鮮半島は中華圏に引き寄せられ、日本は米中衝突の最前線で烈風に曝されつつあるのかもしれない。
そこで「米朝開戦か! 」と騒がれていた2017年秋、早くも「米朝はいずれ結ぶ」と言い当てたインテリジェンスの巨匠2人に依頼。最新の世界情勢に基づいた予想と主張を一冊に整理。
今回その注目の新刊『米中衝突』から"はじめに"をご紹介。
「新アチソンライン」という新たな視座とともに提示される驚愕のシナリオとは一体? 今そこにある日本の危機を直視せよ!
----------------
はじめに
あれは凍てつく冬の出来事だった。
ベルリンの壁が崩れる二年前の一九八七年の暮。アメリカはクレムリンの最高権力者を西側同盟の司令塔に迎えていた。われわれホワイトハウスの特派員にとって、ソ連共産党の書記長、ミハイル・ゴルバチョフのことならどんな些細な動きもニュースだった。
そのゴルビーの身辺に異変が起きたらしい----。大統領補佐官たちの動きが俄かに慌ただしくなった。いつもは温顔を絶やさないアメリカ大統領、ロナルド・レーガンも不安げだった。ホワイトハウスへの到着がもう一時間以上も遅れていたからだ。ソビエト大使館で副大統領、ジョージ・ブッシュと朝食を共にした書記長は、大型リムジンに乗り込んでこちらに向かっているはずだ。
その時、書記長はコネチカット通りの交差点で突然車から降りてしまった。そして街頭で手を振る市民たちのなかにさっさと分け入り、こうロシア語で語りかけた。
「さて、ソ連とアメリカは、どうやって歩み寄っていくか。ここはひとつ、あなたがたもレーガンさんの背中を押して力を貸してください」
米ソ両超大国が核の刃を突きつけあっていた時代のハプニングだった。前方を走っていた警護の車列は、ボスのリムジンを置き去りにしたことに慌て一斉にバックした。新聞は「さながら映画のフィルムを巻き戻したような光景だった」と報じた。レイキャビックの米ソ首脳会談が決裂した記憶はまだ癒えていなかったからだ。ようやく姿を見せた賓客を迎えたレーガンも「お国に帰ってしまったかと思いましたよ」と安堵の表情を見せた。中距離核戦力(INF)全廃条約はこの二日前にホワイトハウスで調印され、冷たい戦争を終わらせる前奏曲が奏でられようとしていた。だが、それも小指で触れればたちまち崩れ落ちてしまう情勢下での合意だったのである。

あろうことか、異形の大統領、ドナルド・トランプは、このようにしてまとめられたINF全廃条約という安全装置を取り外そうとしている。二〇一八年十一月の中間選挙を意識して離脱の舞台に選んだのは、核兵器開発の揺籃の地、ネバダ州だった。だが、この決断はいつものトランプ流の思いつきではない。国家安全保障担当大統領補佐官、ジョン・ボルトンを直ちにロシア大統領、ウラジミール・プーチンのもとに派遣し、INF全廃条約を死に至らしめる旨の通告をさせている。この条約が禁じている射程五〇〇キロを超す巡航ミサイルをロシア側が開発・製造しているというのがその理由だった。
アメリカのINF全廃条約からの離脱によって「米中衝突」の幕があがった----後世の歴史家はこう記すことになるかもしれない。中距離核の縛りを解けば、米ロ両国は核軍拡競争に突入せざるをえない。ロシアは日本の対岸にも巡航ミサイルを公然と配備し、在日アメリカ軍基地を標的とするだろう。加えて、INF全廃条約に加盟していない中国も中距離核の開発競争に巻き込まれていくはずだ。そうなれば、東アジアは核の戦場になる危険が高まってしまう。「トランプのアメリカ」にとっての主敵は「プーチンのロシア」ではない。いまや「習近平の中国」なのであり、危機の本質はここにある。
アメリカのメディアにはいま「新冷戦」「冷戦Ⅱ」という言葉が溢れている。冷戦の時代、米ソ両陣営は核兵器を手に厳しく対峙したが、核戦争だけは辛くも免れた。それゆえ「冷たい戦争」と呼ばれたのだが、「新冷戦」の時代にあっては、核の使用を縛る安全装置を欠いている。冷戦の統帥部に集った司祭たちは、核ミサイルへの防衛手段を制限し、互いの国民を核戦争の人質に差し出す弾道弾迎撃ミサイル(ABM)制限条約を考え出し、中距離核の全廃条約の締結に漕ぎつけたのだった。核戦争の防止装置は、ガラス細工のように繊細で脆い仕組みだったが、「トランプのアメリカ」はそれすら破り捨てようとしている。

二〇一八年十月四日、アメリカ副大統領、マイク・ペンスは「ハドソン研究所」で演説し「米中衝突」の時代に入ったことを宣言した。このなかで、中国の習近平政権は、アメリカからハイテク技術を掠め取る「メイド・イン・チャイナ2025」政策を推し進め、「一帯一路構想」を通じて近隣諸国を債務で搦めとる外交戦略を繰り広げていると批判。さらに、内にあってはウイグル人やチベット人などの少数民族を抑圧し、外にあっては南シナ海に人工島を造って海洋の支配圏を確立しつつあると非難した。米中の対立は、高関税という切り札を互いに繰り出す貿易戦争にとどまらず、海洋を舞台にした軍事力の対決の様相を濃くしている。
こうした情勢のもと、日本の総理、安倍晋三は二〇一八年十月下旬、七年ぶりに中国を単独で訪れ、国家主席、習近平とひざ詰めで話し合った。この釣魚台会談はいつになく和やかだった。習近平は「客観情勢の変化が中日双方にとって高度な協力の可能性をもたらした」と思わせぶりに微笑んだ。高関税のこぶしを振りかざすトランプは、中国ばかりか日本とも軋轢を生んでいる。ならば、日中両国は互いに連携し、こうした負の潮流に抗っていこうではないか、と誘いかけたのだろう。ありていに言うなら、日米同盟にくさびを打ち込もうとしたのである。
保護主義に傾くトランプ政権を牽制するには、「中国カード」を切るのがいい----。安倍官邸を支える経済産業省の官僚群は、習近平の中国の誘い水を好機と考えたのだろう。習近平政権が推進する「一帯一路構想」にも歩み寄る姿勢を示してみせた。通商交渉だけならそんな戦術もあり得よう。だが、日米同盟は、通商分野にとどまらず、外交そして安全保障に及んでその裾野は遥かに広い。加えて太平洋を横断する日米の同盟関係は、東アジアの安定に資する「国際公共財」でもある。習近平の中国を取り込んでトランプの保護主義を抑え込む。日本の対外戦略がかかる浅薄な発想に基づいて発動されるなら、やがて太平洋同盟の基盤は喪われていくだろう。

中央公論新社の求めで佐藤優さんと一年を経ずに新たな対論を編むことになった。前著『独裁の宴』(二〇一七年)でわれわれが示した、いずれ米朝は結ぶという見通しは、ほぼ現実のものとなった。その一方で、東アジア政局はダイナミックに変貌を遂げつつある。これほどの変化は、冷戦が幕を下ろした一九九〇年前後以来のことだろう。本書では、東アジア政局、とりわけ朝鮮半島という鏡に映し出された「米中衝突」の実相を多角的な視点から検証してみた。いまのニッポンは、超大国アメリカの傘から抜け出し、荒海に向かわざるをえない。この国に暮らす人々のインテリジェンス能力にいっそう磨きをかけて新たな針路を定めることに、ふたりの仕事がささやかでもお役に立てるなら幸いである。戦後日本に突然降臨した、佐藤優という孤高のインテリジェンス・オフィサーから近未来を読み解く極意を存分に吸収していただきたいと思う。
手嶋龍一:外交ジャーナリスト・作家。9・11テロにNHKワシントン支局長として遭遇。ハーバード大学国際問題研究所フェローを経て2005年にNHKより独立し、インテリジェンス小説『ウルトラ・ダラー』を発表しベストセラーに。近著『汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師』のほか、佐藤優氏との共著『インテリジェンスの最強テキスト』など著書多数。
佐藤優:作家・元外務省主任分析官。1960年東京都生まれ。英国の陸軍語学学校でロシア語を学び、在ロシア日本大使館に勤務。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、09年6月、執行猶予付き有罪確定。13年6月、執行猶予期間満了。『国家の罠』『自壊する帝国』『修羅場の極意』『ケンカの流儀』『嫉妬と自己愛』『独裁の宴』など。