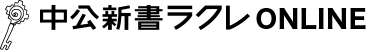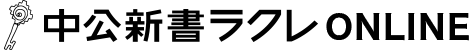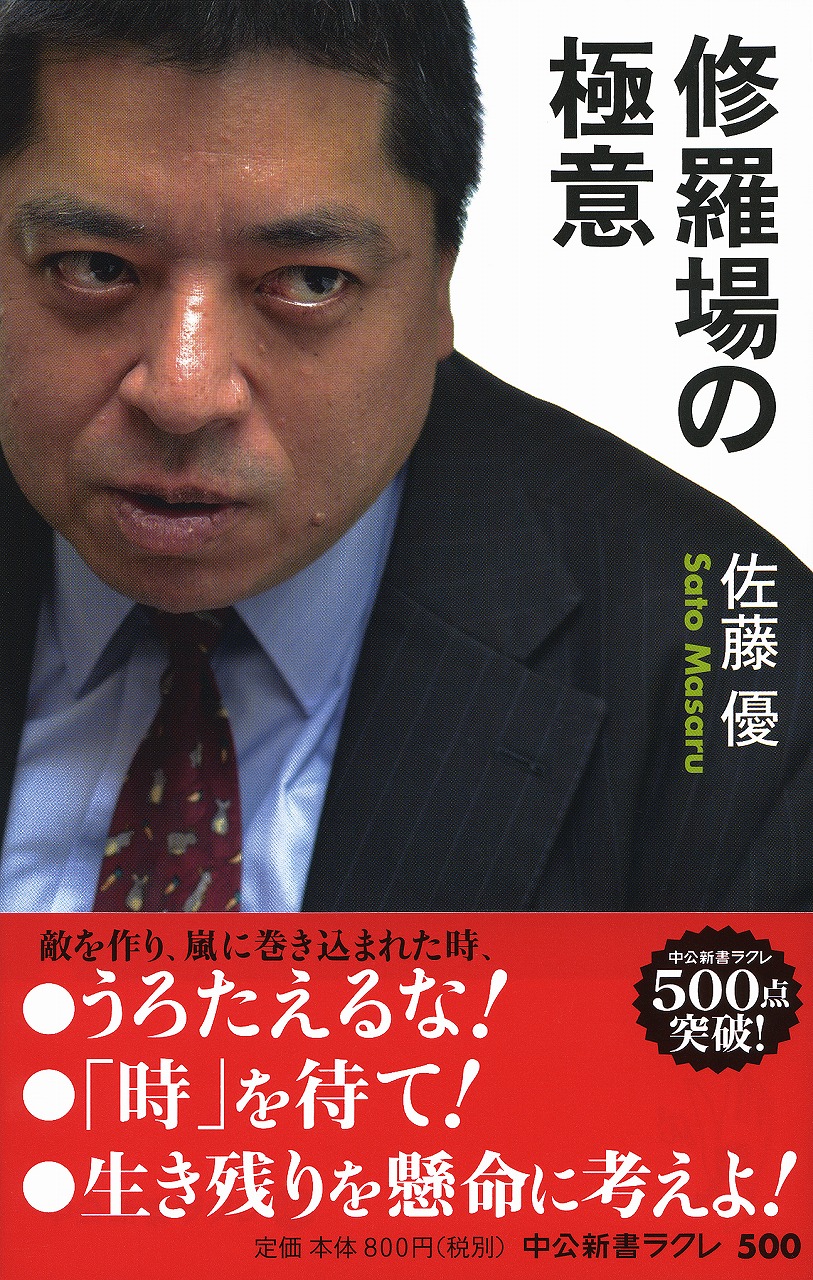文字どおり酸いも甘いもかみ分けたお二人に、「アナログな修羅場」から「デジタル時代ならではの修羅場」まで語り合っていただきました。
なお、この対談は雑誌『中央公論』2014年6月号でさらに詳細を楽しめます(記事タイトル「相手の『拍子抜け』を誘って切り抜けろ!」 )。
『修羅場の極意』では、佐藤さんと西原理恵子さんの対談『「最悪」のシミュレーションだけすればいい』を掲載しています。ぜひ中瀬さんの極意と、西原さんの極意を読み比べてみてください!
*構成 ラクレ編集部 黒田
- ■「一日一修羅場」の時代
- 中瀬:
雑誌『中央公論』での連載「修羅場の作法」はすごく面白いです。本にまとまったのですね。おめでとうございます。
第一章がマキアベリから始まるのは、意外でした。佐藤さんがマキアベリを書くのは、はじめてなんじゃないですか。マキアベリという人物は、佐藤さんにすごくハマっているからこそ、かえってこれまで機会がなかったのかもしれませんね。
- 佐藤:
正確に言うと、一回だけ塩野七生さんの本の解説文で書いたことがあります。ですが、自分の本できちんと書いたのははじめてですね。
本書はマキアベリからはじまって、ヒトラーらの反面教師、中瀬さんのご友人・西原理恵子さんら12人を取り上げて、修羅場を切り抜けるための作法を検証したものです。
「修羅場」というテーマは、これからの時代にぴったりのテーマなんです。なにしろ右肩下がりの時代ですから、毎日が生き残りに必死の修羅場と言っていい。
- 中瀬:
ふと気づけば、日々、「プチ修羅場」がありますね。
- 佐藤:
城山三郎さんに『毎日が日曜日』という作品がありますが、今は「毎日が修羅場」(笑)。いつ組織から追い出されるかわかりません。
- 中瀬:
佐藤さんほどの大変な修羅場を経験した人はなかなかいないと思いますが、誰であれ、「一日一修羅場」の時代ですよね。
修羅場を切り抜けるには、自分の状況よりももっとすごい修羅場の話を聞くと相対化できるので、乗り切れるということがあると思います。本書に登場する12人の修羅場の話は、そういう意味でも役にも立ちますね。
- 佐藤:
そうですね。
「より大きな修羅場体験を知っていると困難を乗り越えられる」は修羅場の極意のひとつですが、それに関連して思い出すのは、私が鈴木宗男事件に連座して、「鬼の特捜」(東京地方検察庁特別捜査部)にパクられたとき、母親がパニックを起こさなかったことです。母親は、沖縄戦の経験があったからこそ、事態を受け止められたのでしょう。私自身にとっても、あのときパクられた経験が今役に立っていて、その後の飯のタネになったと同時に、他人とあまりケンカしなくなった。万が一、ケンカをする時は、よく考えてからするようになった。
不思議な話なのですが、裁判が続いているあいだのほうが国家権力は怖くないものなんですよ。逆に、去年の6月30日に執行猶予期間が終わって、自由になってからのほうが怖くなってくる。
本書で取り上げたドストエフスキーも一緒です。ドストエフスキーは革命運動をしているときは死刑になる覚悟ができていた。しかし、銃殺される直前で命を皇帝の恩赦によって救われた体験をしたがために、死ぬことが怖くなってしまったのです。
国家権力には殺すことだけでなく生かすこともできるということを知ると、本当に国家が怖くなります。
- ■「ゾンビ化」するデジタルデータ
- 中瀬:
国家権力と対峙している人といえば、最近では同じく本書に登場するスノーデンも注目の的ですね。
佐藤さんは『スノーデンファイル』(ルーク・ハーディング著、日経BP)に推薦文を寄せられていますが、私も一足先に出た『暴露:スノーデンが私に託したファイル』(グレン・グリーンウォルド著、新潮社)を読んですごく面白かった。
スノーデンは「天井から監視されているかもしれない」と思って、服を頭からかぶって作業をしたり、携帯電話を冷蔵庫に隠し入れたり……そこまでやるか、という行動が私にとっては印象的でした。
- 佐藤:
携帯電話を冷蔵庫や電子レンジに入れると、電波を遮断することができるんですよ。それはよくある手口ではあります。
スノーデンは最近、プーチン大統領と国民との対話の集会にビデオ出演をしました。そこで、プーチン大統領への質問として「ロシアは一般国民に電話盗聴・通信傍受しているか?」と尋ねたのです。プーチンは、「やっていない」と答えています。日本ではちょこっとニュースになった程度ですが、こういうところにロシアの怖さがある。
どういうことかと言いますと、これはアメリカに対するシグナルなんです。スノーデンが自らの手の内にあるということを見せるための。
プーチンは一人の人間としては、腹の底からスノーデンを軽蔑している。インテリジェンス・オフィサーであるにもかかわらず、忠誠を尽くすべきアメリカ国家を裏切ったからです。ですので、プーチンはスノーデンを単なる道具という意味で利用はするが、尊敬していません。
- 中瀬:
「裏切り者」は「敵」よりも始末に悪いということですね。
- 佐藤:
その通りです。
スノーデンは当初、命を捨てる覚悟で国家を告発したはずですが、ロシアで自由の身になったとたん、今や完全にロシアの「操り人形」になってしまいました。彼を見ていると、人間の強さと弱さが隣り合わせにあるということが実感できます。- 中瀬:
本書『修羅場の極意』では、「元インテリジェンス・オフィサーは存在しない」というプーチンの言葉を引用なさっていますね。「インテリジェンス機関に勤務した者は、一生、この世界の掟に従い、国家に奉仕すべきである。この掟に背いた者は殺されても文句は言えない」のだと。
- 佐藤:
インテリジェンスの世界には脱会規定がないのです。これはキリスト教と似ていて、キリスト教には「破門」しかない。脱会規定がないというのは、きっとキリスト教文明ゆえなのでしょう。
日本人のように「水に流す」という感覚はありません。「水に流す」というのは、「許してやるから、もう忘れる」という意味でしょうが、彼らの場合、「忘れないし、許さない」か「忘れるけど、許してやる」のいずれかです。水に流して忘れることは絶対にない。
- 中瀬:
EUで「忘れられる権利」の裁判(検索結果に、過去の記録が表示されないように求める裁判)が起こっていますが、忘れてもらうのも大変な時代ですね。一回、ネットに刻まれると永遠に記録が残ってしまい、就職や結婚などの機会に検索されて何かがバレるなんてことも起こりえる。
- 佐藤:
データが、まるで「ゾンビ」のように生き返る。
- 中瀬:
そう。「人の噂は75日」なんてのはもはやファンタジーです。
- 佐藤:
元情報屋は、フェイスブックやツイッターに登録はするけれども、実際の利用方法は見る程度で、警戒心から自ら発信しません。
スノーデン事件後、世界的にタイプライターが売れていますが、要するに、電子的なものはぜんぶ傍受される危険があるから、あえてアナログなものを選ぶ人たちが増えているのでしょう。
- 中瀬:
佐藤さんも、メールはあまり打ちませんよね。返信も素っ気なくて「了解しました」だけとか。留守電も残したりもしないし。(笑)
- 佐藤:
それは習慣ですよね。誰かに見られている、誰かに聞かれているというのは習慣になっているんです。
あっ、ただ、冷蔵庫やレンジには携帯を入れないほうがいいですよ。電波は遮断できても、日常的にそういうことをしていると、「その筋」のプロたちに知られたとき、「なんで隠したんだ、怪しいぞ」と疑われかねないし、物理的な尾行をされ、何か弱みを握られる可能性があります。
- 中瀬:
レンジで携帯をチンしちゃうなんていう、大惨事もありえますしね。(笑)

中瀬ゆかり氏
(2014年5月20日 於・中央公論新社。写真撮影・和田直樹)
中瀬ゆかり(なかせ・ゆかり)氏
編集者。新潮社勤務。『新潮45』編集長などを経て現在、出版部部長。『5時に夢中!』(東京MXテレビ)のコメンテーターとしても活躍中。
佐藤 優(さとう・まさる)氏
作家・元外務省主任分析官。著書多数。