
-新書編集者の面白さはどこにありますか
新書とは、幅広い一般読者を対象とした入門書、概説書。歴史や文化、政治や社会や科学など、分野を牽引している研究者にご執筆を依頼することが多いです。その世界の第一人者に話を聞きながら、まだ存在しない本の輪郭が見え始めるとき、えもいわれぬ感覚を味わうことがあります。
いままで知られていない事実を探究する旅人に、「やあ、どこへ行くのですか」と声をかけ、いつのまにか旅路を共にする。著者が辿りついた境地、書き留めた記録を後世の人々に伝える。そういう喜びを感じる仕事です。
-ONとOFFはどのように切り替えていますか
ゆるくONとOFFがつながっている気がします。休日に見聞したほんのちょっとしたことが新しい企画につながることも。でも常時接続だと気が休まらないので、自分をすこし突き放して、斜め上から眺めることを意識したりします。仕事や休息や遊びなど、場面に応じて自分に声をかけることでモードを切り替えています。

出社。メールをざーと返信。他社新書レーベルの新刊や学会誌、担当している本の在庫状況、書店での売れ行きをチェック。
ゲラを読む。著者の文章がどれだけ読者に伝わるか。そのことを考えながら、じっくり読み進め、エンピツや赤字を書き入れます。

早めの昼食。12階の社員食堂はメニューが豊富なのが嬉しい。食堂横には草木茂るテラスがあり、リフレッシュして著者打合せへ。
慶應大学へ著者の研究室を訪ねる。不思議なもので、同じ空間で話していると、思いもよらなかったアイディアが見えてくる。

月に一度行われる編集部のタイトル会議。3か月後に出る中公新書4~5点のまえがき・目次を読んで、読者に響きそうなこれはというタイトル案を考え、編集部全員で議論します。他の編集者ならではの視点や技術を学ぶ貴重な機会です。
中公新書『言語の本質』をロングセラー・定番書にするうえでどのような販売施策、新しい帯が有効か、営業担当と打合せ。ワンフロア―だから、他部署との接点が多い。
退社。都内のエレクトリックジャズのライブへ。たゆたう音の粒が、東京の夜に溶けこむよう。



耳にあて、景色がきゅっと引き締まる瞬間がなんとも。音楽を聴くほか、原稿に潜って集中して読むときや、著者のインタビューを文字起こしするときにも使います。

お茶をのむと気持ちが落ち着きますし、よい気分転換に。ジャスミン茶、紅茶、プーアル茶など。リップクリームで心がうるおうことも。
就職活動中のみなさんへ
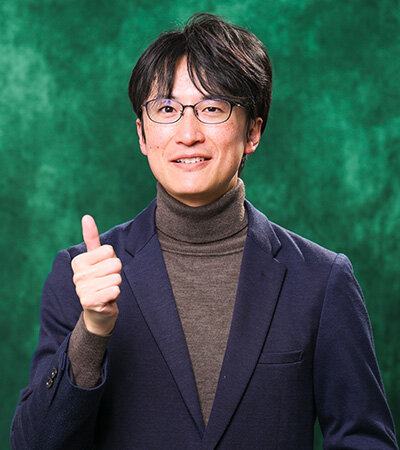
就職活動中のみなさんへ
出版界のことをひととおり知っておくこと。向けられそうな問いをできるかぎり想像し、その答えを自分の中に(いちおうの形でも)持っておくこと。RPGではないですが、事前に装備や経験値を上げておけば、憂いなしです。
本が辿ってきた5000年の歴史を思うと、そのポテンシャルの大きさを、私たちはまだ半分も理解していないかもしれません。新しい本、過去にない出版の形をつくることに参加してみませんか。焦らずに、肩の力を抜いて、前向きに臨んでいただければ嬉しいです。






