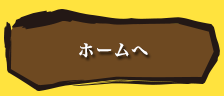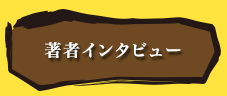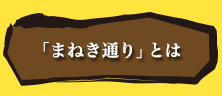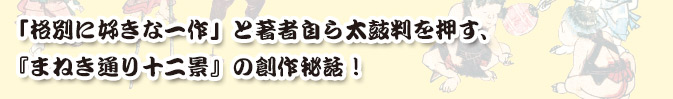
山本一力さんの『まねき通り十二景』が装いも新たに、文庫化された。
江戸・深川にある小さな商店街の十二か月を、十二の連作短編として描いた笑いと人情あふれる作品。作者自ら「自分の深川ものの集大成」と語る自信作でもある。「まねき通り」とそこに住む人々に寄せる思いを、山本さんに聞いた。
(聞き手=石田汗太)
――「まねき通り」は架空の町とのことですが、江戸・深川には、きっとこんな町があったんだろうなと感じさせます。発想はどこから?
山本  yorimoというネット媒体での連載だったので、さあどういう話にしようかと考えた時、短編連作で、全体としてひとつの物語性があるものにしたいと思ったんだ。そこで編集者と話し合って、一ヵ月で一話、正月から始めて、一年で十二話の短編をひとつの町でやろうって大枠が決まった。十二通りの話を作るには、商店がたくさんなきゃなと思って、まず自分で通りと店の地図をこしらえたんだよ。地図があると、すごく物語の展開が楽になるんだ。
yorimoというネット媒体での連載だったので、さあどういう話にしようかと考えた時、短編連作で、全体としてひとつの物語性があるものにしたいと思ったんだ。そこで編集者と話し合って、一ヵ月で一話、正月から始めて、一年で十二話の短編をひとつの町でやろうって大枠が決まった。十二通りの話を作るには、商店がたくさんなきゃなと思って、まず自分で通りと店の地図をこしらえたんだよ。地図があると、すごく物語の展開が楽になるんだ。
――「まねき通り」のある深川冬木町は、今の東京都江東区冬木ですよね。あえて想像するなら、現在の区立深川第二中学校の近辺でしょうか。
山本イエス、イエス。俺、冬木って好きなんだ。昔近くに住んでたし、仙台堀が流れていて、木場があって、材木問屋の町だよね。でも歴史的に見て、冬木はあんな商店街ができるような町ではないけれど。
実は、新宿六丁目に「まねき通り商店街」っていう小さな商店街があるんだ。俺のおふくろが昔そのあたりに住んでいて、「まねきに行ってくるよ」ってよく言っていた。その名前が好きでさ、いつか使ってみたいと思っていてね。架空の町のほうが自分の書きたい物語ができるから、物語に合わせて商店街を作っちゃおうと思った。
――想像の町にしては、非常にリアルです。
山本「まねき通り」は仮想の商店街でも、俺にとって冬木は、生活エリアとしてよく歩いた場所なんだ。時代小説だから、同じ場所に立っても、小説の登場人物と同じ風景を見ることはない。しかし、同じ地べたを踏むことで、伝わってくるものはたくさんあるんだな。今年は『ジョン・マン』の取材で何度もアメリカに行ったけれど、万次郎と同じ場所に足を踏ん張って立つことで、時を超えて感じ取れることがいろいろあった。それが、物書きが取材をすることの意味だと思うな。作家は想像力が何より大事なんだ。見えないものを見る力と言えばいいかな。
――アーサー・ヘイリーがお好きと聞いています。『まねき通り十二景』の発想は、ヘイリーの代表作『ホテル』を思わせます。
山本発想の原点はまさにそこだよ。俺、一番最初に読んだヘイリーが『ホテル』だったから。結果として、かなり違うものになったけれど、ああいうグランドホテル形式をやってみたかったってのはその通り。だから、「ああ、やりたいことを結構やれたな」って達成感はあったね。「まねき通り」という商店街の中で、自分が思いきり遊べたっていう感じかな。
――第一話「初天神」に登場するのが、駄菓子「うさぎや」の徳兵衛さん。その後、他の人のエピソードにも絡んで、次第に物語を引っ張る存在になっていきます。これは最初から狙って?
山本池波正太郎さんが「(連載ものは)行き先も結末もわからないまま、まずスタートする」って言っておられるけれど、俺もまったく同感なんだ。スタートとゴールをガチガチに決めて走ると、作者が考えることは読者だってわかるわけだから、先読みしちゃう人がきっといる。でも、作者に先がわからなければ、読者にだってわからないよな(笑)。徳兵衛については、書いているうちに育ってくれた。だから、こんな展開になるとは思っていなかったね。
一年の暦に従って連作をやっていくと、どんどん先のプロットが湧いてくるんだ。第一話を書いてるときに三話目、四話目の話が浮かんできたりね。それで人物も膨らんでいく。それは、やってみて初めてわかったことだね。
――最初は頑固偏屈で、子どもに嫌われていた徳兵衛さんが、一年経つと慕われている。このあたりがとても温かいですね。頑固オヤジたちは「まねき通り」の名物(笑)。
山本 そうなんだよ。今の時代、人に好かれたいとか、嫌われたくないとか、そういう小賢しいことを考えてしまうから、今言わなきゃいけない「馬鹿野郎!」が相手に言えなくなってしまう。その時に「馬鹿野郎!」と言えなかったら、その「馬鹿野郎!」は外に出るチャンスを永遠に失ってしまうんだよ。
そうなんだよ。今の時代、人に好かれたいとか、嫌われたくないとか、そういう小賢しいことを考えてしまうから、今言わなきゃいけない「馬鹿野郎!」が相手に言えなくなってしまう。その時に「馬鹿野郎!」と言えなかったら、その「馬鹿野郎!」は外に出るチャンスを永遠に失ってしまうんだよ。
でも、徳兵衛さんは、人に嫌われるも好かれるも気にせず、自分でやりたいことをやっている。こういう人を大事にしたいのは、生き方がぶれてないから。今の政治家なんて、すぐにぶれちゃうじゃないか。「政治に命かけてます」なんてわざわざ言わなくても、ちゃんとやってる人は理解されるよ。
俺たちがガキの時分、おとなの背中は怖くてドンとしてて、見るだけで伝わるものがあった。今は、世を挙げてみんな饒舌になっているよね。インターネットを見れば一目瞭然だよな。本当に大事なことは、言葉にせずともお互い分かち合えるのが、日本の本来の国民性だったはずじゃないか。それが最近は、アメリカみたいに、全部言わないと相手に通じない国になっちゃった。
「おたがいさま」っていう感覚もどんどんなくなってる。相手が何を思っているのか、どうしたいのかを察することができないんだね。俺が小学生のころ、NHKで『バス通り裏』っていうテレビドラマがあって、「いっしょに開く窓ならば ヤァこんにちはと手を振って」「むこうがとじた窓ならば なぜだろうかとふり返る」っていう歌で始まるんだけども、その歌がまさに「おたがいさま」なんだよ。それが人と人との心のやりとりなんだということが、この歌から伝わってきた。それは子どもの俺にだってわかったんだよ。
――「まねき通り」は「おたがいさまの町」とも言えますね。
山本そう。江戸のころの人は、もっとお互いが相手を慮り、推し量り、「今何を考えてるんだろう、この人は」って考えたと思う。自分勝手な人ももちろんいるんだけど、そういう人も含めて「おたがいさまなんだよな」っていうのが根っこにあった。「おたがいさま」っていう言葉が、いろんなデコボコを包み込む巨大な風呂敷みたいなものだったんだ。「おたがいさま」って言葉をキーワードにして考えていけば、いま解決できることはいっぱいあると思うんだよ。
――無口な徳兵衛さんが、第十話「もみじ時雨」では、実に細やかな気遣いを見せる。
山本そう。「おたがいさま」という言葉を人間にすると、徳兵衛さんになるんだよ。いつもしかめっ面でも、何も言わなくても、やることはやってくれるんだ。
――『まねき通り十二景』の後に出された『とっぴんしゃん』(講談社)にも、何と徳兵衛さんが出てきます。他人のそら似らしいですが(笑)。大人の側から見たのが『まねき通り十二景』で、子どもから見たのが『とっぴんしゃん』。世界が近いですよね。
山本まったくそうよ。その指摘はうれしいねえ。『とっぴんしゃん』は毎日小学生新聞の連載で、あれも、やり始めたらどんどんいろんなことができていった感じだね。『まねき通り十二景』は話数を重ねるたびに世界が広がって、一年で閉じるのがけっこう大変だった。でも、閉じながら、出口は開いているのが『まねき通り十二景』の世界なんだ。作者としては、感情をそこに思いっきり残しているから、いつでもそこに戻ることができるって気はするね。
――そういう意味で『まねき通り十二景』は、深川ものの集大成?
山本まさに集大成だよ。いろんなことを自分で見つめ直せた。まず第一に、十二話の中で、多くのキャラクターを息吹かせていけた。俺、必ず登場人物の詳しい履歴を作るんだよ。小説そのものには全然出てこなくても、それを書くことでその人になり切れるから。とはいえ、普通、長編でも、そこまでやる人物はせいぜい十人ぐらいだよ。それが『まねき通り十二景』の時は全員作ったんだ。
―― 一話一話が短くて、各話が微妙に絡み合っていますからね。
山本そう。あの短い枚数の中で、人物の出し入れをどうするかは、すごく塩梅の難しいとこじゃないか。でも履歴をしっかり書いておけば、その出し入れを間違えないんだな。
何か事件が起きなきゃ物語にならないけれど、日常じゃそうそう事件は起こらない。ごく普通の夫婦の情愛を描きたい時、無理やりデコボコさせた話は似合わない。その人になりきって、寄り添わなきゃ描けないんだよね。そういう意味において『まねき通り十二景』は、確かに俺にとって、ひとつの大きなゴールのようなもので、集大成だと思うよ。
――最近は深川ものだけでなく、『ジョン・マン』(講談社)や、『龍馬奔る』(角川春樹事務所)など、郷里・土佐の英雄を描く歴史大作も次々に手がけています。
山本万次郎と龍馬を書き始めたのは、それぞれ全然違う理由なんだ。万次郎は、講談社創業百周年記念の「書き下ろし100冊」企画のためにスタートした題材で、調べりゃ調べるほど面白いから、本当に書くのが楽しいし、万次郎と一緒に旅をしてる感じがするな。
龍馬は、とても書ける対象じゃないとずっと思ってた。それを「書け」と言ったのが角川春樹さん。初対面でメシ食った時、「一力さん、龍馬、あなたがやれ」って。でもおれも忙しかったし、龍馬は自分じゃできねえと思ったから、その場はお茶を濁したんだけども、春樹さん、会うたびに「いつやるんだ」(笑)。俺が思うに、龍馬は実はたいしたことをやってない。中岡慎太郎という知恵袋がいたから龍馬が光った。じゃあ、龍馬と慎太郎をダブルキャストで書いていいんならやりましょうと言ったんだ。それが、やり出してみると、慎太郎という人間にどんどん魅力を感じてきてね。
俺のひいばあちゃんが生きてる龍馬を見たらしいんだけれど、高知城下のボンボンで、当時から若い女に騒がれるほど様子が良かったんだって。一方、慎太郎は山奥の村の庄屋の息子。土佐で「いちびり」は「お調子者」っていう意味だけれど、龍馬は間違いなく「いちびり」だね。人を惹きつける魅力はものすごかったと思う。で、慎太郎は、自分には龍馬ほどの魅力がないのを知っていて、死ぬまで龍馬の影になった。ここがすごいと思うよね。
――両作とも、主役の子ども時代から描いていますね。
山本万次郎も龍馬も慎太郎も、子ども時代って誰も描いてないんだ。ほとんど史料が残ってないから、自由にやれる。大人になった龍馬を思い浮かべながら、「こういう子どもだったら将来ああなるだろうな」と自分で納得しながら、育てていくのが面白い。
俺が得意なのは、やはり成長物語だからね。『菜種晴れ』(中公文庫)では、二三ちゃんが育っていく足跡の脇に、自分も足跡をつけながら歩いたから、二三ちゃんがその時に感じたことを、俺も一緒に感じられた。もっと言えば、作家は、登場人物の子ども時代を自分の中で体験しないと、大人時代もうまく書けないと思うんだ。
今、中公ホームページで連載している『おいでやす』もそうだね。主人公の文絵ちゃんが生まれる前の両親の話から始めて、文絵が生まれて、御輿のワッショイを子守唄がわりに育っていく。小さいころのことは、覚えてないようで覚えているものだよ。これから時代がドンと飛ぶんだけれど、子供のころに見たり聞いたりしたことが、文絵にとって、ものすごく大事になっていくんだよ。
――そういう意味では、子どもにとって親のあり方も重要。
山本それが、もうすべてを決めると、俺は確信してるよ。必要なのは、やっぱり大人がわきまえを持つってことなんだ。人によく思われたいとか、子供に好かれたいとか、そんな自意識ではなしに、見返りを求めない愛情を子どもに注いでいくってこと。それが人の営みの原点だろうと思う。俺はそういう時代に育ってきて、その意味を語り継いでいこうと自分で決めてるから、何を書いてもやっぱりそうなるわね。
――英雄的な主人公って、あまりお好きじゃないんですね。
山本 うん、全然興味ないな(笑)。それはほかの人がやり尽くしてるわけだし、俺はやっぱり無名の市井の人間を描きたいからさ。万次郎にこれだけ心を動かされるのは、この男をまだ誰も深く書いていないということもあるけれど、あいつは名を求めてないんだよ。最後は今の銀座二丁目あたりで、無名のまま亡くなるんだ。
うん、全然興味ないな(笑)。それはほかの人がやり尽くしてるわけだし、俺はやっぱり無名の市井の人間を描きたいからさ。万次郎にこれだけ心を動かされるのは、この男をまだ誰も深く書いていないということもあるけれど、あいつは名を求めてないんだよ。最後は今の銀座二丁目あたりで、無名のまま亡くなるんだ。
で、明治になってハワイから万次郎を訪ねてきたデーモン神父が、万次郎が正当に遇されていないのを知って憤るんだけれど、万次郎自身は、別に何とも思わなかったと思うな。
万次郎が帰国した時は、船頭の筆之丞、その弟の五右衛門ともども、外国で見聞したことについて箝口令を敷かれて、幽閉に近い扱いを受ける。この筆之丞の直系の人に話を聞いたけれど、本当にしゃべってないので、子孫に何も伝わっていないんだよ。これが日本人のメンタリティーだなって思うんだ。
――名を求めず、己を語らず。
山本そう。人として何をなすべきかを考えれば、答えは自ずと出る。しかもそれをやったのが、英雄じゃなくて、名もない人たちなんだ。普通に生きて、死んで、土に帰ることを当たり前と考える、つまりは徳兵衛のような人たちが、昔はわんさかいたわけよ。そういう時代に、ものすごい憧れを覚えるね。
――では、徳兵衛さん、万次郎、慎太郎は、深いところでつながっている。
山本そう、まったく同じ。俺はやっぱり池波さんがものすごい好きだから。そりゃ長谷川平蔵という人は実在したけれど、「鬼平」の周囲の人物は、みんな池波さんの創作じゃないか。池波さんもやっぱり無名の人を描きたかったんだよ。あの藤枝梅安も、秋山小兵衛もそう。もうね、英雄を描くと、途中でつまんなくなるんだよ(笑)。そんなんだったら、端からやらないほうがいいよな。
――今後も、深川ものをずっと書いていきますか。
山本やっぱり深川ものだよね。深川ものイコール職人ものだと思ってる。来年は「めがね屋」を主人公にした捕物帳を書くんだ。江戸のころは、調べれば調べるほどいろんな職業がある。一つの職業に行きあたると、そこから派生する別の職業もあって、興味が尽きないね。これはまさにアーサー・ヘイリーなんだよ。ヘイリーは死ぬまで職業を追っかけて、徹底的にその職業で物語を描いた。ヘイリーの取材力や構成力には到底及ばないにしても、俺は職業の中に物語があるっていうことは信じてる。
――職業が人を作るということですか。
山本そう。職業が変われば、付き合う人間が変わるじゃないか。仕入れ先もあれば卸し先もある、客もいる、職人もいる。江戸の職業づくしを見たり、看板見たりすればさ、いくつあるかわかんないよな。それぞれの職業で、こういうことが営まれてたんだろうなっていうのを、資料を読み込んで、自分で想像して描くのは楽しいぜ。やっぱり物を作ってる人たちは貴いもん。
――『まねき通り十二景』がまさに、十二の職業が詰まった贅沢な一冊(笑)。
山本そう。町は生きてるから、移り変わりもあるわけだよな。人の出入りも、生き死にもある。俺ね、江戸時代っていうのは、生きること自体が何よりの挑戦だったと思うんだよ。だって、気を抜いたら病気にかかって、あっという間に命をなくすわけだよね。いつどんな天災が襲いかかってくるかもわからない。いろんなネガティブ要素が渦巻く中で、健気に今日を生きる、明日が来ることを信じる、子供を授かって育てる......これ以上のチャレンジはないじゃないか。
それをそのまま書いたんじゃ物語としては成り立ちにくいだろうけど、その中に物語性を考えていったら、これは無限だよね。
――『まねき通り十二景』にも、まだ物語として描かれてない店が残ってます(笑)。
山本うん。これから越してくる人たちもいるだろうしね。そういう意味では、ものすごく裾野の広い話を描くことができたね。来年の話も、二年先の話も描ける、いくらでも伸ばしていける。『まねき通り十二景』はそんな物語。だから、書いてる作者が一番楽しめたよ。
――いつか再び「まねき通り」に戻れる日を楽しみにしています。ありがとうございました。
(2012年11月26日 中央公論新社にて)

一九四八年高知生まれ。東京都世田谷工業高校電子科卒業。旅行代理店、広告制作会社勤などを経て、97年「蒼龍」でオール讀物新人賞を受賞しデビュー。2002年『あかね空』で直木賞を受賞。『損料屋喜八郎始末控え』『大川わたり』『まとい大名』『銀しゃり』『たすけ鍼』『菜種晴れ』『いすゞ鳴る』『ジョン・マン』『朝の霧』など著書多数。
弊社HPにて『おいでやす』を好評連載中!